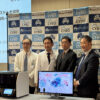浅間氏
日本漢方生薬製剤協会は、漢方製剤などの医薬品に使われる原料生薬の数量を把握するため、「原料生薬使用量等調査」を実施。このほど結果の概略がまとまり、日漢協生薬委員会の浅間宏志委員長が、13日につくば市で開かれた「薬用植物フォーラム2010」で発表した。調査結果によると、わが国で医薬品原料として使用された生薬249種類の数量は、総計で年間約2万トンに上った。そのうち、日本国内で調達できていた割合(重量ベースの自給率)は12%に過ぎず、大半を外国、特に中国からの輸入に頼っている実態が裏づけられた。また、一部でも国内で入手していた生薬は、3分の1強に当たる89種類だった。
調査は、2009年度の厚生労働科学特別研究「漢方・鍼灸を活用した日本型医療創生のための調査研究」に日漢協が協力することとなり、その一環として行われたもの。日漢協に所属する76社に対し、08年度に医薬品原料として使用した生薬の種類ごとの数量と、その入手先国を聞いた。
調査対象とした生薬の種類数は、医療用漢方エキス製剤の原料生薬132種類、一般用漢方210処方の原料生薬150種類、薬局製剤用医薬品の原料生薬136種類、薬価基準収載生薬185種類など、国内で医薬品に用いられる生薬を網羅的にリストアップし、重複等を整理して276種類を抽出。このうち、08年度に使用実績があった生薬は249種類だった。
トータルの使用量は2万トン余で、入手先として国内から供給されていたのは、12%の2480トンに過ぎなかった。輸入先としては、中国が圧倒的に多く1万6916トン(83%)、それ以外の国が967トン(5%)だった。
生薬の入手先を見ると、[1]全て日本国内から入手しているものはコウイ、クマザサ葉など22種類[2]中国のみに依存しているのはカンゾウ、タイソウなど114種類[3]日本と中国以外の国からの輸入だけに依存しているのは17種類[4]日本と中国の2カ所から入手しているのは43種類[5]日本およびその他の国から入手しているのは5種類[6]国内供給がなく、中国およびその他の国からの輸入のみに頼っているのが29種類[7]日本、中国、その他の国の3カ所から入手しているのは19種類――となっている。
使用頻度の高い順に生薬を並べると、カンゾウ、シャクヤク、ケイヒ、ブクリョウ、タイソウ、ハンゲ、ニンジン、トウキ、マオウ、コウイ、カッコン、ソウジュツ、サイコ、ヨクイニン、ダイオウ、ビャクジュツ、ジオウ(熟地黄を含む)、オウゴン、セッコウ、センキュウ、タクシャ、ショウキョウ、センナ、カッセキ、ボタンピ、オウギ、キキョウ、クマザサ葉、チンピ、カンキョウが上位30種類になる。
これら30種類で、使用数量全体の76%を占めている。さらに、上位71種類で95%、117種類で99%に達しており、249種類の半数以上は、ごく僅かしか使用されていないことが分かった。
今回の調査から、医薬品原料としての生薬の入手は、中国への依存度が極めて高いことが改めて浮き彫りになった。一方、日本国内でも249種類の36%に相当する89種類([1]の22種類+[4]の43種類+[5]の5種類+[7]の19種類)が供給されていることから、今後の栽培体制の見直しなどによって、中国への依存体質を改善できる可能性もある。