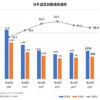日本製薬団体連合会会長 多田正世

昨年を振り返ると、医薬品業界にとっては、2月に抗がん剤の緊急薬価改定が行われるなど、大変厳しい年であったと同時に、改めて「医薬品の価値」を考える年になりました。昨年1月から開始された「薬価制度の抜本改革」に関する中央社会保険医療協議会の議論に対し、日本製薬団体連合会は、新薬、長期収載品、後発品、基礎的な医薬品が疾患領域や各製剤の特性を踏まえて適切に評価され、予見性と安定性のある薬価制度の構築を強く求めてまいりました。
しかしながら、年末に示された「2018年度薬価制度改革」は、総じて薬価を引き下げる方向の提案であると言わざるを得ません。中でも「新薬創出等加算」については、特許期間中の全ての新薬を対象として薬価が維持されるべきとの私共の主張に対し、対象を大幅に絞り込むための品目要件や、極めて複雑で予見性の乏しい企業要件により、多くの品目で薬価が維持されないという予想外の厳しい内容となりました。
また、長期収載品を数年かけて後発品水準まで薬価を段階的に引き下げる新たな制度や、後発品について、収載から12年経過した品目は原則1価格帯とするなど、これらも厳しい内容になりました。このままでは、事業の根幹をなす薬価は継続的に引き下げられ、国内の医薬品事業は立ち行かなくなり、新薬の開発や医薬品の安定供給に支障が生じ、いずれは患者さんの治療に貢献できなくなるのではないかと危惧しております。
この改革が、医薬品産業の成長や企業経営にどのような影響を与えるのか注視しつつ、政府には詳細な分析による検証を強く要望してまいります。
一方、社会保障関係費の抑制を薬価のマイナス改定による財源捻出で対応することは、もはや限界です。十数年の研究開発投資により、約3万分の1という確率の中から創生される新薬の価値は、その医療的便益のみならず社会的便益も含め、正当かつ精緻に薬価において評価されるべきです。また、安全性面の改善や新たな剤形の追加・投与経路の開発など、新しく市販後に追加される価値も同様です。
私共は、ゲノム情報・AIなどの世界最先端の科学技術や基礎研究を基盤とし、医療の質の向上に資する新薬を創生し、いずれは国民負担の軽減に資する基礎的医薬品・後発品・OTC医薬品などに道を譲る、というイノベーションサイクルを確立し、より高い創薬力を持つ産業構造に転換していきます。そして、人々が世代を超え持っている「健康長寿でありたい」という願いに応えられるよう、努めてまいります。