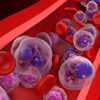このところ薬業・薬学関係者の葬儀が多いように感じるが、その席で「死因は○○癌だった」という会話が昔より多くなった気がする。一方で、「去年は、うちの父親が癌の手術をして、その後も化学療法で大変だったが、いまは落ち着いている……」など、癌と共に生きる人々が身近な存在になっている。
それほど昔ではないが、癌といえば、本人には知らせない、また医療機関側のインフォームドコンセントも今のように徹底されてはいなかった。それが高度な抗癌剤の開発や、的確な治療計画の実施など医療レベルの向上により「決して直らない、死の病」から、日常的な疾患とまではいかないものの、癌になっても悲壮感のみが漂うような状況は減りつつある。
とはいえ「人生の終末期をどう有意義に過ごすか」という大きな命題は、本人ばかりでなく家族にもつきまとい、それを支える関係職種の支援が望まれている。患者が亡くなった後は、遺族の精神的疲労に対する何らかのフォローも不可欠で、場合によっては、精神科医による適切な治療も必要だ。
最近では癌の専門病院に、緩和ケアチームが構成されるようになり、「精神腫瘍科」という聞き慣れない専門科も設置されつつある。癌治療・ケアをめぐる病院環境については、次第に整いつつあるようだ。
また、医療費削減を“錦の御旗”にした医療制度改革、診療報酬体系の変更など「政策による誘導」もあり、病院の機能分化が進んでいる。それは癌治療においても同様。癌の診断、手術、化学療法、さらには在宅医療のそれぞれが、異なる施設で行われる時代が迫っている。
特に在宅医療の推進に関しては、癌も例外ではない。しかし、実際には、疼痛管理・治療を伴う癌の在宅医療については、緊急時の受け入れ機関の確保など地域連携の遅れもあって、進展の歩みは遅い。そこで今年度、その体制作りに向けたモデル事業が全国4カ所で始まった。
その一つが千葉県の柏、我孫子、流山の3市にまたがる東葛地域。「癌になっても安心して暮らせるまちづくり」がキャッチフレーズ。
同事業に対する地元薬剤師の関心も高い。既に、国立がんセンター東病院(柏市)が中心となって進めてきた“地域の症例検討会”を拡充。リンクスタッフといわれる関係職種の「指導的スタッフ」が意見交換を始めている。実は40人程度のリンクスタッフのうち半数近くは訪問看護師だが、「薬剤師が“意外”に多く参加している」と、事務局サイドは、薬剤師の積極性や意欲を評価している。
同地域以外にも浜松市、長崎市、鶴岡市の3地区が指定されている。東葛地域も含め、多少は地域医療に対して「腕に覚えのある地域」ではあろうが、ともかく薬剤師がそこに参画し、熱意と専門性を認知・理解してもらうことが肝要だ。
幸い、今春からは在宅医療の推進に向け、「退院時共同指導料」「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」「在宅患者緊急時等共同指導料」などが新設された。薬局・薬剤師に対する一つの期待の表れだ。
今回、特定の地域だが、モデル事業という形で、新たに“チーム”の青写真が描かれようとしている。このような絶好のチャンスを逃す手はない。物おじせず、飛び込んでいくことが肝心だ。