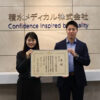「医師の指示による分割調剤」の実施率は極端に低く、ほとんど活用されていないものの、有用性を示すエビデンスをいくつか目にするようになってきた。将来のリフィル処方導入へとつなげるためにも、分割調剤の活用や必要な体制作りを各地で推進し、医師の支持を得られるような厚みのあるエビデンスを構築する必要がある。
岡山県薬剤師会が有用性を報告している。昨年度に厚生労働省予算で実施した事業において、10人の患者に分割調剤を行った。薬剤師が対象患者を選定し、処方医の承諾と指示を得た上で、実施に踏み切った。分割調剤時には患者宅を訪問して患者の状況を把握。得た情報をもとに、必要に応じて処方変更を提案した。
その結果、10人中6人で服薬アドヒアランスが改善、3人で多剤併用(ポリファーマシー)が改善され、2人で副作用を発見できた。今年度は規模を拡大し、50人を目標に同様の検証事業を推進している。
京都大学病院でも薬剤部が中心になって、分割調剤の有用性の検証に取り組んでいる。モデルとしたのは関節リウマチ治療と乳腺術後ホルモン治療である。医師にメリットを実感してもらうためには診療に役立つ情報を薬局薬剤師から医師にフィードバックしてもらうことが重要と考え、各治療用のトレーシングレポートや経過観察表を作成して取り組みを進めた。
昨年10月から今年3月まで10人の関節リウマチ患者に分割調剤を実施した結果、症状の変化や副作用の早期発見、アドヒアランス維持など7人の患者で良好な成果を確認したという。
長期処方患者では、医師の診察間隔が長くなるため、副作用の発見が遅れたり、不適切な服薬が放置されるなどして、患者に不利益が生じる可能性がある。分割調剤によって薬局薬剤師が患者との接点を持つことで、これらの穴をカバーできる。
分割調剤とその先にあるリフィル処方の推進は、医薬品医療機器等法の改正で薬剤師に求められる「服薬中の継続的な薬学管理」を実践する上で有用な手段になり得る。
医師のタスクシェアリング推進という医療の時流にも合致する。医師の負担を軽減し、働き方改革を促す手段として位置づけることが可能だ。実現に向け、追い風を受けやすい環境が整っている。
前々回と前回の診療報酬改定で、医師の指示により分割調剤を実施できるようにルールが整備されたが、実施率は0.04%と著しく低い。医師側の理解が十分ではない上、得られる調剤報酬が少ないため薬局薬剤師側の意欲も低いように思える。
しかし、ここで足踏みをしていては前に進まない。リフィル処方の導入を目指すのであれば、まず分割調剤でエビデンスを積み上げなければならない。各地でのさらなる実践と検証が必要だ。