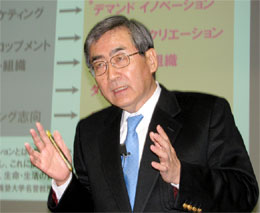
内藤社長
エーザイの内藤晴夫社長は26日、都内で開いた記者懇談会で、7月1日から研究開発体制を刷新し、R&Dから「プロダクト・クリエーション」への転換を図る方針を明らかにした。現在、新体制の設計を進めており、人材を重視したプロダクト・クリエーション活動によって、患者志向をさらに明確化する。また、製造販売の領域では、製品・情報・サービスをパッケージ化して提供する「デマンド・イノベーション」の創出を目指し、新たなビジネスモデル「E‐ファーマモデル」を追求していく考えを強調した。
プロダクト・クリエーション(研究開発)の新体制は、創薬から承認申請までの責任を負う「プロダクト・クリエーション・ユニット(PCU)」、技術・薬制などの機能を担当する「コア・ファンクション・ユニット(CFU)、戦略やマネジメントを手がける「CEOオフィス」の三つの要素で構成し、疾患・技術領域別の専任組織に転換する。
具体的には、PCUは神経科学、癌、抗体、フロンティア(免疫)など6ユニットで構成。CFUは原薬製造、代謝・安全性、バイオマーカー・ファーマコオミクスなど6ユニットからなる。これらユニット間の連携、調整をCEOオフィスが支援していく。
内藤氏は「これまで様々なビジネスモデルが模索されてきたが、規模が大きければ革新的新薬が創出できるという仮説には懐疑的だ」と指摘。「むしろ有能な人材がどういうモチベーションで新薬を創出していくかが重要」との姿勢を示し、プロダクト・クリエーションの新体制に移行する意義を強調した。
一方、地域戦略について、内藤氏は「一つのグローバル戦略では成長は望めない」と指摘。特に欧州事業では、英国・ロンドン北部に「欧州ナレッジセンター」を新設し、探索研究から生産、マーケティング、欧州統括機能からなるバリューチェーンを集約させる、新たなビジネスモデルへの転換を目指す考えを明らかにした。既存の欧州各国の販社は、薬価・保険償還の取得に特化させる。さらにEU新加盟国、中東欧に対しては、専任統括体制を敷くことで、ビジネスの大幅な拡大を狙う。
その上で、デマンド・イノベーション、プロダクト・クリエーション、人材とバリューチェーン重視による新たなE‐ファーマモデルを追求していく方向性を示した。今後、研究開発費をプロダクト・クリエーション投資、売上原価・販管費をデマンド・イノベーション関連費、営業利益を再投資への原資と位置づけ、事業構造を転換することでさらなる生産性の向上を図る方針だ。





















