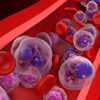日本医師会は、病院と診療所の医師を対象に行った、医薬品の処方期間に関する調査結果を公表した。病状が安定していて、定期的に通院している慢性疾患患者への処方日数が長期化していることに伴い、長期処方期間中に患者の容態が悪化した事例が報告されており、高血圧管理中に腎障害を発症した問題事例なども寄せられたという。日医は、「長期処方によって疾病の重症化に気づくのが遅れるおそれがある」とし、中央社会保険医療協議会などで、改めて処方期間のあり方を検討するよう求める考えを示した。
調査は、慢性疾患患者に対する長期処方の実態を把握するため、北海道、茨城、群馬、千葉、広島、福岡の6道県の99病院に勤務する医師2820人と、日医会員から無作為に抽出した診療所1389施設の医師1395人(計4215人)を対象に、9月30日から11月5日にかけて実施した。
慢性疾患患者に対する処方期間では、「5週間以上」が52・9%と最も多かった。患者全体で見ても、「5週間以上」としたのは27・3%を占め、「処方期間が長期化している」と分析した。
長期処方の対象となる疾患と薬剤としては、3割以上が高脂血症のHMG‐CoA還元酵素阻害剤、高血圧のジヒドロピリジン系Ca拮抗剤が挙げられた。この二つの薬剤については、医師の半数近くが8週間以上の処方が多いと答えた。
5週間以上処方している理由として最も多かったのは、勤務医の「病状が安定しているから」(約8割)に対し、診療所は「患者からの要望」(約6割)だった。
ただ、5週間以上の長期処方では、約2割の医師が、患者の容態の変化に気づくのが遅れたことがあると回答。長期処方中に容態が変化しても、次の診療時まで我慢してしまったり、別の病気を発症しても、長期処方された薬を服用するなどの問題事例も報告された。
日医は、「長期処方は患者からの要望も多いが、安全は最優先させなければならない」とし、医師の責務として、適切な処方期間の確保に自ら努める一方で、中医協での検証を求めた。