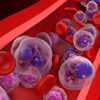今年度の補正予算が成立し、「成長による富の創出」の一環としてiPS細胞などを用いた再生医療研究の加速などに240億円が計上された。
安倍首相は、既にiPS細胞関連の研究を「経済再生の一丁目一番地」と位置づけ、10年間で約1100億円の研究支援を表明している。
世界に冠たるiPS細胞技術を活用した経済成長戦略は的を得たものであると考えられるが、その焦点があまりにも“再生医療”に向けられすぎているのが大きな気がかりだ。
もちろん、iPS細胞による再生医療の研究は重要だ。だが、それに加えてiPS細胞の創薬への応用にも、もっと目を向けるべきである。iPS細胞を樹立した山中伸弥京都大学教授自身も「これから力を入れるiPS細胞研究の応用分野は、再生医療よりも創薬の方がはるかに大きい」とコメントしている。
iPS細胞の可能性が再生医療よりも創薬の方が高いことは昨夏、発表された「疾患は細胞の中にあり」をテーマとした米国の学術論文の中にもはっきりとうたわれている。欧米では、再生医療よりも創薬に対してiPS細胞の可能性を見出そうとしているのは間違いない。
iPS細胞の創薬への応用としては、どのような手立てが考えられるのか。その一つに、患者の細胞からiPS細胞を作製し、疾患を表現している細胞を選択して増殖させることで疾患のメカニズムを解明する手法がある。
わが国でも先日、長崎大学と京大iPS細胞研究所などの研究チームが、患者の細胞から作ったiPS細胞を用いて、アルツハイマー病の新たな発症メカニズムを確認したことを発表している。
この研究は、アルツハイマー病の患者の皮膚細胞からiPS細胞を作り、試験管に大脳の神経細胞の状況を再現して解析するというもので、その成果からはアミロイドの蓄積状態による予後予測や、病態に応じた投薬の可能性が期待されている。
また、同研究所では、CINCA(慢性乳児神経皮膚関節)症候群の患者からiPS細胞を作り、病態を再現する研究に取り組んでいる。
患者の皮膚細胞から、遺伝子変異の存在するiPS細胞と、存在しないiPS細胞を作製し、疾患発症にNLRP3遺伝子の変異細胞が深く関わっていることを見出した。
CINCA症候群の発症メカニズムは痛風やアルツハイマー病などと共通しているため、新たな治療法開発に結びつく可能性が注目されている。
iPS細胞は、研究開発の早期段階でのヒトでの効果予測や、肝細胞、腎細胞、心細胞、神経細胞のiPS細胞化によるヒト特有の毒性チェックなどにも活用されており、新薬開発の効率化には不可欠な存在となっている。
わが国においても、関連府省や薬業界、学会が一丸となって、国のプロジェクトとしてiPS細胞を活用した創薬研究が推進できる体制の構築を望みたい。