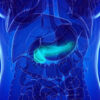薬価制度の見直し論議が大詰めを迎えた。厚生労働省が見直し方針として中央社会保険医療協議会に提示した「薬価制度改革の骨子(たたき台)」に、優れた新薬に対する薬価の加算率の大幅な引き上げなどがあったとはいえ、業界側が劣勢に見える。
製薬業界がかねてから反対していた市場拡大再算定が、さらに対象を拡大する案が盛り込まれたからだけではなく、業界が覚悟して提案したはずの新制度案の実現に向けた議論が見えなかったからである。一連の論議に対する業界の戦術は正しかったのかと問いたい。
今回の医療費改定論議の環境は、薬価制度の面から見ると、政府の経済成長力強化策の一つに位置づけられる「革新的医薬品・医療機器創出5カ年戦略」に基づくイノベーションの評価という追い風と、2011年度までの歳出改革の一環の社会保障関連予算2200億円削減という逆風の二つの力が引っ張り合う中にあった。
ということは、歳出改革に応えつつも、特許期間中の新薬薬価の維持などからなる新制度案を、中長期的にどのように導入していくかの道筋をつけることが、業界側の課題であった。業界側も認識しており、本紙は、その課題に取り組むには、相手と情勢を見極めて柔軟な戦術が必要だと主張していた。
歳出改革では、後発医薬品の使用促進策は業界が必要性を認め、政府の後押し、反対していた日本医師会の柔軟な対応などもあって前進を見た。新制度案では、長期収載品の後発医薬品への置き換えを促すことを想定しており、その素地はできたといえよう。
問題は、加算率の引き上げなどの来年度に向けた提案と、中長期的に導入を求める新制度の提案のつながりが不明確だったことだ。課題は、来年度だけでなく、中長期的にイノベーションの追い風にどう乗るかである。
来年度改革が大切なのは分かるが、中長期的にどう改革を実現していくのか、ここが戦術の駆使のしどころだったと考える。例えば、調整幅を議題に載せる必要があったのではないかということだ。
業界側には十分に問題意識があった。新制度案の下地となった日本製薬工業協会医薬産業政策研究所の研究報告には、「流通慣行を踏まえた上で、合理的と認められる乖離幅を設定し、その範囲内で市場価格が形成されている品目については、定期的な薬価改定の対象外とする」とある。この中の乖離幅は調整幅の議論にも結びつけられる。
日本製薬団体連合会保険薬価研究委員会の研究報告では、調整幅を一律に適用すべきではないとし、希少疾病用医薬品など銘柄の特性を踏まえ設定することを提案している。
厚生労働省幹部も議論の必要性を指摘していた。また同省は、中医協に「原価計算方式で算定された類似薬がない新薬が改定により2 03%引き下げられている」との資料を提出しており、薬価研に似た問題意識がうかがえる。
これら議論を深めることは、将来に道筋をつける戦術になり得たと考える。希少疾病用医薬品は別途調整幅を設けるといった検討もあってよかったのではないか。中医協で調整幅の議論がなかったことは残念に思う。
新制度案は、たたき台で「平成20年度薬価制度改革以降」の検討課題にはなったが、いつまでに結論を出すという書きぶりにならなかったことも不安材料と言えよう。