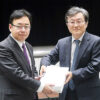厚生労働省が公表した2018年度「医薬品販売制度実態把握調査」(覆面調査)の結果、エフェドリン、コデインなどを含む「乱用の恐れがある医薬品」の販売ルールを遵守していない店舗が増えている実態が明らかになった。
調査結果によると、店舗で乱用の恐れのある医薬品を複数購入しようとした際に、「質問等されずに購入できた」との回答が48.0%と、前年調査の38.8%から9.2ポイント上昇し、不適切に販売していた店舗が増えていた。
乱用の恐れのある医薬品の販売に注目が集まるのには理由がある。昨年8月に開かれた厚労省の「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」で、「オメプラゾール」「ランソプラゾール」「ラベプラゾール」のプロトンポンプ阻害剤(PPI)3成分のスイッチ化が見送られた大きな要因の一つになったからだ。
評価会議では、薬局などの店舗で乱用の恐れがある医薬品を「質問なしに複数購入できた」ケースが4割近くに上った覆面調査の結果が複数の委員から問題視され、結果的にスイッチ化は「否」と判断されてしまった。
数ある調査項目のうち、最も象徴的なものの遵守率が10ポイント近く下がるという事態は、新たなスイッチOTC薬の登場への障壁になってしまいかねない。
ましてや、若者を中心に咳止め薬やかぜ薬などの市販薬の乱用が問題になっている時期でもあり、覆面調査の結果は非常にタイミングが悪いと言わざるを得ない。
スイッチOTC化に慎重な勢力に対しては、塩を送ってしまったようなものだ。厚労省関係者も「この結果は悩ましい」と頭を抱える。
昨年の評価会議では、販売ルールの遵守状況が改善された時点で、再びPPIを議論の俎上に載せるよう求める意見が出ていたが、今回の調査結果を見ても、その機会はほとんど失われたと言っていいだろう。
薬剤師・薬局は、改めてPPIに限らず、スイッチOTC化の障壁が製品そのものの安全性の問題ではなく、販売体制の不十分さになっていることを重く受け止めるべきである。
薬局やドラッグストアは、適正に販売できる体制を真剣に考えなければならないが、製造販売業者として講じることができる対策もあるはずだ。OTC薬の関連団体もスイッチOTC化を進めたいのであれば、薬剤師や登録販売者ばかりに任せるのではなく、外箱で大きく注意喚起するなど、乱用防止の工夫を施してもいい。販売ルールの遵守率向上に向け、売る側と作る側がお互いに知恵を出し合うことも必要だ。