保科清(山王病院小児科部長)
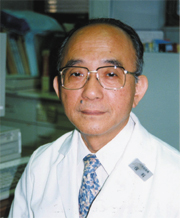
平成16年までは、小児科医になろうとする医師が全国で450名前後はいました。その年の4月から導入された新医師研修制度で、2年間は小児科を直接専攻することはできなくなり、内科、外科を1年目で研修することになりました。その結果、平成18年度に小児科を志望する医師が300名に達せず、約3分の2以下に減少することになりました。
小児科希望者が減少した原因はいろいろあるでしょうが、このように減少した小児科医で、どうやってこれからの子ども達を健全に成長させるかが問題です。
少子化で患者さんの数が減ることにより、小児科になっても患者がいなければと考えたわけではないでしょう。
厚生労働省は、日本における医師の数は今後10年で過剰になると推計していますし、小児科医の数も実際に増えていると報告しています。数年前までは、確かに少しずつですが小児科医は増えていたようです。しかし、現場では小児科医が足りません。この違いはどこにあるのでしょうか。
厚生労働省は、2年に1度の医師の自己申告による調査を行っていますが、それによると数値的には増加しています。そして、小児科を希望する若い医師に、女性医師が増えています。女性医師が30歳頃から結婚、出産、育児の時期となり、フルに働けなくなります。その間、少しずつでも働いていれば復帰は簡単なのですが。休んでいても自分は小児科志望なので、厚生労働省の調査には小児科に○をつけますから、小児科医は増えているとみなされます。
病院で当直すると、時間外救急患者の3分の2は小児科と言うことも珍しくありません。ほとんど眠れない状態が続いて、次の日も外来と入院患者の診療で1日働くことになります。そのような当直を月に5,6回やったら、かなり疲弊しますが、子どものためにと思って頑張っているのが小児科医です。いくらがんばっても病院内における小児科の収入が低いので、病院からは「小児科は不採算部門」という発言になり、結果として小児科を縮小ないし閉鎖した病院が増えています。
入院するような子どもの病気も少なくなっています。それは、小児科医が子どもを病気にかからせないように予防接種などの保健活動に力を入れているからです。入院するような子どもの病気を少なくしたために、結果として病院では小児科が赤字になりました。
元気な子どもの成長を願って働けば働くほど赤字になる小児科。ただ、子どもが好きだからといっても、小児科を選択する医師はいなくなるのではと心配しています。















