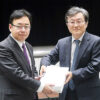今月1日から一般用医薬品の販売方法等を規定した改正薬事法が全面施行された。この数カ月、医薬品ネット販売規制の是非をめぐる議論などに振り回された格好で、最終的な省令公布が5月末になるなど、施行直前までドタバタ感があったことは否めない。一方で、約半世紀ぶりの医薬品販売制度の改正ということもあり、この1週間、テレビや新聞などの一般マスコミも、この法改正を大きく取り上げる報道が目立った。
ただ、一方で、耳に入ってくるトーンは、「薬剤師がいなくとも、医薬品販売が可能になりました」「24時間営業のコンビニでも薬を購入できるようになりました」「インターネット等での医薬品販売が規制されます」など、改正後の医薬品販売の変化のみをクローズアップする報道が多かったように感じる。
この1週間、ドラッグストアなどの店頭を見て歩いた。薬剤師しか販売できない第1類医薬品については、多くの店舗が空箱陳列を行い、購入者は、空箱を薬剤師のいる相談カウンターに持ち運び、文書による情報提供を受けた上で、製品と交換するというパターンで、基本的に法律に則りつつも、従来のセルフ形式は残すという販売手法をとる店舗が大半だった。施行通知の解釈に沿ったものとはいえ、何か機械的な販売方法には釈然としないものを覚える。
一方、異業種の医薬品販売参入も始まった。コンビニエンスストア、スーパーなどの流通業態をはじめ、家電量販店までが一般用医薬品販売を本格化させる動きを見せている。
こうした中で、武田薬品は改正薬事法に合わせて、1日からコンビニなどの新規チャネルにも対応。必要な分だけ購入できる形で小容量のかぜ薬など10品目を発売。「社会的ニーズに対応した」(同社)という。こうした医薬品メーカーの素早い対応にも法改正の影響を感じさせる。
異業種参入の背景には、改正法に伴う新たな医薬品販売専門家の登録販売者の存在がある。薬剤師に比べ低コストで雇用できる。しかも一般用医薬品の9割を占める第2類医薬品、第3類医薬品が販売できることから、消費が低迷する中、カンフル剤としての医薬品販売参入を目論む異業種にとって、登録販売者は、格好の条件が整ったように映るのかもしれない。
昨年度は約5万8000人が登録販売者試験に合格、さらに今後も毎年試験が実施されることで、登録販売者はさらに増加が見込まれ、医薬品販売への参入がしやすい環境になる。
様々な不協和音が未だ残る中で、スタートを切った改正薬事法。やはり、一貫して抑えておかなければならないのは、改正法の本来の趣旨であろう。
今後の医療保険制度を下支えする意味でも、必要なセルフメディケーションに向け、医薬品を安全に適正使用するために必要な情報や、相談を受けることができる国民の権利が、法制化されたことになるはずだ。こうした側面こそ、幅広く国民に周知されるべきなのだろう。