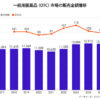2020年度診療報酬改定に向けた議論が佳境に入ってきた。調剤報酬については、「累次にわたる改定で見直す」との方針が掲げられていることもあり、18年度改定よりも議論する回数が上回る見通しである。
厚生労働省は、既に医療現場で導入されている取り組みを評価するための提案を中央社会保険医療協議会で行っているが、医薬品の有効・安全、かつ効率的な使用に貢献することが期待されているフォーミュラリーや、疑義照会などにおいて薬局から医療機関への問い合わせを簡素化する取り組みに対しては、慎重論が相次いでいる。
フォーミュラリーについては、取り組みを進める意義に理解は示されたものの、使用する薬剤が絞られることを懸念する声が上がったり、「診療報酬で誘導していくというのは違う」などと、診療報酬上の評価に慎重な意見が相次いだ。
医療者の負担軽減や患者の待ち時間短縮につながると期待される薬局から医療機関への問い合わせを簡素化する取り組みに対しても、一定の理解は得られつつも、療養担当規則で定められている「特定の薬局への誘導禁止に抵触する可能性がある」といった理由で診療報酬上の評価に否定的な意見が出た。
「総論賛成・各論反対」のような議論を聞いていると、より良い医療の提供という同じ一つの方向に進んでほしいと感じることはあるが、取り組みに対する評価がことごとく反対された要因の一つに、専門学会や職能団体、行政などによって、ある程度のルール化がなされていなかったということはないだろうか。
12年度診療報酬改定で「病棟薬剤業務実施加算」の新設につながった10年の医政局長通知や政府の「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」を受け、抗菌薬の適正使用の観点からAMR対策を進めるため、感染防止対策加算で抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の取り組みを評価する「抗菌薬適正使用支援加算」の新設につながった例を挙げるのが適切かという議論はあるが、ガイドラインや通知のような一定のルールや施策が存在した上で、それぞれの現場に即した形で進められている状況で動いていたのであれば、もう少し違った議論が展開されていたかもしれない。
医薬分業に対する風当たりが強いことも相まって、たとえ医療現場で役立つ取り組みであっても、診療報酬の点数を付ける、付けないといったシビアな議論をする場では、専門学会や職能団体、行政などによってある程度取り組みを明確化することも大事だという印象を受けた。
議論を有利に進める上でも、現場での取り組みに対するエビデンスの集積とある程度のルール化をワンセットで行っておくことも必要なのではないだろうか。