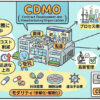改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムが決定し、今年度から関係各方面への周知が始まっている。2024年度から入学する学生に対しては、臨床薬学を重視した教育体制が柱となる。
改めて改訂コアカリの基本方針を整理すると、▽大きく変貌する社会で活躍できる薬剤師を想定した教育内容▽生涯にわたって目標とする「薬剤師として求められる基本的な資質・能力」を提示した新たなモデル・コア・カリキュラムの展開▽各大学の責任あるカリキュラム運用のための自由度の向上▽臨床薬学という教育体制の構築▽課題の発見と解決を科学的に探究する人材育成の視点▽医学・歯学教育のモデル・コア・カリキュラムとの一部共通化――となっている。
こうした中、24年度予定の順天堂大学薬学部薬学科、国際医療福祉大学成田薬学部薬学科の開設が文部科学大臣に諮問されたほか、収容定員の増加を東邦大学薬学部薬学科、神戸薬科大学薬学部薬学科が申請した。改訂コアカリのスタートと定員抑制方針の期限に向け、各薬系大学の動きが活発化してきている印象だ。
改訂コアカリでは、大学のカリキュラムの自由度が高められたことから、各大学で独自色を出そうと様々な取り組みが検討されている。既に公表されているものも多いが、データサイエンスを重視した科目や研究の取り込みなどが目立つ。
それでも7割程度を占める共通の「コア」の部分は決められており、大学関係者からは「理想を詰め込んだ」との率直な声も聞かれる。これからスタートする改訂コアカリではあるが、同じ感想を多くの教員から聞いた。
カリキュラムの過密を指摘する声も国公立大学、私立大学を問わず少なくない。改訂コアカリでも「これからの薬剤師の養成に当たっては、自ら考える力やリーダーシップを身に付ける必要があり、カリキュラムの過密化は必ずしも望ましい状態ではない」と付言しているが、なかなか現実は難しいようだ。
共通して取り組むべきコアの部分は「疾病の予防や個々の患者の状況に適した責任ある薬物療法を実践できる薬剤師の養成」を目指し、国家試験に合格するために必要な科目ばかりだが、「学生が疲弊している」(大学教授)現実もあるという。
カリキュラムの自由度が高まり、大学の個性を生かせるようになると言っても、希望を持って入学してくる学生が疲弊してしまっては元も子もない。薬学教育の理想と現実の間で板挟みになるのは学生であり、過密なカリキュラムの中であっても学生生活を充実できるようなサポートも重要になるだろう。
改訂コアカリは時代の要請であることは間違いない。授業で疲弊しないよう学生のケアも丁寧に行っていくことで、より良いものに昇華させていってほしい。