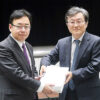厚生労働省と経済産業省主催のSaMD産学官連携サブフォーラムが10日ハイブリッド開催され、第1部ではAIを利用したSaMDの薬事規制のあり方について講演・討論が行われ、第2部ではDASH for SaMD2の進捗報告・討論が行われた。
フォーラムは、政府が進める「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」(DASH for SaMD)に基づき、SaMD(サムディ:プログラム医療機器)の早期実用化の課題とその解決に向けて産学官が意見交換を行うもので、2022年2月から始まった。これまでに本フォーラムが4回、サブフォーラムが2回開催されており、今回は3回目のサブフォーラムとなる。今回の参加者は現地参加が120人、ウェブ参加が1500人。
開会に先立って、当初からフォーラムに関わってきた参議院議員の自見英子内閣府特命担当大臣が挨拶に立ち、「プログラム医療機器が医療機器の本体になるような世界観を描いていきたいということで」フォーラムが始まった。「(SaMDを)とにかく成長産業に押し上げていきたい」などと述べた。
第1部:AIを利用したSaMDの薬事規制のあり方
第1部の演者は、[1]厚生労働省医薬局医療機器審査管理課プログラム医療機器審査管理室室長の水谷玲子氏、[2]医薬品医療機器総合機構(PMDA)プログラム医療機器審査部審査役の小池和央氏、[3]元米国FDA(食品医薬品局)で現グーグル社所属のバクル・パテル氏、[4]国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野長の浜本隆二氏、[5]米国医療機器・IVD工業会・GEヘルスケアジャパン株式会社政策推進部長の大竹正規氏。総合討論は以上の演者に加え、東京農工大学大学院工学研究院教授の清水昭伸氏、公益財団法人医療機器センター専務理事の中野壮陛氏が参加して行われた。
水谷氏は主に、プログラムの医療機器該当性について説明し、迷ったら厚労省医薬局の監視指導・麻薬対策課に相談してほしいと述べた。
小池氏は、「AIを使った治療機器の審査の考え方」は、PMDAがまとめた文書「病変検出用内視鏡画像診断支援プログラムの審査ポイント」(2023年3月7日)と「プログラム医療機器の薬事開発・承認申請に関する手引き(よくある質問集)」(2024年10月21日)の中にあるとし、その考え方について、「入力の変化に出力が大きく変わりうるのがAIであり、似たようなインプットがあった場合に異なる結果が得られるという場合もある。そのため承認審査の考え方としては、入力に対して適切な出力が得られているかを確認することに重きを置いて審査している」と説明した。一方、「(承認審査で)難しいのが汎用AI」で、「現時点で疾病の診断や治療に寄与する目的で提供されている生成AIはないが、そういう常に性能が変化していくようなものを医療機器として承認するには何を評価すればいいのかというのはPMDAのみならず開発者の先生方も悩んでいる」と述べた。
パテル氏は、GMLP(Good Machine Learning Practice)やPCCP(Predetermined Change Control Plan:市販後の変更を認める変更管理計画)などソフトウェアやAIテクノロジーに対するFDAのこれまでの取組について述べた後、生成AIの規制については「体系的に監督する」(systematically oversee)仕組みにしたらどうかと提案した。つまり、「生成AIベースの臨床アプリケーションは、機器としてではなく、新しいタイプの臨床インテリジェンスとして扱う」こと。
浜本氏は、医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン(令和6年9月30日厚生労働省事務連絡)を紹介。
大竹氏は、AI医療機器の使用に当たっては企業側と医療従事者の責任分界を明確しなければならないと述べた。また、「自動学習」を医療に導入できるかどうかの検討ではなく、「医療に導入するための検討」をしてもらいたいと要望した。
第2部:DASH for SaMD2の進捗
第2部の演者は、[1]厚生労働省医薬局医療機器審査管理課課長の高江慎一氏、[2]経済産業省商務・サービスグループ医療・福祉機器産業室室長の渡辺信彦氏、[3]日本医療機器産業連合会プログラム医療機器規制対応SWG主査の田中志穂氏。総合討論は以上の演者に加え、AI医療機器協議会会長・株式会社AIメディカルサービス 代表取締役CEOの多田智裕氏、株式会社MICIN代表取締役CEO・日本医療ベンチャー協会理事の原聖吾氏、国立がん研究センター東病院副院長の伊藤雅昭氏、厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室室長の木下(きした)栄作氏、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課医療機器政策室室長の南川一夫氏、PMDAプログラム医療機器審査部部長の岡崎譲氏が参加して行われた。
高江氏は、DASH for SaMD2の4項目[1]萌芽的シーズの早期把握と審査の考え方の公表、[2]SaMDの特性を踏まえた実用化促進、[3]早期実用化のための体制強化等、[4]日本発SaMD国際展開支援における厚労省の取組について講演。このうち[1]の関係では「疾病治療用の家庭用プログラム医療機器に関する評価指標案を、次世代医療機器・再生医療籐製品評価指標作成事業の家庭用プログラム医療機器審査ワーキンググループで議論しているところ。案ができたらパブコメするのでご意見いただきたい」と述べた。また[2]の関係で、同ワーキンググループでの議論を踏まえ、「医療現場向け・家庭向けSaMDの販売方法に関する明確化のための指針を今後検討していく予定になっている」と述べた。
渡辺氏は、DASH for SaMD2における主に産業振興策について述べ、この中で「上市後の社会実装に向けた支援をするデジタル開発・導入加速事業ということで9.2億円の補正予算をいただいた。スタートアップに限定してはいるが、スタートアップ(SU)の作ったSaMDを医療機関が導入して実際の価値を評価して、製品競争力の向上を促す、そういう事業をSUを対象に実施する。2月下旬くらいに公募する予定」だと述べた。
田中氏は、SaMD版リバランス通知(令和5年11月16日医薬機審発1116第25号「プログラム医療機器の特性を踏まえた二段階承認に係る取扱いについて」)発出に至るDASH for SaMD2に対する産業界の取組などについて述べた。