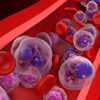順天堂大学・循環器内科学の南野徹教授らの研究グループは、高齢心不全患者における入院前の運動習慣と退院後の予後との関連性を明らかにした。高齢心不全患者の約半数が入院前に運動習慣を有さず、入院前に運動習慣を有さない患者は、退院後の予後が不良であることを見出した。
心不全の高齢者は再入院や死亡リスクが高く、適切な管理が求められる。これまでの研究では、心不全診断後の運動療法の有効性が示されているが、入院前の運動習慣が退院後の予後に与える影響については十分に解明されていない。今回、研究グループは、高齢心不全患者における入院前の運動習慣と退院後の予後の関連を検討した。
研究では、2016~18年にかけて、国内15施設において急性非代償性心不全で入院し、独歩退院が可能となった65歳以上の心不全患者を前向きに登録した多施設コホート研究「FRAGILE-HF」のデータを用いて統計解析した。
解析対象は、FRAGILE-HFに登録された1262人の患者(中央値年齢81歳、男性56.9%)で、入院前の運動習慣の有無を簡易的なアンケートで評価した。具体的には、ウォーキング以上の強度の運動を週1回以上実施した患者を「運動習慣あり群」、それ未満を「運動習慣なし群」として分類した。
その結果、46.5%(n=587)の患者は入院前に運動習慣がなく、53.5%(n=675)の患者は何らかの運動習慣があった。また、運動習慣がない患者は、ある患者に比べて6分間歩行距離、握力、四肢骨格筋指数(ASMI)、歩行速度、SPPB(Short Physical Performance Battery)スコアおよび5回椅子立ち上がり試験などの身体機能が低いことが確認された。
また、単変量および多変量のCox比例ハザードモデルによる解析でも、運動習慣が死亡リスクと有意に関連していた。
ただ今回の研究では、患者の主観的な評価に基づいて運動習慣を分類しており、活動量や歩数といった客観的な指標による評価は行われていない。研究グループは今後、「加速度計や歩数計などの客観的なデータを活用し、より具体的な運動習慣の実態を把握すると共に、予後との関連性をより精緻に求められる。また、運動習慣の評価を精度向上させることで、心不全患者のリスク層別化や、適切な運動介入プログラムの開発にもつなげていきたい」としている。