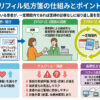Photo Credit: Adobe Stock
米食品医薬品局(FDA)は、4月11日、切除不能または転移性の肝細胞がん(HCC)の成人患者に対する1次治療として、分子標的薬のオプジーボ(一般名ニボルマブ)とヤーボイ(一般名イピリムマブ)の併用療法を承認した。
オプジーボとヤーボイの併用療法(CheckMate-9DW試験)は、2020年にFDAから迅速承認を取得しており、ソラフェニブによる治療歴のある進行HCC患者に対する2次治療として確立されているが、今回のFDAの承認によって現行の適応が完全承認に変更され、適応が1次治療にも拡大された。
今回の承認は、切除不能または転移性のHCCを有する成人参加者668人を対象としたCheckMate-9DW試験の結果に基づいている。対象者は、組織学的にHCCが確認され、Child Pugh分類がAクラス、がん患者の身体機能評価であるECOG Performance Statusが「0(全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える)」または「1(肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は
行うことができる)」で、進行がんに対する全身療法歴のない患者だった。対象者は、オプジーボ1mg/kgとヤーボイ3mg/kgを3週間ごとに最大4回まで点滴静注した後、オプジーボ480mgを4週間ごとに点滴静注する群(併用療法群、335人)と、レンバチニブまたはソラフェニブ(治験責任医師が選択)を投与する群(対照群、333人)にランダムに割り付けられた。対照群の85%はレンバチニブ、15%はソラフェニブを投与された。
その結果、主要評価項目である全生存期間(OS)の中央値は、併用療法群で23.7カ月(95%信頼区間〔CI〕18.8~29.4)だったのに対し、対照群では20.6カ月(同17.5~22.5)であり、併用療法群では死亡リスクが21%低下することが示された(ハザード比0.79、95%CI 0.65~0.96、P<0.0180)。また、3年時点での全生存率は、併用療法群で38%、対照群では24%だった。
全奏効率(ORR)は、併用療法群で36.1%(95%CI 31~41.5%)であったのに対し、対照群では13.2%(同9.8~17.3%、P<0.0001)であり、両群間には統計学的に有意な差が認められた。さらに、併用療法群では奏効期間の中央値は30.4カ月であり、対照群での12.9カ月と比較して、より長期にわたる治療反応が得られることも示された。新たな安全性シグナルは確認されなかった。
CheckMate-9DW試験の治験責任医師である米メドスター・ジョージタウン大学病院のAiwu Ruth He氏は、「肝がんの発生率は、過去40年間で3倍に増加しているにもかかわらず、HCC患者の予後は依然として不良であることを考えると、今回の承認は患者にとって大きな前進である。本試験のエビデンスの信頼性、特に対照群の選択条件と治療成果が強力であることを考慮すると、オプジーボとヤーボイによる併用療法は、切除不能または転移性のHCC患者に対する1次治療の標準治療となる可能性があると考える」と、Bristol Myers Squibb社のリリースで述べた。
なお、オプジーボとヤーボイの併用療法の正式承認は Bristol Myers Squibb社に付与された。(HealthDay News 2025年4月15日)
More Information
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-nivolumab-ipilimumab-unresectable-or-metastatic-hepatocellular-carcinoma