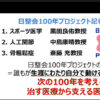目次
1.HTAとは何か
医療技術評価(HTA)の定義と目的
医療技術評価(HTA:Health Technology Assessment)とは、新薬や医療機器などの医療技術について、その有効性・安全性に加え、社会的・経済的な側面から総合的に評価する手法および研究領域です。簡単に言えば、ある医療技術が「医学的に効果があるか」だけでなく「そのコストに見合う価値があるか」を評価することを目的としています。HTAの目的は、限られた医療資源の中で効果的かつ効率的な医療サービスを提供し、医療システム全体の効率や持続可能性を向上させることにあります。そのために、治療によって得られる健康上の効果(アウトカム)や費用、社会への影響など、あらゆる観点から医療技術の価値を検証します。例えば新薬を導入する場合、その薬剤の価格と効果(延命効果やQALY増加など)を、従来治療の費用・効果と比較し、追加費用に見合う効果が得られるかどうかを判断します。この総合的・体系的な評価プロセスを通じて、エビデンスに基づいた医療政策の意思決定を支援することがHTAの役割です。
医療技術評価の重要性
医療技術評価が注目される背景には、医療の高度化や高額な新技術の登場に伴い、医療保険財政への負担増大が深刻化している現状があります。効果が高い医薬品や医療機器でも、医薬品の価格(薬価)や投入リソースが過大であれば、医療経済的に見合わない可能性があります。HTAはこうした課題に対し、経済的観点から医療技術を評価し、医療費の適正化と優先度の高い技術への資源配分を可能にします。
特に日本では急速な高齢化や慢性疾患の増加により、医療費の伸びが社会問題となっています。例えば、糖尿病ひとつとっても、厚生労働省の推計では2016年時点で糖尿病患者および予備群は約2000万人に上り、20~64歳の10人に1人が該当するとされています。糖尿病のように長期の治療とケアが必要な疾患では、医療の質(医学的効果)を維持しつつ、経済的な負担をどう抑えるかが重要です。こうした慢性疾患治療の効率化や患者の負担軽減という観点からも、HTAの重要性は年々高まっています。実際、HTAは患者中心の医療を支える制度の一つと位置付けられており(後述)、医療の質と持続可能性を両立するために必要不可欠といえます。
日本におけるHTAの歴史と制度的背景
日本においてHTA(とりわけ費用対効果評価)が本格的に議論され始めたのは比較的最近です。背景には、免疫チェックポイント阻害薬やCAR-T細胞療法など革新的で高額な治療法の登場により、国民皆保険制度を将来にわたり維持できるのか懸念が生じたことがあります。医療費増大への危機感から、2012年頃より中央社会保険医療協議会(中医協)で費用対効果評価制度(HTA)の導入が検討され始めました。その後、2016年から一部の医薬品を対象に試行的導入(パイロット試行)が行われ、制度の検討とデータ蓄積が進められます。その結果を踏まえ、2019年4月から厚生労働省によりHTAの枠組みが正式に制度化され、医療技術の費用対効果評価が薬価制度に組み込まれることになりました。制度導入当初の対象品目はごく限られた数に留まりましたが、その後対象は徐々に拡大しています。さらに制度の運用を支える専門組織として、2018年には国立保健医療科学院に「保健医療経済評価研究センター」(C2H:Center for Outcomes Research and Economic Evaluation for Health)が設立されました。C2Hは費用対効果評価のガイドライン作成や分析支援などの専門的業務を担い、HTA推進の中核的役割を果たしています。制度は運用開始後も改善が重ねられており、2022年には評価プロセスの見直し(例えば分析期間の短縮等)が行われるなど、今なお適宜改革・調整が進められています。総じて、日本のHTA制度は歴史が浅く認知度も高くありませんが、持続可能な医療制度の構築に向けて重要な一歩を踏み出したと言えるでしょう。
2.HTAの評価手法とプロセス
費用対効果評価の基本
HTAにおける費用対効果評価とは、新たな医療技術の費用(コスト)と効果(ベネフィット)を定量的に比較分析することです。一般に「費用対効果 (cost-effectiveness)」という言葉はコストパフォーマンスと同義に使われますが、HTAではより厳密に、新技術と既存の標準治療を比較した増分の費用と増分の効果を評価します。その代表的指標がICER(増分費用効果比)です。ICERは「1追加単位の効果(アウトカム)を得るために必要な追加費用」を示すもので、効果指標としてはしばしばQALY(質調整生存年)が用いられます。QALYは患者の生存年数に健康の質(QOL:生活の質)を掛け合わせた指標で、治療による寿命延長効果と生活の質の改善効果を統合したものです。
例えば、ある新薬Aを用いた場合のQALYと従来薬Bの場合のQALY差(△QALY)、およびそれらのコスト差(△費用)からICER=△費用/△QALYを算出します。ICERの値が小さいほど費用対効果に優れていることを意味します。各国ではICERに閾値(しきい値)を設けており、それを下回る治療を「経済的に有効」と判断します。
日本では1 QALYあたり500万円(上限1000万円)が一つの目安とされており、この閾値を超える(=費用対効果が低い)場合には価格を段階的に引き下げる調整が行われます。この基準値は日本独自に設定されたもので、算定方法(一人当たりGDPや社会の支払意思額などに基づくべきとの意見)や妥当性について専門家の間で議論が続いています。一方、ICERが非常に低く費用対効果が良好な場合には価格を引き上げる仕組みも設けられており、特に新技術が既存治療より費用を削減し効果が同等以上(ドミナントと呼ばれる状況)のときは、薬価を加算できるルールもあります。このように費用対効果評価は、医療技術ごとの「効果に見合った適正な価格」を見極めるための経済的評価手法であり、医療経済学に基づく科学的根拠を政策や価格決定に反映させる重要なプロセスです。
主な評価手法の種類(CEA・CUA・CBAなど)
費用対効果評価を含む医療経済評価にはいくつかの分析手法があります。HTAで用いられる代表的な評価手法を以下に紹介します。
CEA(費用効果分析:Cost-Effectiveness Analysis)
最も基本的な手法で、医療介入ごとの費用と効果を比較します。効果は寿命延長や症状改善など自然単位の臨床アウトカムで測定し、例えば「1年寿命を延ばすのに必要な費用」を算出します。異なる治療の効率を直接比較できる点が特徴です。
CUA(費用効用分析:Cost-Utility Analysis)
効果を質調整生存年(QALY)など効用で測定する手法です。患者の生活の質を考慮したアウトカム指標を用いることで、延命効果とQOL向上効果を統合的に評価できます。事実上、現在多くの国のHTAで採用されている標準的な手法で、日本でもQALYに基づくICER評価がCUAにあたります。異なる領域の医療技術間の比較が可能になる利点があります。
CBA(費用便益分析:Cost-Benefit Analysis)
効果を金銭的価値に換算して評価する手法です。医療介入によるベネフィット(便益)を金額で表現し、費用と差し引きして純便益を算出したり、費用便益比を求めたりします。例えば「介入によって節約できた医療費や生産性向上による経済効果」を金額換算し、コストと比較します。ただし、健康や生命の価値を金銭評価することには倫理的・技術的な難しさがあり、HTAの実務ではCEA/CUAほど一般的ではありません。
以上の他にも、医療経済評価にはCMA(費用最小化分析)やBIA(予算影響分析)などの手法がありますが、基本的な考え方は費用と効果を何らかの形で定量化し比較する点にあります。HTAでは評価対象や意思決定の場面に応じて適切な手法を選択・組み合わせ、総合的に判断します。特に公的保険の意思決定では、効果と費用のバランスを見るCEA/CUAが重視されますが、政策の観点によっては財政へのインパクトを見るBIA等も補助的に用いられます。
対象品目の選定基準と評価体制
対象品目の選定基準について、日本のHTA制度では「医療保険財政への影響が大きいもの」「革新性が高く高額なもの」を優先して評価対象に選定しています。厚生労働省が定めた具体的な基準では、新規収載医薬品の場合はピーク時年間売上高が100億円超と見込まれるものや、年間50~100億円規模で画期的なもの、また既存医薬品でも年間売上が1000億円以上となるもの、極めて高価格なものなどが対象候補となります。加えて、評価の比較対象として選ばれた製品(類似技術)も対象に含められます。
一方、例外的に対象から除外される基準も設定されており、例えば患者数が極めて少ないため薬価が高額にならざるを得ない製品(超希少疾病用治療薬)や、QALYでは評価が難しい抗がん剤等については費用対効果評価の対象外とされる場合があります。具体的には国指定の難病治療薬や血友病・HIV治療薬など「治療法が確立していない疾患」の薬剤、および小児疾患にのみ使用される薬剤は当面HTAの対象から外す、といったルールが設けられています。これは医療アクセスの観点から、極めて希少な疾患領域では費用対効果のみで価値を判断すべきでないとの考慮によるものです。ただし高額かつ販売規模が大きい製品は別途選定され得るため、全てが免除されるわけではありません。総じて、日本のHTAは社会的に影響の大きい医薬品・医療機器にフォーカスしつつ、医療上必要な領域への配慮も行うバランスを取った運用となっています。
評価体制については、厚生労働省の下部組織である中医協の費用対効果評価専門部会がHTAの審議を担い、最終的な評価結果(価格調整等)の決定を行います。実務的なプロセスは次のような段階を経ます:
分析準備・枠組み設定
対象品目に選定された製品について、製薬企業(または医療機器メーカー)はHTAの実施機関であるC2Hと協議し、評価の前提となる分析枠組み(対象患者集団や比較対照となる標準治療の選定)を決定します。これを「分析前協議」と呼び、分析結果が公正になるよう重要なステップです。
企業による費用対効果分析
分析枠組みに合意したら、企業側でC2Hの定めるガイドラインに沿って費用対効果の分析を行い、企業分析報告書を提出します。提出期限は原則として品目指定から9か月以内(その中に前協議期間も含む)と定められています。ICERを算出するため、臨床試験データだけでなく、必要に応じて国内外の文献、保険請求データや電子カルテなどのリアルワールドデータ(RWD)、専門家意見など多様な情報源を組み合わせる必要があります。ただしデータソースごとに患者背景が異なるため、結果統合には限界もあり、エビデンスの不確実性が課題となります。こうした課題に対応するため、日本では次世代医療基盤法による大規模データベース整備が進んでおり、診療情報(電子カルテ)と請求情報(レセプト)を連結可能なデータ基盤の活用が期待されています。
第三者による評価・再分析
提出された企業分析報告書の内容は、C2Hと独立した公的分析班(アカデミックグループ)によって精査されます。必要に応じてモデルの再分析やパラメータの検証が行われ、企業分析との差異や不確実性が評価されます。公的分析班は企業報告提出後180日以内を目安に評価結果(公的分析結果)をまとめます。企業側分析と公的分析の双方を材料に、最終的な費用対効果評価結果が取りまとめられます。
総合評価と価格調整
最終評価結果は中医協に報告され、総合的な評価に基づき薬価の調整が行われます。日本のHTAは価格調整型であり、評価結果が直接「保険適用する/しない」の判断になるわけではありません(英国NICE等と異なり、すでに保険収載済みの価格を後から見直すアプローチ)。具体的には、算出されたICERが閾値を上回る場合には薬価の引き下げ率が決定されます。日本では薬価算定時に有用性加算という革新性評価による上乗せや、会社利益率が含まれる仕組みがありますが、価格調整の基本はこの有用性加算部分の減額として実施されます(ただし原価計算方式で詳細不開示の場合は営業利益部分も含め調整)。
調整率はICERの水準に応じて数段階に設定されており、例えば標準的な治療でICERが500万円~750万円/QALYとなった場合は価格を30%減額、750万円~1000万円/QALYの場合は60%減額、1000万円/QALY以上は90%減額、といった具合です(小児疾患やがん等特別な配慮が必要とされる品目には閾値が1.5倍に緩和される措置あり)。逆にICERが非常に低く費用対効果が極めて良好と判断された場合、価格据え置きどころか増額も可能となる設計で、特に前述のドミナントケースでは大幅な加算が認められます。こうした最終的な価格調整案は中医協での審議・了承を経て正式決定されます。調整後の薬価は概ね評価開始から15~18か月後の次回薬価改定時に反映されるスケジュールとなっています。
以上が日本のHTAにおける評価手法とプロセスの概要です。制度開始から日が浅いため、評価の運用にはなお課題も残ります(これについては次節で述べます)が、国として専門の組織・手順を整え、医療技術を科学的・経済的根拠に基づき評価する仕組みを動かし始めた意義は大きいでしょう。
3.日本のHTAの現状と課題
医療制度との関係
日本におけるHTAの位置付けは、診療報酬(薬価)制度を補完する役割として定義されています。先に述べたように、新薬の承認可否や保険収載そのものを左右する仕組みではなく、承認・保険適用された医薬品の価格を事後的に調整するために費用対効果評価が活用されています。これは英国などのようにHTAで「この薬は費用対効果に見合わないから保険で使わない」といった償還(保険給付)可否を判断する形とは異なり、日本独自の運用と言えます。裏を返せば、日本の公的医療保険制度では国民皆保険の理念の下、基本的に有効性・安全性が確認された医薬品や医療技術は原則保険適用とし、HTAは価格の妥当性を担保することで制度の持続性を図る手段となっているのです。このため、HTAの実施タイミングも欧州では新薬発売前(事前評価)が主流なのに対し、日本では発売後に行われます。評価結果による価格調整は次回の薬価改定時に反映される仕組みで、患者や医療提供者にとっては治療アクセスがいきなり制限されることはなく、製薬企業にとっても発売直後から収益を得る機会は保証されています。
その一方で、医療保険財政に影響の大きい製品については後から適正な水準まで価格を引き下げることで、医療費の無駄遣いを防ぐというバランスを取っています。医療政策上は、このようなHTAの導入によって社会保障財政の持続可能性を高めつつ、患者への医療提供(サービス)の公平性・普及を両立させる狙いがあります。実際、2019年の制度本格実施以降、超高額薬を含む複数の医薬品で費用対効果評価が行われ、薬価の調整がなされています。例えば、一部のがん免疫療法薬ではHTAの結果を踏まえ大幅な薬価引き下げが実施され、年間数百億円規模の公的医療費削減効果が報告されています。このようにHTAは医療経済の視点から国の医療政策・制度に組み込まれ始めており、日本の医療システムにおいて重要な意思決定プロセスとなりつつあります。
糖尿病治療を例とした具体例
HTAの概念をより具体的にイメージするため、糖尿病治療を例に考えてみます。糖尿病は患者数が多く長期にわたる治療が必要な疾患であり、新しい治療法が次々と登場しています。ある新規糖尿病治療薬が開発されたと仮定しましょう。この薬剤Aは従来の標準治療Bに比べて血糖コントロールを改善し、合併症リスクを下げる効果が期待されます。一方で薬価が高く、年間治療費がBよりも大幅に増加するとします。HTAではまず、治療薬Aを用いた場合の患者の予後(平均寿命や合併症発症率、QOLなど)をモデルで予測し、A使用群とB使用群でどれだけ健康上の成果に差が出るかを評価します。例えば「Aを使うと平均余命が2年延び、その期間のQOLも向上する」といった効果を見積もります。同時に、医療費についてもAは薬剤費が高い代わりに合併症治療費が減る、といった費用の増減を計算します。こうして「追加2年分のQALYを得るために追加費用がいくらかかったか」をICERとして算出し、これが先述の基準値(例えば500万円/QALY)以下であれば費用対効果が高い=導入価値があると判断されます。逆にICERが基準値を超える(例えば1200万円/QALY)のようであれば、費用の割に効果が十分でないとみなされ、薬価を引き下げることでICERの改善(費用対効果の適正化)を図ります。
糖尿病のような慢性疾患では、患者は長年薬を使い続けるため、効果がわずかでも費用差が積み上がると経済的負担は大きく変わってきます。HTAにより長期的な医療コストとアウトカムを見通しておくことで、医療保険者(国)も患者も納得感のある治療選択が可能になります。実際、日本の糖尿病治療の現状を見ても、患者負担や社会保障費の増大が課題となっており、HTA的な視点でデータを分析し「費用に見合う効果が得られているか」を検証することは、医療の質(医学的有効性)と経済的効率の両立に寄与します。もちろん、糖尿病以外にもがん治療、希少疾病治療、予防医療など様々な領域でHTAの考え方は応用されています。臨床現場に直截に結びついたリアルワールドデータの活用や、治療効果だけでなく患者の生活への影響まで評価対象に含める視点は、まさにHTAが医療を総合的に評価するアプローチであることを示しています。
HTAの実施状況と課題
日本のHTAは制度的に走り出したとはいえ、まだ発展途上であり課題も指摘されています。まず、制度運用上の課題としては評価プロセスの煩雑さと時間が挙げられます。1品目あたり分析開始から最終評価までに約1年~1年半程度を要し、関係者の負担が大きいことから、2022年の見直しでは一部プロセスの効率化が図られました。それでも、増え続ける対象品目に迅速に対応するには人員・予算の拡充やプロセスのさらなる効率化が必要と考えられます。
次にデータ・分析上の課題です。HTAの質は前提となるエビデンスに大きく依存しますが、日本では医療データの統合利用がまだ充分とは言えません。臨床試験だけでは把握しきれない長期のアウトカムや費用情報を得るため、RWDや海外データの利活用が不可欠ですが、それらの情報を統合して分析する手法やデータ基盤は発展途上です。今後、データベース研究の推進や国際的な研究ネットワークとの連携が期待されます。
また、専門人材の育成も喫緊の課題です。医療経済評価を担う人材(ヘルスエコノミストなど)が国内ではまだ限られており、製薬企業・行政・学術いずれのセクターでも知見を持つ人材強化が求められています。さらに、患者や臨床現場の理解と協力を得ることも重要です。HTAは一見「医療をコストで評価する」ように受け取られ、医療者から抵抗感が示される場合もあります。しかし本来は限られた財源を有効に活用し、患者にとってより価値の高い医療を実現するのが目的であり、そのための価値評価のツールです。この理念を共有し、適切なコミュニケーションを図ることで、現場の協力やデータ提供などHTA実施に必要な基盤が強化されるでしょう。
特に指摘されることの多い課題が、患者視点の反映不足です。現状の評価プロセスでは、定量的なICERや専門家の評価が中心で、患者や市民の意見を直接取り入れる仕組みは十分整っていません。医療の価値は患者一人ひとりにとって異なる側面もあるため、質調整生存年(QALY)と費用だけでは測れない価値の次元も存在します。例えば、治療を受けることで得られる安心感や、介護者の負担軽減、社会復帰への寄与などです。こうした定量化しにくい効果や倫理的・社会的価値判断をどう評価に組み込むかは、日本のみならず国際的にもHTAの難題として議論が続いています。日本でも今後、患者団体の意見聴取やマルチクライテリア意思決定法の活用など、質的な要素を補完的に取り入れる検討が必要になるでしょう。
最後に、基準値設定の妥当性も課題です。日本独自の500万円/QALYという閾値は暫定的に導入された経緯があり、国民の支払意思額調査やGDP水準から見直すべきとの指摘もあります。今後、高額な遺伝子治療や画期的新薬が続々登場する中で、この基準値で本当に社会的価値を適切に評価できるのか、引き上げや柔軟な運用も含め継続的な見直しが必要とされています。
以上のように、日本のHTAは制度設計上・運用上いくつもの課題を抱えています。しかし、これらは裏を返せば改善の余地でもあります。実際に2022年の制度改正ではプロセス短縮など一部対応がなされましたし、厚生労働省や中医協でもさらなる調整や仕組み強化に向けた議論が続いています。諸課題を乗り越えながら、HTAがより日本の実情に即し、透明性・公平性・科学的妥当性を備えた高度な評価システムへと成長していくことが期待されています。
4. HTAがもたらす患者中心の医療
患者視点の評価とは
HTAの究極的な目標は、患者中心の医療の実現に寄与することです。ここでいう「患者中心」とは、医療政策や治療選択の意思決定において患者の利益や価値観を最優先に考えることです。HTAは一見、費用対効果という経済的な観点を導入するため、「患者本位よりコスト優先ではないか」と誤解されがちです。しかし実際には、限られたリソースを無駄なく活用して本当に患者にとって有益な医療を提供することこそが、HTAの目的に他なりません。医療技術評価が適切に行われれば、効果の乏しい治療や不必要に高額な医療サービスが淘汰され、代わりに価値の高い治療(患者のQOL改善や生存延長につながる効果的な治療)が推奨されるようになります。これは結果的に患者が受ける医療の質を高め、その人にとって最善の結果をもたらすことにつながります。
また、HTAでは質調整生存年(QALY)など患者の生活の質を反映する指標を用いるため、単に延命効果だけでなく「どれだけ健康に生活できるか」という患者にとっての価値も評価軸に含まれています。例えば、副作用が強く生活の質を著しく下げる治療よりも、多少効果が劣っても穏やかな副作用で日常生活を維持できる治療の方が、患者にとって価値が高い場合があります。QALYはそうした患者の視点を数値に組み込む工夫の一つです。さらに近年では、HTAの場に患者代表を参加させたり、患者報告アウトカム(PRO:Patient Reported Outcome)のデータを評価に組み込んだりする動きも国際的に進んでいます。日本でも将来的に、患者が自身の経験や希望をHTAプロセスに伝え、それを考慮した評価・意思決定が行われる仕組みが求められるでしょう。
要するに、HTAの本質は「患者に通知された上での意思決定を支援する体系的評価」であり、医療の直接・間接の効果を含めて患者にとっての真の価値を見極めることにあります。その結果導かれる政策判断は、患者にとって安全で効果的かつ最大限の価値をもたらす医療を模索するものとなります。これはまさに患者中心の医療を推進するアプローチと言えるでしょう。
医療の質向上とアウトカム評価
HTAがもたらすもう一つの大きな利点は、医療の質の向上とアウトカム(治療結果)重視の文化を醸成することです。従来、医療提供の現場では新しい技術や薬剤が出れば効果や安全性を確認して保険収載し、あとは医療者の裁量で使われてきました。しかしHTAの導入により、「その技術は本当に他より優れているのか」「費用に見合うだけのアウトカム改善が得られているか」をエビデンスとデータに基づき検証する流れが生まれます。これは医療従事者に対しても、常に治療の結果と費用を意識し、より良いアウトカムを追求する動機付けとなります。例えば、ある治療ガイドラインを作成する際にも、HTAの結果が参考情報として提示されれば、エビデンスの質とともに経済的なインパクトも考慮した総合的な推奨が可能になります。
また、HTAの実施には多職種・多分野のコラボレーションが必要です。医師などの臨床専門家は治療効果や患者の状態について知見を提供し、経済の専門家はコストや効率について分析し、行政は政策目標と制度設計を検討します。このように学際的(科学・社会科学的)な連携が進むことで、医療技術の評価に対する理解が深まり、ひいては医療の質保証体制が強化されます。HTA自体が「研究と政策決定の世界を橋渡しする」ことを意図しているとも言われ、医療現場の知見と医療政策をつなげる仕組みとして機能します。
アウトカム評価の観点では、HTAの普及により治療効果の定量評価がますます重視されます。例えば、これまであまり測定・評価されてこなかった患者の生活機能や長期的な生存率などを追跡する研究が増え、医療ビッグデータの整備も促進されます。その結果、医療政策だけでなく医療機関レベルでも、自院の治療成績やコストを分析して改善するという医療の質管理(Quality Management)の取り組みが活性化するでしょう。実際、HTAの考え方は院内の新規医療技術導入の評価や、保険者による給付適正化の分析などにも応用され始めています。最終的には、HTAによって示されたエビデンスに基づく改善策を取り入れることで、患者にとって有益な医療サービスがより効率的に提供されるようになります。これは患者の治療成績(アウトカム)の向上に直結します。
総合的に見て、HTAは医療を質(Quality)と結果(Outcome)で評価し、そこに資源配分の論理を組み込むことで、患者に最良の医療を持続可能な形で提供し続けることを目指すものです。その意味で、医療者にとっても患者にとっても win-win の仕組みと言えます。もっとも、HTAの効果を十分に引き出すには、評価結果を現場の意思決定に適切に反映させる運用が不可欠です。医療の質向上にはフィードバックループが重要であり、HTAで得られた知見をガイドライン改定や医療技術の選択に反映し、さらにその結果をデータ収集・研究につなげていくという循環を作る必要があります。そうした取り組みを継続することで、真の意味で患者中心の価値に基づく医療が実現していくでしょう。
5.国際的なHTAの動向と日本への示唆
英国NICEやドイツIQWiGなど諸外国の制度紹介
HTAは世界各国で導入・発展していますが、その仕組みや活用方法には国ごとに特徴があります。ここでは主要な国際的HTA制度をいくつか紹介します。
イギリス:NICE(英国国立医療技術評価機構)
英国はHTA先進国であり、1999年に設立されたNICEがガイドライン策定と医療技術の費用対効果評価を担っています。NICEでは増分費用効果比(ICER)に基づき、公的医療保険でその技術を償還(患者に提供)すべきかどうかを勧告します。通常 £20,000–30,000/QALY 程度の閾値が用いられ、この範囲を超えると原則不採用となるケースが多いです。ただし、小児や終末期など特定の場合にはICERの許容基準を緩和し、社会的価値を総合考慮する仕組みも取られています。NICEの判断は事実上英国の保険適用を決定づけるため、製薬企業は上市前にNICE向けの経済評価を用意する必要があります。英国におけるHTAは医療技術の採否決定に直結する点が特徴で、その厳格な評価プロセスと透明性の高いガイドラインは各国のモデルとなっています。なお、NICEは技術評価だけでなく臨床ガイドラインや医療サービスの効率化評価など広範な業務を担っており、医療の質と効率の両立に寄与する組織として機能しています。
ドイツ:IQWiG(医療品質・効率性研究所)
ドイツにはNICEのような償還可否の直接判断を行う仕組みはありませんが、IQWiGというHTA機関が2004年に設立され、医薬品や処置の相対的医療効果と費用に関する評価を行います。ドイツの特徴は、QALYなどの統一指標を用いない点です。IQWiGは主に新薬の「付加的治療効果」(有効性上どれだけ既存治療を上回るか)を評価報告し、その結果を基に連邦合同委員会(G-BA)が薬価の価格交渉に臨みます。つまり、ドイツではHTA結果は直接「使う・使わない」を決めるのではなく、製薬企業との薬価交渉で参考資料として使われるのです。
例えば「革新的効果が中等度」という評価なら価格プレミアムも限定的に、「効果なし」と判定されれば価格下げ要因になるといった具合です。ICERのような増分効率は出しませんが、その代わり臨床的有用性の程度を細かく評価する仕組みで、価格にメリハリをつけています。またドイツでは新薬は上市後1年間は自由価格で販売でき、その間にIQWiG評価と価格交渉が行われるというスピード感のある制度になっています。総じて、ドイツのHTAは経済評価より効果の評価重視で、価格決定の材料とするアプローチです。フランスのHAS(フランス高等保健機構)もドイツと似た運用で、QALY指標を使うこともありますが、最終的には価格交渉のための等級評価(ASMRと呼ばれる評価ランク付け)を行います。
カナダ・オーストラリア
カナダではCADTH(※2024年から組織改編されCDA-AMC)という連邦レベルのHTA機関があり、新薬の費用対効果評価を行って各州の公的薬剤ベネフィット採用の可否を勧告します。オーストラリアでもPBAC(医薬品給付諮問委員会)がHTAを経たうえで薬剤の保険収載を決定します。これらの国も基本的にQALYに基づくICERを判断基準としています。例えばオーストラリアPBACはおおよそ A$50,000/QALY 以下を一つの目安としていると言われます。また予算影響や地方への波及効果なども考慮しますが、やはりHTA結果が償還決定に直結する点では英国型に近いといえます。
アメリカ合衆国
米国は公的保険による一元的な償還システムがなく、民間保険主体のため政府主導のHTA制度はありません。ただしICER(Institute for Clinical and Economic Review)という独立組織が存在し、費用対効果に関するレポートを公表しています。ICERは新薬の経済評価を行い、ベンチマークとなる価格レンジを提示するなど、透明性ある情報提供で支払い側(保険者)や患者への意思決定支援を図っています。法的拘束力はありませんが、近年その影響力は増しており、製薬企業もICERの評価を無視できなくなっています。米国ではコスト重視への反発も根強く、公的にQALYを用いることには批判がありますが、民間ベースでHTA的な取り組みが進んでいる状況です。
以上のように、諸外国のHTA制度は国の医療提供・保険制度と深く関連しており、日本のように価格調整のみを行うケース、英国のように採否を決めるケース、ドイツのように価格交渉に使うケースなど様々です。どの国でも共通するのは、医療技術評価の際に経済的な効率と臨床的有用性の双方を考慮し、限られた資源を最大限有効活用しようとしている点です。また各国HTA機関同士の連携も進んでおり、INAHTA(医療技術評価国際ネットワーク)やEUnetHTA(欧州医療技術評価ネットワーク)といった国際組織を通じて情報交換や手法の標準化が図られています。例えば欧州では共通のHTAレポートを各国で共有し、それぞれの国の意思決定に活用する仕組みづくりも進行中です。こうした国際的動向を踏まえ、日本も自国の制度を磨き上げていくことが重要です。
| 国・機関 | HTA評価の特徴 | 結果の活用 |
|---|---|---|
| イギリス (NICE) | QALYを用いたICER評価が中心。小児や末期疾患では特例考慮あり。 | HTA結果に基づき、公的医療保険の償還可否を勧告。 |
| ドイツ (IQWiG) | QALYは用いず臨床的有用性を評価。増分効果を定性的に判定。 | 評価結果は薬価交渉の材料として用いる(償還は原則保証)。 |
| フランス (HAS) | 必要に応じQALYも使用。臨床的有用性(SMR)と追加価値(ASMR)で等級付け。 | 評価等級に応じて薬価を調整(償還可否には直接影響せず)。 |
| カナダ (CADTH) | QALYベースの経済評価+予算影響分析も重視。 | 評価に基づき各州の採用可否を勧告(事実上カバレッジ決定に影響)。 |
| オーストラリア (PBAC) | QALYを指標にコスト効率を評価。患者数や重症度も考慮。 | HTA結果を踏まえ薬剤給付リスト収載を決定(閾値は約A$50,000/QALY)。 |
| 日本 (中医協・C2H) | QALYあたり500万円を基準にICER評価。価格調整型の評価。 | 評価結果に応じ薬価を増減調整(保険収載可否には影響せず)。 |
海外データベースの活用事例
国際的なHTA動向としてもう一つ注目すべきは、リアルワールドデータ(RWD)や医療ビッグデータの活用です。欧米やアジア各国では、医療保険データベースやレジストリ(患者登録)をHTAに役立てる取り組みが進んでいます。例えば、イギリスにはNHSが保有する大規模データ(Hospital Episode Statisticsなど)があり、NICEの評価プロセスでも必要に応じてそれらが分析に使われます。フランスやカナダも公的医療データベースを整備し、薬剤の実世界での有効性や安全性の情報を集積しています。また国際共同データベースも充実してきており、欧州のEUnetHTAでは各国が持つエビデンスを共有する仕組みがあります。具体例として、欧州には欧州医薬品庁(European Medicines Agency)が運営する患者レベルのデータネットワークや、各国HTA機関が共同で構築した疾病別のアウトカムデータ集などがあり、ある国で不足するデータを他国の情報で補完するといった連携も見られます。さらに、製薬企業側でもグローバル治験の長期追跡結果や海外の疫学データをHTA提出資料に引用することが一般化しています。
日本にとって参考になる海外データ活用のエピソードとしては、たとえば英国NICEがあるがん治療薬の評価時にアメリカのがん登録データを用いて長期予後を推計した例や、オーストラリアPBACが自国で不足する患者報告アウトカムのデータを欧州の臨床研究から補った例などがあります(※具体的事例は各国HTA報告書に記載)。こうした事例は、「必要なデータは国外のものであっても積極的に活用する」姿勢を示しています。日本でも、国内データが乏しい場合は海外文献や周辺国のエビデンスを取り入れることが評価ガイドライン上認められており、今後ますます国際データベースを参照する機会が増えるでしょう。実際、C2Hのガイドラインでも海外の臨床試験結果やメタ分析の活用が想定されていますし、必要に応じ専門家へのアンケート調査など多角的手法でデータ収集することも推奨されています。さらに、日本はリアルワールドデータの面でも遅れを取り戻しつつあり、近年診療情報とレセプト情報の連結データが利用可能になったことで、実臨床下での治療効果や費用をより正確に把握できる環境が整ってきました。例えば、既存のDPCデータやレセプトデータを解析して費用項目を洗い出したり、患者報告アウトカムを収集する研究(PRO研究)を行って参考値を得たりする事例も出始めています。このように、データ活用はHTAにおけるエビデンスの質を左右する鍵であり、日本も海外のケースを教訓にしながら自国のデータインフラを強化・活用していく必要があります。
日本への応用可能性と示唆
諸外国のHTA制度やデータ活用事例から、日本への示唆として得られるポイントをまとめます。
まず、意思決定プロセスへの組み込み方です。日本のHTAは価格調整に限定した運用ですが、英国のように明確な基準に基づき採用可否を判断する方式は、医療資源配分の透明性を高めるメリットがあります。もっとも国情や文化の違いもあるため、一概に英国型が良いとは言えませんが、少なくとも評価結果と政策決定の結び付きをより強くすることは、制度の実効性向上につながるでしょう。例えば評価結果を診療ガイドラインの改定や医師への情報提供に反映させ、臨床現場の選択に影響を与えるような仕掛けも考えられます。またドイツやフランスにならい、HTA結果を価格交渉で柔軟に活用することも一案です。現状でも一部そうした側面はありますが、より創造的な価値に応じた価格設定(例えば画期的新薬には高価格を認めつつ一定期間後に再評価する等)を制度化する余地があります。
次に、患者参加と社会的価値の考慮です。諸外国では患者や市民の視点を取り入れる努力が続いており、日本も公聴会的な場を設ける、患者代表を委員に加える、アンケートで広く意見を募るなど、HTAのプロセスに多様なステークホルダーの声を反映させる工夫が求められます。例えば英国NICEには市民カウンシルがあり価値判断に関する勧告を行っていますし、カナダCADTHでは患者グループからの事前意見聴取制度があります。日本でも中医協の枠組みの中で患者や国民の価値観を議論に載せる工夫を凝らすことで、より患者中心の評価につながるでしょう。
三つ目に、国際協力と情報共有です。HTAは世界共通の課題に取り組む分野であり、日本も積極的に国際ネットワーク(例えばHTAiやISPORの学会活動)に参加し、最新の知見を取り入れることが重要です。また、他国のHTA事例を国内向けに紹介・分析する専門家コミュニティを育て、最適な手法を自国版にアレンジしていく努力も必要です。例えば、イギリスNICEの手法をそのまま真似るのではなく、日本の医療制度に適合する形でガイドライン化する作業などです(実際、日本の費用対効果評価ガイドライン策定には海外専門家の助言も取り入れられています)。さらに、アジア近隣国ともHTAに関する情報交換を進めることで、地域特有の課題(例えば高齢化の進行や医療保険財政の似た構造)に対する共通解を探ることも考えられます。韓国は2008年にアジアで先駆けてHTAを導入しており、台湾も医療技術評価センターを設立するなど動きがあります。こうした国々との協調も将来的に日本のHTA高度化に役立つでしょう。
最後に、長期的視野に立った制度発展の必要性です。HTAは導入して終わりではなく、常に研究と科学的手法の進歩に支えられて発展していくものです。日本版HTAも今後、医療技術や社会の変化に応じて進化が求められます。例えば、AI医療やデジタルヘルスといった新領域への評価方法の確立、予防医療や介護との連携評価、さらには医療以外の社会サービスとの包括的アセスメントなど、挑戦すべきテーマは数多く存在します。海外ではすでに、医療機器やデジタル治療に特化したHTAの枠組みや、高度な価値評価手法の研究が行われています。日本もそうした流れに乗り遅れないよう、産官学でのオープンな議論と実証を重ね、HTAを自国のニーズに合った形で深化させていくことが重要でしょう。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. HTAの評価は誰が行っていますか?
A1.日本では、HTAの制度運用は厚生労働省のもとで中央社会保険医療協議会(中医協)の医療技術評価分科会が担当しています。具体的な分析作業は、製薬企業が提出したデータをもとに保健医療経済評価研究センター(C2H)や有識者からなる公的分析班が行い、その結果を踏まえて中医協で評価・薬価調整の決定がなされます。要するに企業・国の研究機関・中医協という三者が連携して評価プロセスを進めている形です。
Q2. 費用対効果評価の具体例を簡単に教えてください。
A2.
例えば、新しい抗がん剤Xと既存の標準治療Yを比べるケースを考えます。臨床試験でXはYより患者の平均寿命を1年延ばし、副作用プロファイルも良好だったとします。一方、Xの治療費はYより高く年間100万円の追加費用がかかるとします。この場合、費用対効果の指標であるICERは「100万円の費用で1年の質調整生存年(QALY)を得た」と計算されます。仮に日本の基準値である500万円/QALYと比較すると、100万円/QALYは十分に低いため「費用対効果が良い」と判断できます。逆に追加費用が1000万円かかるのに延命効果が数ヶ月程度であればICERは大幅に基準値を超えてしまい、「費用対効果が低い」と評価されます。その結果、薬価を引き下げてICERを改善させる措置が提案される、という流れになります。このように具体的数値で見ると、費用対効果評価は「追加コストに見合うベネフィットか」を判断するものだとイメージできるでしょう。
Q3. HTA導入のメリット・デメリットは何ですか?
A3.
メリット: HTAを導入することで、医療資源の配分が合理的になり、医療保険財政の効率性向上が期待できます。限られた予算を本当に価値の高い治療に振り向けることで、結果的に患者が受けられる有効な医療が充実します。また、評価プロセスを通じてエビデンス集積が進み、医療の透明性・説明責任(アカウンタビリティ)も高まります。製薬企業にとっても、真に画期的な製品であれば高い価値が公的に証明され、適正な評価を受けられる利点があります。
デメリット: 一方で、HTAのプロセスには時間とコストがかかるため、制度運用の負担が増大します。企業は経済評価のデータ提出や価格交渉に追加リソースを割く必要があり、行政側も専門人材や分析予算を確保しなければなりません。また評価結果によっては収益見通しが下がるため、企業の新薬開発意欲にマイナスに働く懸念も指摘されます。しかしそのリスクを抑えるために日本では価格調整に留める運用としており、革新的製品が締め出されないよう配慮しています。さらに、費用対効果の数字だけが独り歩きすると「費用のために患者の命を切り捨てるのか」といった誤解や反発を招く可能性もあります。従ってHTAの導入には、関係者への十分な説明と理解醸成が欠かせません。このようにメリットとデメリットがありますが、総じてHTAは適切に設計・運用すれば医療の質と持続可能性を両立させる有力なツールとなり得ます。日本ではまだ始まったばかりの制度ですので、課題を改善しつつメリットを最大化できるよう取り組んでいくことが重要です。
まとめ
HTA(医療技術評価)は、医療技術の有効性や安全性だけでなく、経済的・社会的な側面も含めて総合的に評価する仕組みです。日本でも制度化が進み、医療資源の最適配分や医療保険財政の持続可能性を支える重要な役割を果たしています。費用対効果評価やQALYなどの指標を用いることで、患者にとって本当に価値のある医療を見極めることが可能となりました。今後もHTAの活用が進むことで、医療の質向上と効率化が期待されます。
今後の展望
今後のHTAには、以下のような発展が期待されています。
患者・市民参加の強化
患者や市民の意見をより積極的に評価プロセスに取り入れ、医療の価値を多面的に判断する仕組みが求められます。
リアルワールドデータの活用拡大電子カルテやレセプトなどの実臨床データを活用し、より現実的な費用対効果評価を行う体制の整備が進められています。
国際連携と標準化
諸外国のHTA機関との情報共有や手法の標準化を進めることで、グローバルな視点での医療技術評価が可能になります。
新技術への対応
AI医療やデジタルヘルス、遺伝子治療など新しい医療技術にも柔軟に対応できる評価手法の開発が求められています。
HTAは今後も進化し続け、患者中心かつ持続可能な医療システムの実現に向けて、ますます重要な役割を担っていくでしょう。
- 【日本薬学会第145年会】SaMDのHTA機関評価ルール設定‐仏独白の3国のみ(2025年04月02日)
- 夢も希望もない社会(2018年09月26日)
- 【PhRMA】新薬創出等加算の見直し要望‐パトリック委員長「日本への投資なくなる」(2018年01月31日)
- 費用対効果評価(HTA)の試行的導入(2016年09月07日)
- 将来の薬局のあり方が問われた年(2015年11月06日)
- 日本のHTA導入に懸念‐PhRMA・グレンジャー氏「患者の医薬品アクセスに影響」(2015年09月02日)
- 関心高まるHTAの活用(2014年12月12日)
- HTA活用メリットなど例示‐国立保健医療科学院 福田氏が講演(2012年09月25日)
- 【民主党医療・介護WT】次期改定に向け議論開始(2012年04月24日)
- 【EFPIAジャパン】フォシェ新会長が初会見‐医療技術評価委立ち上げ(2012年02月29日)