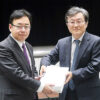松浦氏
日本新薬取締役研究開発本部長の松浦明氏は、本紙の取材に応じ、新薬創製の目標について、「2年で3品目の自社創製品の臨床開発入りを目指したい」と語った。日本新薬は2年前、大手製薬企業とは競合しないニッチ領域に、研究資源を集中させる方針を明確化。自社創製の対象を、▽血液がん▽泌尿器科の慢性炎症性疾患‐‐の2領域に絞り込んだ。以前から強かった領域を、さらに強化する戦略だ。成功確率を高めると共に、開発期間を短縮し、10年後には2年に1品目の自社創製品を上市できる体制を目指す。
同社は2009年、全社的な研究開発コンセプトを策定した。以前は明確な方針がなく、研究部門が独自の考えで研究に取り組んでいた。それを改め、社内の各部門が参加して協議し、1年かけて方針を決めた。営業部門が強い診療科を意識して、研究開発資源を集中化。他社からの導入や自社品の創製を目指す体制に変わった。
導入の対象は、血液内科、泌尿器科、婦人科、耳鼻咽喉科、整形外科の5診療科。これらの診療科を中心に、開発パイプラインを充実させる方針を、改めて明示した。
一方、自社創製の対象は、診療科でいうと血液内科と泌尿器科、疾患でいえば血液がんと泌尿器の慢性炎症性疾患の2領域に絞り込んだ。「以前は研究テーマの底辺は広く、領域を絞っていなかった。現在は、二つの領域の中で可能なテーマを挙げなさいと、起案自体に制限がかかっている」と松浦氏。「資源の集中化が成功確率とスピードアップにつながる」と話す。
コンセプト策定によって、以前から取り組んできたことが、より明確になった。その一つが、ニッチ領域への集中だ。例えば、大手製薬会社が手を出しづらい、売上高の見込みが30億円ほどの製品でも、医療用医薬品の売上高が500億円台の同社にとっては、売上増への貢献度は大きい。ニッチ領域に集中することで、大手製薬企業との競争を回避でき、成功確率を高められる。
また、オーファンドラッグに指定されるような、患者数が少ない疾患や難病であったりすれば、高い薬価が期待できる。海外のデータがあれば、国内臨床試験の症例数は少なく済み、開発期間を短く、費用も安く抑えられる。
「血液がんはまさにニッチ。国内の大手製薬企業では、以前は取り組んでいるところはなかった」と松浦氏は振り返る。同社は約10年前から本格的な研究を開始。見出した「NS‐187」(バフェチニブ)を導出し、現在、B細胞性慢性リンパ性白血病や進行性前立腺癌などを対象とした第Ⅱ相臨床試験が、海外で進行している。
同剤は、各種のチロシンキナーゼを阻害する作用を持つ。血液がんには様々なタイプがあるが、その標的分子の構造は似ているため、バフェチニブに似た構造の化合物群は、様々な血液がんの治療薬になり得るという。候補品ライブラリーの充実に伴って、成功確率やスピードも高まり、今後、血液がん領域で複数の薬剤を生み出せるかもしれない。「一つずつ適応を取っていけば、ミニブロックバスターになる可能性がある」と松浦氏は、この領域に期待する。
一方、泌尿器科領域は、「大手製薬企業が参入する過活動膀胱などの分野は、競争が激しいものの、大手の入り込まない分野が泌尿器領域にもある。そこに注目して取り組んでいる」。研究部門の人員は、本社にある西部創薬研究所(京都市)に約160人、東部創薬研究所(つくば市)に約20人という体制。人員や費用などの研究資源を、泌尿器科領域に6割、血液がん領域に3割の配分で振り向けている。
残り1割の研究資源を投下するのは、東部創薬研究所で取り組む核酸医薬品の研究。3年後の臨床開発入りを目指し、修飾型オリゴ核酸の研究が進んでいる。
もう一つは、長鎖RNAの活用。数年前に、高収率、高純度で長鎖RNAを合成できる技術を確立した。RNAワクチンとして活用すべく、研究に取り組んでいる。また、遺伝子発現を長鎖RNAで制御し、分化誘導剤、分化促進剤として、血液がんの治療を目指す研究について今後、外部機関と連携して進めたい考え。「長鎖RNAの使い道が見えてきた」と松浦氏は話す。