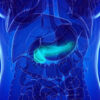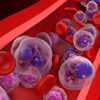今月に行われた2022年度薬価改定では、実勢価等改定分が薬価ベースで6.69%(医療費ベースで1.44%)引き下げられ、新薬の特許期間満了後に薬価を引き下げる新薬創出等加算の返還額の総額が、加算額の総額を初めて上回った。
新薬創出等加算の対象品目の拡大や市場拡大再算定対象品目の類似品のルールにおいて、一定条件下で対象除外とするなどイノベーションを評価する方向で一部改善が図られたものの、薬価ベースで大まかに見積もると国内医薬品市場から6000億円程度が失われることになる。海外売上比率が低い製薬企業の業績に影響を与えるのは必至だ。
気になるのが中間年改定の行方である。21年4月の中間年改定では、薬価調査の平均乖離率0.625倍超と全体の約7割の品目が対象となった。当初は実勢価と薬価の乖離率が著しく大きい品目のみを対象にするとしていたたため、多くの製薬企業が想定を超える打撃を被った。
財務省は、財政制度等審議会財政制度分科会で毎年薬価改定の完全実施を要求している。今後、中央社会保険医療協議会で中間年改定のあり方について議論されることになるが、21年と同規模もしくはそれ以上の規模で改定の対象品目が拡大すれば、新薬開発の意思決定を行う上で重要となる事業の予見性がますます見失われる恐れがある。
製薬関連団体からは、度重なる薬価改定によって、欧米で承認済みの医薬品が国内で開発されないドラッグラグの再燃が懸念されている。
厚生労働行政推進調査事業「薬価制度抜本改革に係る医薬品開発環境及び流通環境の実態調査研究」(研究代表者:北里大学薬学部成川衛教授)の研究結果からは、新薬開発で米国、欧州の申請・承認時期から日本が遅れる“申請・承認ラグ”が、これまでの短縮傾向から直近数年間で頭打ちになっていることが明らかになった。
製薬企業を対象としたアンケート調査でも、開発中の品目について日本での開発を断念、保留したものが「ある」「近い将来にある可能性が高い」と回答した企業が、大手20社では9割に上った。主な理由として「中間年改定」を挙げる企業が3年前に行った調査から増加した。
10年度から試行導入された新薬創出等加算は、ドラッグラグの解消に大きな貢献を果たしてきた。しかし、18年度の薬価制度抜本改革で新薬創出等加算の対象品目が見直されたのを契機に、5年連続で薬価改定が行われ、その効力は失われつつある。
安定確保医薬品や供給不安が続いている後発品を継続的に安定供給できるような薬価設定も重要な検討課題である。医薬品の安定供給や新薬開発などのイノベーションに歪みが生ずることがあれば、不利益を被るのは患者だ。そういう意味でも、大規模な中間年改定の実施は慎重に考えなくてはならない。