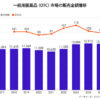認定制度改革への対応支援

左から土井氏、久保氏
医学アカデミー YTLは、MR認定センターが2026年度の実施を予定するMR認定制度改革に伴い製薬企業が必要になる対応を支援していくサービスを準備している。基礎教育はこれまで通りの万全のサポートに加え、特に企業側が行う実務教育(導入研修、継続研修)支援にも注力する。実務教育では、「倫理」と「安全管理」において、認定センターが定める「実務教育認定基準」に基づいて実際に行動できるMRに向けて教育を行うことになる。企業ごとのあるべきMR像をどう定め、その達成度をどう評価し、教育していくのかについては各企業の悩みは多いという。そこでMR教育を手がけ、活動現場を知る同社は、蓄積してきたノウハウを生かして実務教育認定基準も視野に入れて各社の教育を支援する。
MR認定制度改革では、現行のMR認定試験はなくなる。各個人が取り組むMR基礎試験の合格証と、企業が実施する実務教育(導入研修)の修了認定のいずれも揃うことで初めてMR認定証が交付される仕組みに変わる。認定証の更新は、基礎教育と実務教育(継続研修)の修了認定が必要になる。
実務教育では現行では7科目で、そのうち「倫理」と「安全管理」においてはSBOを設定することが求められているが、内容は企業側に委ねられている。MR認定制度改革においては、認定センターが同2科目については全社共通の実務教育認定基準を定め、SBO(到達・行動目標)とともに具体的な「行動」まで明確化され、それに沿って企業が研修を計画・実施し、行動項目が具体的にできるかを成果確認する。
認定センターは、同基準が「MRの必須の行動基準」であり、ミニマムリクワイアメントと位置づけ、コンピテンシー(優秀なMRの行動特性)ではないとしている。そこで各社は同基準をベースに自社MRのあるべき姿を目指していくことになる。
ここで同基準と自社の定めるあるべき姿とをいかに連続性のあるものにするかが悩みどころになる。
同社は、この認定基準を満たすための新人向け教育・未達者向け教育の支援を行う。加えて、これまでのMR教育で蓄積した知見、ノウハウをもとに、理想のMR像を定義するオリジナルのコンピテンシーを開発している。
この理想のMR像は特定の企業に限定するものではなく、広く医療関係者から信頼されるパートナーとして高い質の活動ができるレベルを想定している。また、業界内外の様々な環境変化も考慮し、現代のMRに求められる能力要件やレベル別の具体的な行動を盛り込む予定にしている。
企業が導入する際には、各社の目指すMR像をヒアリングし、その企業に特有のオリジナルな評価・教育体系にカスタマイズしていくことをイメージしている。
さらに、営業所長のMRへの指導育成力の維持、強化への教育支援サービスも開発する予定だ。
制度改革の26年度実施に向けて各企業は運用に向けて準備も進めていく必要がある。
その点、企画制作部メディカル教育課の土井勇人主任は、「YTL版コンピテンシー素案はほぼできている。コンピテンシーは各社によってカスタマイズが必要になるので、われわれの出す案をベースに各社様と協議して、一緒に作り上げていくことになる。ぜひご相談いただければ」と、対応可能な状態にあると説明する。
同部メディカル教育課の久保雅樹氏は、「これから先何十年を見据えて、医療関係者から信頼される理想のMR像を打ち立て輩出するにあたり、理想像の設定から評価・教育制度の運用まで、どんな些細なことでも構わないのでお手伝いできれば非常に嬉しい」と、メッセージを送る。
医学アカデミー YTL
https://www.ytl.jp/