新興住宅街で一から面分業展開‐「生活」に視点を置き指導充実

はまなす薬局
東京に隣接する埼玉県三郷市の新興住宅街で、5年前に面分業を目指して開局したメディスンショップ「はまなす薬局」(管理薬剤師・高田泰江さん)では、一般の外来処方箋のほか、老人ホームやグループホーム、個宅の患者向けの在宅調剤(薬の管理、服薬指導)をしている。最寄り駅は秋葉原と筑波を結ぶ、つくばエクスプレス線の三郷中央駅。歩いて5分ほどの距離だ。駅前にはビル診と薬局・ドラッグストアを含む複合商業施設があるが、周辺の開発はこれからという状況。同駅から、はまなす薬局までの道中、いくつかの診療所と寄り添う薬局が目立つため、ぽつんと建つ印象だが、地域のかかりつけ薬局として軌道に乗りつつある。
患者負担考慮し「ジェネリック医薬品」へ積極変換
はまなす薬局の薬剤師は、高田さん1人、他に事務員が2人(パート1人含む)という構成。1日20~30枚の処方箋を受けているが、処方箋の発行機関数は75を超す。そのため、医薬品在庫は約1300品目に達する。
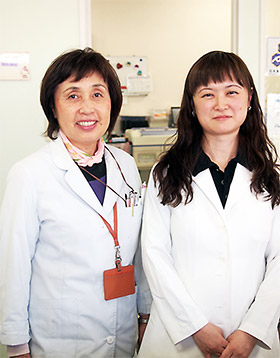
高田さん(右)と2人で
高田さんは5年前、苦い経験を踏まえ近隣でのマンツーマン薬局を閉め移転、面分業に打って出た。しかし「当初、周りからは絶対に面分業は無理、潰れるに決まっていると言われました。2人薬剤師だったのと、以前からの患者さんの激減で、正直とっても赤字で大変でした」と当時を振り返る。
ただ現在は、患者がぽつぽつと訪れ、特にピークもなく、飛び込みの患者も少なくない。開設当初から、近隣住民や病院からの帰り道の患者が飛び込みで入ってきて定着するというパターン。「次にまた来たいと思ってもらえるような薬局作りをモットー」に、徐々にだが着実に患者の支持が広がっている。その理由を「私がよくしゃべるから」と笑う。確かに事務員も含め、よく会話する。話題は幅広いが、高田さんが特に注意するのは、食事や睡眠などを中心にした生活全般についてだ。
「お薬に頼るのではなく、食生活や生活習慣をきちっとしてもらえば、薬は要らなくなると思います。塩分を控える。おやつを食べない。夜遅く食べない。よく噛んで食べる。食べ過ぎない。飲みすぎない。喫煙量に注意する。これらを守れば、ある程度の疾患は多少なりとも緩和できるはず」との信念のもと、生活習慣改善を促している。
また患者さんには「できるだけお金を使わないように」との思いから、ジェネリック医薬品(GE薬)への切り替えも積極的だ。「他の薬局と違いGE薬への変更がしやすい」と評判だ。実際、その比率は40%を超えている。
新興住宅街とはいえ昔からの住民も多く、患者の半数は高齢者。約75医療機関から処方箋を受けるだけに診療科も多様だ。ただ、その4割弱は、1kmほど離れた総合病院の患者だという。
ITとアナログ組合わせ“在宅”推進
さて、開設間もなく高田さんの在住地・千葉県船橋市で、あるグループホームの患者を対象に訪問薬剤管理を引き受けた。以降、三郷市でもグループホーム1軒(15人)、サービス付き高齢者住宅1軒(14人)、さらにケアマネなどから近隣個人宅の患者の依頼も増え、今では76人ほどの“在宅患者”を担当している。
患者数の増加と共に、主治医に返す報告書は「手間がかかる。書類作りは大変」ということで、手軽に現場で記録できるツールはないかと探していた。そこで出会ったのが東日本メディコムの「iPad用訪問アプリDrugstar iMove」だ。「指導内容など紙にメモし、戻って記録をつけるのでは、タイムラグがあり、十分な内容も書けなかった」と振り返る。
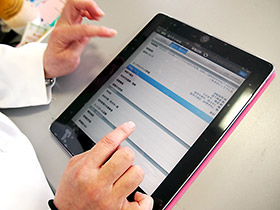
現場では優先度に応じて適宜記録する
いまは重たい紙ファイルに代わって、VPN経由でサーバーに接続されるiPadを持参。薬局にいるのと同様、薬歴をチェックし、聞き取った内容をその場で入力できるのが利点。「“薬情”だけで物足りない患者さんには、メーカーのページを開き、詳しく説明できる。その場で添付文書のチェックもでき重宝しています」と、サクサク情報収集できる点に魅力を感じているようだ。
多様な関連アプリが使えるのも利点だ。“在宅患者”の3分の1は認知症であり、指導上、その進み具合は気になる。そこで認知度チェックのアプリを使ってみたり、患者との簡単なやり取りや会話で大まかに状態を確認している。コンプライアンスの維持のため多様な機能を活用している。
簡単に現場入力できるため「報告書をあげるのが非常に楽になり、患者さんの状況がより細かく伝達できるようになった。報告書の質も向上したと思います」と笑う。
ITを活用しつつもアナログな工夫もしている。表裏で2週間分のお薬カレンダーを手作りし、認識ができる人には自身で薬をセットしてもらう。困難な場合は、各患者専用のトレーにセットして届けるという。
その届け方にも一工夫。例えば90日の長期処方は1カ月分のみ一包化して届け、残りは薬局で個々の患者専用に薬箱で預かる。適宜届け、少しでも現場での混乱、間違いが避けられるよう手間をかけている。「確実に患者さんに飲んでもらう手段」という。
高田さんは「自分たちの視点でなく、“できない人”の視点に立ち、どうしたら喜んでもらえるかを考え、(薬剤師の)仕事をすべき」と語る。
東日本メディコム
http://www.e-medicom.co.jp/



















