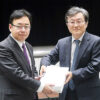薬価制度の抜本改革が来年度から実施される。特許が切れた長期収載品の薬価を段階的に後発品まで引き下げ、イノベーションを評価する新薬創出等加算は革新性の高い新薬に絞り込まれる。品目・企業要件については業界から批判も強いが、まず2年間は新制度を運用して課題を探ることになる。いずれにしても、国内製薬企業にとって、長期収載品依存からの脱却、革新的新薬の創出を一層促す流れが加速するのは必至の情勢となった。
日本の医薬品市場は、良くも悪くも長期収載品のシェアの高さが特徴で、切り崩しが難しい市場であったが、いよいよ後発品の数量シェア8割時代を迎えて本格的に決別する時代が到来した。近年、新薬の開発も難易度は高まるばかりであり、薬価上のインセンティブを得るため、より狭き門に挑戦せざるを得なくなる。世界的に開発コストが高騰し続ける中、成功確率は低下している。メガファーマを含め世界の製薬企業がそのジレンマと戦っている中、国内製薬企業は活路を見出すべく大きな岐路に立っているといえよう。
この二つの難題に立ち向かうためには、規模の大小はあれ、全てのバリューチェーン機能を自社で持ってきた業態転換が急がれるのではないか。特に製薬企業のイノベーションの源泉となるのは研究開発費であり、資金力のない中小メーカーにとっては、体力をどう確保するかが喫緊の課題となる。創薬技術は日進月歩の状況であり、グローバル競争に打ち勝てる資金力を確保するには、もはや中小でフルバリューチェーン機能を持つ現在の業態では存続が難しいかもしれない。導入や買収、水平合併を行っても大規模なリストラは避けられず、行き詰まる可能性がある。
一方、日本は世界でも指折りの創薬国であり、それを支えてきた国内製薬企業の研究力は大きな資産だ。今後、研究開発、製造、販売部門の外注化やIT化などによりダウンサイジングが進むと見られるが、それにとどまらず新薬創出の一点に絞って研究開発部門の創薬技術を結集し、ベンチャー型として企業統合する道も十分考えられる。現有部門をどう整理、集約し、軟着陸させるか極めて大きな難題となるが、既に製薬各社で化合物ライブラリーの共同利用が始まっている。こうした取り組みをベースに新薬のイノベーションを最優先する体制づくりは一考に値するのではないか。
日本発のイノベーションが結集した免疫チェックポイント阻害剤「オプジーボ」は、そのイノベーションが高く評価されるべき画期的新薬だったが、政府による医療費抑制策や制度の不備に翻弄される事態に直面した。その時の都合で新薬本来の価値を損ねることはあってはならないのは当然だが、一方で今後、イノベーションの評価は狭き門となり、新薬が生み出せなければ経営危機に直結する時代になる。
まず何よりも新薬を出し続けるにはどうしたらいいか、それを最優先にした動きに注目したい。