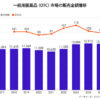世界でも類を見ない速度で少子高齢化が進行しているわが国だが、人手不足をはじめとした少子高齢化の様々な影響は薬業界においても例外ではない。その中で、医療やセルフメディケーションを担う重要なキーパーソンとして、薬学生への期待が一層高まっており、薬学生の就職を取り巻く環境は、依然として売り手市場が続いているとされている。
薬学教育協議会による「薬系大学卒業生・大学院修了者就職動向調査」によると、薬学生の就職先としては薬局が最も多く、ドラッグストアなどの一般販売業を合わせると、就職者の合計は4割を大きく超えている。それだけ多くの薬学生が就職する薬局やドラッグストアは、学生が入社して良かったと感じたり、働きがいがあると思えるような状況や環境を作り上げる必要がある。
薬学生の就職に関する課題などへの対応を協議、検討している取り組みの一つが「薬学生のための合同企業・大学交流会」である。交流会は薬学部・薬科大学の就職担当責任者と調剤薬局、ドラッグストアなどの人事採用担当者らが一堂に介する場で、継続的に企業と大学が協力し合い、学生の社会人への道をより良いものすることが目的とされている。今年開催された交流会には31大学30企業が参加している。
交流会では、入社後のミスマッチや早期離職をテーマに、原因や解決法などが探られ、ミスマッチや早期離職につながる問題点として「インターンシップと称して就職活動が行われている」「合同説明会の時期が早すぎる」とスケジュールの早期化を挙げる声や、「内定を得てから決定までの期間が短い」「ガイダンスを複数回開催する余裕がない」といったタイトなスケジュールを指摘する声が多かった。学生側、企業側の双方にとって、じっくりと考える時間がないのが現状だと言えそうだ。
こうした問題点を踏まえて今年の交流会では、選考開始時期や会社説明会の時期などについて、業界内で足並みを揃えた形である程度のルールを明確化するよう求める声が挙がった。ルールを定める上で、情報収集など交流会の果たす役割への期待も寄せられたが、自社のみの利益を考えた行動を再考する必要性など企業側のモラルも当然問われていくことになるだろう。
就職は、学生のその後の人生を左右する分岐点の一つと言っても過言ではない。こうした認識を企業側は持ち、志望する学生一人ひとりと丁寧に向き合ってほしい。
一方の学生側も、目先の損得や一時の感情により、就職先を軽々に決めることは避けるべきであろう。今後、企業側、学生側にとってうまくマッチした就職が実を結んでいけば、結果的に医療やセルフメディケーションへ大きく貢献していくことにもつながっていくのではないか。