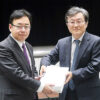昨年来、大麻の所持・販売や不正栽培など、大学生への大麻汚染が社会問題化している。
そうした中で、今月7日には、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学のいわゆる「関関同立」と呼称される関西有力4私立大学が「薬物乱用防止に向けて力を合わせ、今後とも積極的な取り組みを行う」との共同声明を発表した。
薬物乱用防止として、複数大学が共同声明を出すこと自体、異例のこと。大学生の大麻汚染が、国公私立の別なく大学キャンパスにも確実に広がっているのが現状。関関同立のうちの大学からも既に逮捕者が出ていることもあり、「大麻汚染が一大学の問題ではなく、大学間をまたがった事件の可能性もあるため、情報交換を行う場などを設けて連携していく必要がある」(大学関係者)との判断もあったようだ。
今後は来月にも4大学による連絡会を設置し、関係機関の協力を得ながらポスターやリーフレットの作成等の4大学共同のアクションプランを推進していく構えだ。また、薬物に関する学生の意識調査も実施し各種の啓発プログラムも実行。広く社会に向けても薬物乱用防止の諸活動を展開していくという。
大麻などの汚染は大学生だけではなく、中高生などの少年にまで裾野は広がっている。警察庁が先月末に発表した2008年の「少年非行等の概要」によると、大麻取締法違反は227人で、前年比約27%増の状況にある。有職・無職少年で約67%を占めるが、学識別でも中学生2人、高校生49人、大学生16人といずれも増加傾向にあり、大麻汚染の低年齢化が憂慮すべき事態となっている。
現在、国では薬物乱用防止対策の一環として「第3次薬物乱用防止5カ年戦略」の中で、小・中学校、高校の児童・生徒に対する指導・教育の徹底を指示している。これに基づき、各都道府県レベルでも、学校薬剤師等の外部講師による薬物乱用防止教室の開催を促しているところだ。
大麻を含めた薬物乱用防止の啓発教育は低年齢から行うべきだが、実態として汚染が拡大している大学生、高校生は大麻自体を安易に捉えている傾向もあるようで、その認識を改めさせる啓発活動が必要なところだ。
先般、大阪府薬剤師会でも事態を憂慮し「大麻の乱用防止」を強く訴えるポスターを作製し、府内の大学、高校、各種学校に加え、会員薬局への配布を開始。同ポスターでは、大麻の有害性のほか、大麻の所持が取り締まりの対象となることを明記している。
また、行政レベルでは、福岡県が昨年11月に大麻乱用防止に特化した啓発ポスターを作成、県内全ての大学などに配布。さらに九州ダルクの協力を得て、過去に大麻を乱用して依存に陥った人を取材し、その内容をもとに、大麻乱用防止の啓発広告を作成。「細かい作業が苦手になり、仕事や運転のような注意力を要する作業には支障を来してしまう」という元依存者の生の声を、青少年が主な購読層となる雑誌に掲載するなど、積極的な取り組みも行われている。
薬物乱用は近年、覚せい剤検挙者数が減少してきているが、一方でゲートウェイドラッグと呼ばれる大麻、MDMAの検挙者数は逆に増加傾向にある。さらにインターネットの普及で、一般の青少年でも薬物乱用につながる有害情報に簡単にアクセスできる環境にもある。それだけに薬物乱用防止対策には、「啓発」というよりも、危機感をもった「警告」が必要な時代に入った。