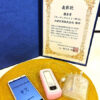医薬品医療機器等法の一部改正で8月に施行となった認定薬局制度だが、本紙の集計では9月29日時点で地域連携薬局が740軒だった。各都道府県は認定状況について滑り出しとしては順調と概ね評価したものの、認定された薬局を見てみると大手調剤薬局に偏り、地域個店薬局の少なさが目立つ。制度がスタートして2カ月だが早くも不安だ。
現場からも認定薬局の現状について心配なデータが出てきている。東京都薬剤師会が都内の会員薬局を対象に実施した調査によると、地域連携薬局の申請を済ませた、もしくは届け出予定のある薬局が2割に満たない。「届け出をしたい気持ちはあるが満たしていない項目がある」が7割を超え、届け出要件を満たすのが困難な現実も浮かび上がっている。
全国で唯一、三桁の認定薬局を持つ東京都のみならず、他の道府県も認定を取得した軒数の伸び悩みに直面する可能性がある。このままだと届け出が未だに少なく成功したとは言い難い健康サポート薬局の二の舞を踏むことになる。地域包括ケアシステムの構築に向け、都道府県の医療政策に認定薬局を活用していく構想にも狂いが生じる。
問題視されたのが医療機関への情報提供実績と無菌調剤への対応だ。情報提供実績については都薬の調査でも「医療機関に対する情報提供実績月平均30回以上」の要件を満たしているのはわずか14%に過ぎなかった。平均30回以上の情報提供を実施できなかった薬局の平均数は「10回未満」が74%だった。
確かに医療機関との情報共有の面では、薬局の努力が足りていない部分はある。しかし、地域住民が安心して医療を受けられる体制を目指していくために創設された認定薬局制度の趣旨を踏まえると、地域の薬局が医療機関に対して月平均30回以上の情報提供を行うという基準が果たして適正な要件なのか。
国も認定要件について、「情報提供回数ありきで認定を取るべきでない」との考え方を発信している。地域の状況によって薬局に求められる機能は異なる。薬局から医療機関にどれだけ役立つ情報を提供しているのか、医療機関と薬局が必要なときにいつでも連携できる体制があるのかなど地域連携薬局に必要な要件とは何かを改めて見直す必要があるだろう。
専門医療機関連携薬局の認定状況はより深刻であり、およそ半数の道県で認定薬局がゼロとなっている。地域連携薬局の認定を取った薬局が専門医療機関連携薬局を目指すと考えられ、地域連携薬局が停滞すれば地域の癌対策にも影響が及ぶ。かかりつけ薬局・薬剤師の推進に向け、要となる認定薬局を社会に根づかせるためにも軌道修正は早い方がいい。