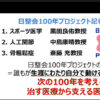2020年12月に判明した小林化工の後発品製造不正から間もなく3年が経過し、後発品の供給をめぐっては現在もなお、欠品や出荷調整が続くなど視界不良の状況だ。厚生労働省の検討会は、後発品の安定供給実現に向けた産業構造改革を実現するための中間取りまとめを公表し、薬事・薬価に関する事項について提言を行った。厚労省は、供給問題の課題解決に向けた第一歩と位置づけているが、1万品目以上の多種多様な品目を少量で生産する後発品産業の構造改革は容易ではない。
中間取りまとめでは、少量多品種構造の解消に向け、新規収載品目の絞り込みや既収載品目の統合、供給停止・薬価削除プロセスの簡略化などを対応の方向性に挙げた。新規収載品目の絞り込みでは、安定供給に貢献しない企業の参入を抑制するため、企業に安定供給に関する責任者の指定を求めると共に、継続的に供給実績を報告させる仕組みを検討すべきと提言した。
後発品の製造販売承認をめぐっては、先発品との生物学的同等性試験や安定性試験での結果をもとに審査が行われ、問題がなければ承認、新規収載されるプロセスが取られているが、製造能力を要件に課していなかった。その結果、共同開発の解禁によって参入障壁が下がり、新規参入企業の増加を招いた。
製造能力や安定供給に関する事項を要件化するとしても、安定供給責任者の指定や継続的な供給実績の報告を要件とする仕組みだけで、安定供給に貢献しない企業の参入を食い止める有効打になるかは疑問が残る。共同開発品の考え方も含めた対応策が必要だろう。
既収載品の統合作業は短期決戦で決着が付けられるかが勝負になる。厚労省の検討会では、医薬品の製造方法変更にかかる薬事手続で「一部変更承認」「軽微変更届出」の中間カテゴリとして「中等度変更事項」を試行的に導入することが了承された。新たな薬事手続きの仕組みを利用し、期限を決めて目標となる品目数となるよう企業間の品目統合を進めていくべきだ。
医療上必要性が乏しく市場シェアが低い品目の供給停止・薬価削除も、現行プロセスでは時間を要するため、医療現場への影響や採算性のみを理由とした供給停止に配慮しつつ、簡略化・合理化を図らなければならない。
薬価制度でも安定供給の評価軸を決める必要がある。提言では、企業に安定供給に関する情報公開を促し、安定供給に貢献している企業には高い評価を与え、逆に基準を満たしていない場合は低評価とするメリハリが付いた薬価制度の導入を促した。
新薬創出等加算に企業要件が設けられているように、後発品にも同様の制度があって然るべきである。品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で生き残れるためには、インセンティブとペナルティの強弱を付けた制度設計が前提となる。