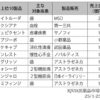病院薬剤師の活躍の場は年々広がっている。チーム医療の一員として多職種と連携する場面が増え、医療人を志す薬学生がやりがいを持って働ける職種になっている。各領域の専門・認定薬剤師制度も充実しており、ジェネラリストとして基盤を固めた上で、その領域の専門家を目指す道もある。ただ、薬剤師数が十分な病院とそうでない病院では、業務内容に差が生じるのも事実。薬剤師不足や偏在の解消、給与等の処遇改善など、業務発展に向けて解決すべき課題は依然として多い。
かつて外来患者の調剤が主軸だった病院薬剤師の業務は、院外処方箋発行によって院内の様々な業務にシフトした。病棟で入院患者に服薬指導するだけでなく、チーム医療の一員となって多職種と連携。問題点の発見や改善策の提案を通じて、患者の薬物療法の個別化に関わる機会が増えた。
薬剤師が救急や手術など院内の各部門に常駐する取り組みも拡大している。外来部門で業務を担うことも増加。その一環で、外来で化学療法を受けるがん患者に対する「薬剤師外来」の業務が、昨年6月の診療報酬改定で「がん薬物療法体制充実加算」として新たに評価された。
同加算は、外来で医師の診察前に薬剤師が患者に面談し、服薬や副作用発現の状況などを聴き取って評価した上で、医師に情報提供や処方提案を行うなど、一連の業務を実施することで算定できる。多忙な医師が、限られた診察時間内で全ての情報を聴き取るのは容易ではない。薬剤師が診察前に関与することで、確実な情報把握や薬学的評価が可能になり、医師の労務負担軽減や医療の質向上につながる。
国は、医師でなくても行える業務は他職種に移管したり、協働したりするタスクシフトやタスクシェアを推進している。これを追い風に、今後も病院薬剤師の業務は拡大していくだろう。
一方、病院就職者が集まりやすい都市部の急性期病院に比べ、地方にある病院や中小病院の多くは依然として薬剤師不足に直面しており、業務を広げたくても限界がある。
病院薬剤師の不足や偏在を招く要因の一つが、若い年代での薬局薬剤師との給料格差だ。病院薬剤師の生涯年収は薬局薬剤師に引けを取らないとされるが、奨学金の返済を抱える若い年代では、初任給の格差が大きく、ドラッグストアや薬局を就職先に選択する傾向が強い。
病院の経営環境が悪化する中、多職種が働く病院で、薬剤師の給料だけを優先的に引き上げてもらうのは難しい。まずは国の補助や診療報酬による全体的な処遇改善を求めるのが現実的だ。
各都道府県で昨年度から始まった第8次医療計画の多くには、薬剤師確保策が盛り込まれた。病院を含む地域の就職候補先の特徴を示して薬学生とのマッチングを促したり、地域全体で薬剤師を育成する基盤作りをしたり、基幹病院から地方病院へ薬剤師を出向させたりする取り組みで、その効果にも期待したい。
日本病院薬剤師会は今年10月に2035年までのミッション・ビジョンを発表。目指す方向性の一つとして、病棟薬剤業務実施加算の算定施設割合50%以上の実現を掲げた。
今年8月時点で同加算1の算定を届け出ている病院の割合は全体の26.2%。400床以上の大病院の届出率は約7割と高いが、全病院の71%を占める200床未満の病院では届出率が19%と低い。今後、算定要件の緩和などで全体の底上げをどう図るのかが大きな課題だ。