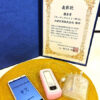セルフMなど積極的に採用し差別化
明治薬科大学(東京都清瀬市)は、2007年に薬剤師認定制度認証機構の認定薬剤師研修制度のプロバイダーとなり、同年4月1日から初回の生涯学習講座をスタートさせた。最近は、厚生労働省が「健康サポート薬局」の普及に乗り出したことを踏まえ、セルフメディケーションなどのテーマを積極的に採用。講義には、座学だけではなく、ロールプレイや小グループディスカッション(SGI)といった参加型のメニューを取り入れ、特色ある取り組みを行っている。
同大学は当初、「現場の薬局薬剤師をサポートする」という目標を掲げ、プライマリ・ケアや漢方、法規、服薬支援などのテーマを取り上げ、講座を提供していたが、最近では一般用医薬品を含むセルフメディケーションや緩和医療などのテーマも積極的に取り入れるようになった。
16年度診療報酬改定で「かかりつけ薬剤師指導料」が導入されたことなどを踏まえ、厚生労働省が示す「かかりつけ薬局の機能」、さらには一般薬・衛生材料の提供や、健康相談応需などを通して病気の予防や健康づくりに貢献する「健康サポート薬局」の実現に向けての対応だ。

菅野氏
明治薬科大学薬学教育研究センター地域医療学准教授の菅野敦之氏は、「セルフメディケーションと一般薬はこれから地域で活躍する薬局・薬剤師を考える上で柱になるテーマ。講座を充実させてきた」と話す。
今年度の講座で代表的なのが「かかりつけ薬剤師と健康サポート薬局の実現」と「薬局におけるOTC医薬品の相談販売」だ。
在宅を視野に入れた講座では、緩和ケアだけでなく寝たきりの高齢者を想定し、ベッドに横になった状態での服薬補助などを体験したり、薬局で簡単にできる健康チェック機器(自己穿刺血液検査、骨密度測定、ストレスチェック、脳年齢測定など)を実際に操作しながら、各測定機器の特徴を理解することで、健康相談応需に必要なスキルを身につけることができる。
OTC薬の相談販売では、医薬品販売制度や、OTC医薬品の添付文書の読み方などを学ぶほか、頭や胃の痛みを訴えてきた顧客に対するOTC薬の相談販売プロトコールを理解した上で、少人数のグループに分かれ、実際にどういう判断に基づいて医薬品を選んだかなどをロールプレイ形式で学ぶメニューなども用意している。
菅野氏は、「どうしても座学だけだと頭でっかちになってしまう。実利的なメニューも入れていかないと、いろいろな場面で対応できない」と話す。
根強い人気を誇る「漢方・鍼灸」の講座は、集合研修講義をビデオ収録し、e-Learning講座としてオンデマンド配信するなど、工夫を凝らしている。また、受講者の負担を考慮して、1日単位での参加を可能にするなどして柔軟性を持たせている。
ただ、多くの大学が、今年4月の診療報酬改定や、国が進める政策を踏まえた生涯学習のプログラムを構築しており、「どうしても似たり寄ったりになりがち」だという。そのため、「今後も薬局が差別化を図っていく上で、身につけておかなければならない内容を積極的に取り上げていきたい」と話す。
具体的には、「国の政策として、スイッチOTC薬は、これから増えていくだろう」とし、「薬剤師はそれに対応できる能力をもっと身につけていかなければならない」と強調。
菅野氏は、「類似テーマの氾濫になるかもしれないが、その中で独自色を可能な限り出していければと考えている」と語った。
明治薬科大学・生涯学習講座
http://www.my-pharm.ac.jp/lifelong/index.html