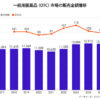サプリの専門家を育成

「NR・サプリメントアドバイザー」のロゴマーク
健康への関心の高まりを背景に、様々な健康食品や保健機能食品、サプリメントが市場に登場しているが、その一方で現代は様々な情報が溢れており、「何を選べばいいのか」「誰に相談すればいいのか」と迷っている人は多い。日本臨床栄養協会(多田紀夫理事長)では、消費者が適切かつ安全に保健機能食品やサプリメントを選択・利用できるよう専門的な観点から個人個人の栄養状態を評価し、適切にアドバイスできる「NR・サプリメントアドバイザー」の育成・認定を行っており、薬剤師を含めたサプリメントに関わる多くの人々が同資格を取得し、修得した専門的知識と技能を幅広い職域で発揮している。
サプリメントは食品の機能を強調したものであり、医薬品と食品の性格を兼ね備えるものと言える。そのため、消費者が適切かつ安全に保健機能食品を摂取するためには、正しい栄養学が消費者に理解されることが望まれる。厚生労働省も2002年2月に「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方について」の通知を発表し、保健機能食品等に関する消費者の指導・教育を目指したアドバイザー養成の重要性を指摘してきた。
同協会は、長年にわたり国民への栄養の啓発を目標に活動しており、医師・栄養士・薬剤師をはじめとした医療専門職種が中心となって消費者を啓発する必要性に鑑み、いち早く日本サプリメントアドバイザー認定機構を設立。その後、12年4月からは国立健康・栄養研究所養成の栄養情報担当者(NR)事業が同協会に移管統合され、新たな統合資格「NR・サプリメントアドバイザー」となり、今日に至っている。
同協会ではNR・サプリメントアドバイザーの質の確保および向上を図るため、認定試験制度と更新制度により認定を行っている。認定試験の受験資格は、まず同協会に入会し、研修単位(40単位)を取得することが必要。
単位取得は、インターネットによる通信教育の受講または学術大会の参加が必要。認定試験は年1回(今年は12月4日の予定)で、合格すると認定証・認定カードが授与され、資格の更新は5年ごとに実施している。
通信講座の主な受講科目は、基礎の生理学・生化学、人間栄養学、生活習慣病概論、臨床栄養と臨床検査、身体活動と栄養、食品安全衛生学、健康食品、臨床栄養学、食品機能の科学的根拠、行動科学とカウンセリング、国内外の関連法規など。講師はいずれも同協会専任で、各分野の第一人者が担当している。
NR・サプリメントアドバイザーは、薬剤師を含めた多くの医療関係職種の人たちが認定を取得して、薬局・ドラッグストア等の小売店舗、通販会社、保健機能食品等を製造・販売する企業のお客様相談室、保健所や保健センター、病院・診療所等の保健医療機関、消費者センター等の消費者相談機関や、地域における食生活改善活動の場などの幅広い職域で、その役割と責務を認識して活動している。
同協会ではNR・サプリメントアドバイザー資格取得者を対象に、知識と経験を生かして広く一般の人に栄養やサプリメントについて啓発を促すことを目的に「サポーター登録」を設けている。登録者には協会主催または外部団体が主催するセミナー等での講師や、協会主催イベントでのサプリメント相談などを案内しているが、「資格を生かす場所として多くの人が登録しており、現在では月1件ペースでの講師派遣がある。特に薬剤師の資格者には、健康食品とサプリメントをめぐる依頼が目につく」(同協会事務局)とのこと。
また、最近では学校会員も増えており、薬系の大学も新規会員となるケースもある。そこで「学生会員登録が顕著に増えていることから、正会員の中に通信教育受講料を10分の1の価格で受講できる学生割引も開始した」という。
日本臨床栄養協会
NR・サプリメントアドバイザー
http://www.jcna.jp/