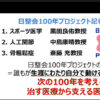リアルワールドデータ(RWD)は、医療の臨床現場や日常生活で得られる実世界の医療・健康情報を指す言葉です。従来の臨床試験(RCT)など人工的に管理された環境下で得られるデータとは異なり、RWDは日常診療や介護、健康管理の場で生じる多種多様なデータを包含します。近年、高齢化社会に伴う医療費の適正化、医療の質向上、新薬開発の効率化などを目的として、このRWDに大きな注目が集まっています。本記事では、RWDの基本的な定義から、関連するリアルワールドエビデンス(RWE)との関係、日本の法制度(次世代医療基盤法)の概要、医薬品開発や市販後調査、医療の質改善、希少疾患対策への活用事例、そしてプライバシー保護やセキュリティ対策まで、最新動向を交えながら分かりやすく解説します。
ポイント①:RWDは「実世界」の医療データ
RWDとは、レセプトや電子カルテ、健康アプリなど現実の診療・生活で得られるすべての医療関連データを指します。
ポイント②:RWDから生まれるRWE
RWDを解析して得られた科学的根拠がリアルワールドエビデンス(RWE)です。政策立案や新薬評価に活用されます。
ポイント③:RWD活用の広がり
RWDは新薬開発、市販後安全対策、医療質改善、難病研究など多様な領域で活用が進み、2025年時点で重要性が増しています。
リアルワールドデータ(RWD)の定義と特徴
リアルワールドデータ(RWD)とは、実際の診療や日常生活の中で収集される医療・健康に関するデータの総称です。言い換えると、病院や診療所、薬局、介護施設、健診センターなどから日々生じる患者さんの診療情報や、個人が使う健康管理アプリ・ウェアラブルデバイスから得られる生活習慣データなど、現実世界(リアルワールド)で発生するあらゆるデータが含まれます。
典型的なRWDの例として、以下のようなものがあります(※括弧内はデータの具体例):
- 診療記録データ(電子カルテ):病院での診療内容、処方、検査結果、画像所見、既往歴など。
- 診療報酬明細書データ(レセプト):医療保険の請求情報(診療行為や使用薬剤、医療費など)。
- DPCデータ:入院診療の包括支払い制度に基づくデータ(診断名、手術・処置内容、入院期間など)。
- 患者レジストリ:特定疾患の患者を登録し追跡したデータベース(治療経過や転帰など)。
- 健診・検診データ:健康診断の結果データ(身長体重、血液検査値、画像検査所見など)。
- 患者報告アウトカム(PRO):患者自身が報告する症状や生活の質に関する情報。
- パーソナルヘルスレコード(PHR)/ウェアラブルデータ:個人がスマートフォンアプリやウェアラブルで管理する健康活動量、バイタルサイン(心拍数、血圧、血糖、睡眠パターン等)。
このように、RWDには医療機関由来のデータ(電子カルテ、レセプト、DPC、検査データなど)から生活者由来のデータ(PHR、スマホアプリ、ウェアラブル等)まで幅広いソースが含まれます。いわば「医療ビッグデータ」の中核がRWDであり、現場の実態を反映したデータである点が大きな特徴です。
比較:ランダム化比較試験(RCT)データとの違い
RWDは実臨床下で日常的に集められるため、患者背景や治療法が多様でデータ形式も標準化されていないことがあります。一方、ランダム化比較試験(RCT)由来のデータは、選択基準で限定された患者に対し厳密なプロトコルで収集されるため高品質ですが、現実の患者全体を必ずしも代表しない可能性があります。両者は相補的な関係にあり、RWDはRCTでは捉えきれない「現場の実態」や長期転帰を補完する役割を果たします。
リアルワールドエビデンス(RWE)との関係
リアルワールドエビデンス(RWE)とは、上記のRWDを適切な手法で解析し、そこから得られた科学的根拠(エビデンス)のことを指します。すなわち、RWDという素材から生み出された「知見」がRWEです。RWDが単なるデータの集合体であるのに対し、RWEは統計解析や研究デザインによって信頼性を担保された情報であり、臨床・行政上の意思決定に資するものとなります。
例えば、電子カルテやレセプトから取得した何千人もの患者データ(RWD)を解析し、ある治療の実地での有効性や副作用発生率を明らかにした結果(RWE)は、新しい治療ガイドラインの作成や医薬品の承認可否判断などに活用されます。「エビデンス創出のゴールデンスタンダード」は従来RCTでしたが、その補強エビデンスとしてRWD由来のRWE活用が近年拡大しています。
補足: 国際的にもRWD/RWEの明確な定義はまだ調整中ですが、一般にはFDA(米国食品医薬品局)の定義などが参照されています。FDAはRWDを「患者の健康状態および日常的に収集される医療提供に関連するデータ」、RWEを「RWDの分析から得られる医療製品の使用および効果・リスクに関する臨床的エビデンス」と定義しています。欧州EMAもほぼ同様の定義を採用しています。
次世代医療基盤法とは
日本では2018年に「次世代医療基盤法(正式名称:医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)」が施行され、RWD利活用を促進するための制度基盤が整えられました。この法律の狙いは、全国の医療機関等から個人の医療情報を匿名加工した上で大規模に集約し、研究開発に役立てる仕組みを作ることにあります。それまで個人情報保護の観点から医療データの第三者提供には患者の事前同意取得が必要でしたが、同法では個人情報保護法の特例として、一定の条件下で同意不要でのデータ提供を可能にしました。
具体的な仕組みは以下の通りです:
- 認定匿名加工医療情報作成事業者(認定事業者)と呼ばれる国の認定を受けた民間事業者が中核となります。認定事業者は全国の協力医療機関や自治体から診療情報を収集し、氏名や住所など個人を特定できる情報を削除・変換する匿名加工処理を厳格な基準で施した上で、研究利用者(大学や企業の研究者など)にデータ提供します。
- 医療機関側は患者への事前の明確な同意取得は不要ですが、情報提供の事実を通知し、患者が希望すれば提供停止の申し出ができるようになっています。このため病院の事務的負担を大幅に軽減しつつ、患者の権利にも配慮した仕組みといえます。
- 提供される情報は全て匿名化されており、個人が特定できない状態が担保されています。従来はデータ提供ごとに倫理委員会審査などが必要でしたが、この枠組みを通じて迅速かつ継続的なビッグデータ活用が可能になりました。
データベースの特徴として、次世代医療基盤法に基づき構築される医療情報データベースには次の利点があります:
- 多様なデータの名寄せ統合:複数の病院・健保組合・自治体等から集まった診療記録、検査結果、健診情報などを個人単位でひも付けて統合可能(名寄せ)。これにより、ある患者さんの複数医療機関にまたがる受診情報をまとめて解析できる。
- リッチな臨床情報:診療報酬明細だけでなく詳細な検査値や画像所見、処方内容など質の高い臨床データを蓄積。実際に検査結果まで含む豊富な情報が得られます。
- 厳格な匿名化によるプライバシー確保:認定事業者が高度な匿名加工を実施し、特異な数値や希少疾患名などからも個人が特定されないよう配慮。プライバシーリスクに配慮しつつ大規模データ活用を両立しています。
現状の進捗: 現在、この枠組みに基づく認定事業者は3社が指定されており、約127の医療機関・自治体がデータ提供に協力しています。約400万人分の患者データが既に匿名化されて蓄積されており、研究利用に供されています。研究者にとっては自機関の倫理審査を経ることなく迅速にデータにアクセスできるメリットがあり、産官学連携でのデータ駆動型研究が動き出しています。
- 約400万人(患者データ):次世代医療基盤法の下で匿名化・集積されたデータ件数。
- 127(協力医療機関等):データ提供に参加している病院・自治体等の数。
- 3(認定事業者数):匿名加工医療情報の作成・提供を行う国認定事業者(民間企業)。
2024年の法改正:施行から数年が経ち、2024年4月に次世代医療基盤法が改正されました。改正のポイントは大きく2つあります。
- 一つは、新たに「仮名加工医療情報」の活用が可能になったことです。従来の匿名加工では、他のデータと照合しても個人が特定できないよう、極端な検査値を丸めたり希少疾患名を伏せるなどかなり厳格な加工を行う必要がありました。その結果、元データから内容が変質して研究に使いづらい面があったため、改正後は一定の個人識別子を仮名(コード)に置き換える加工に留め、必要に応じ他の情報との照合で個人を特定しない限り識別できない形でデータ提供することが認められました。これにより、データの有用性を保ちつつ安全性を確保するバランスが図られています。
- 二つ目は、公的データベースとの連結が可能になったことです。これまで次世代医療基盤法に基づくデータベースは、国のナショナルデータベース(NDB;国民健康保険診療報酬データベース)など公的に蓄積されたビッグデータと統合ができない制約がありました。改正により、この連携が解禁され、既存のNDBや介護DB等と名寄せしたより大規模かつ包括的なデータ解析基盤の構築が可能になります。これによって、日本全体の医療データを横断的に活用できる「データ連携基盤」が一層強化され、創薬や公衆衛生研究への貢献が期待されています。
以上のように、日本では法律・制度面でRWD利活用の環境整備が急速に進んでいると言えます。次章以降では、このRWDが具体的にどのように医薬品開発や医療の現場で役立っているのか、最新の動向を見ていきましょう。
新薬開発の効率化
製薬企業にとって、医薬品の研究開発プロセスは莫大な時間と費用を要します。そこでリアルワールドデータ(RWD)を新薬開発に活用することで、開発の効率化・高度化を図る試みが活発化しています。RWDは、創薬の初期段階から承認申請・市販後まで医薬品ライフサイクル全体で役立つポテンシャルがあります。
- 開発初期のシーズ探索・疾患研究:RWDを解析することで、疾患の患者数や自然経過の解明、アンメットメディカルニーズ(未充足の医療ニーズ)の特定に役立ちます。例えば大規模クレームデータや電子カルテを分析すれば、特定疾患の患者像(年齢層、合併症、既存治療パターンなど)を深く理解でき、新薬のターゲットや効果指標の設定に有用です。またバイオマーカー探索にも、実患者データの解析結果がヒントを与えるケースがあります。
- 臨床試験の計画・実施:治験(臨床試験)の段階でも、RWDは様々な形で貢献します。被験者候補のスクリーニングや治験実施施設の選定にRWDを使えば、より迅速かつ適切なリクルートが可能です。特に患者数の少ない疾患では、あらかじめRWDから患者分布を把握することで効率よく治験組入を進められます。また、倫理的・実務的理由でプラセボ対照群を設定しにくい場合に、RWDから抽出した外部対照群を用いるアプローチも注目されています。例えば希少疾患の治験では、既存の患者レジストリデータから類似背景の未治療患者をマッチングし対照群とすることで、単一の治験でも十分な有効性エビデンスを構築できた事例があります。これは従来なら多数の症例を集めるのが難しかった開発を可能にし、開発期間短縮にもつながる画期的手法です。
- 承認申請・審査:新薬の承認申請資料にRWD由来の知見(RWE)を盛り込むケースも増えてきました。海外では、米FDAが21世紀治療法(Cures Act)に基づきRWEを適応拡大や市販後要求事項に活用する枠組み整備を進めており、実際にRWDを有効性の裏付け証拠として承認審査に供する例が出ています。前述の希少疾患治療薬の承認では、単一のRCT結果に加えRWD解析から得た確証的エビデンスが決め手となりました。日本でも2018年のGPSP省令改正により製造販売後調査でのRWD活用が認められ、将来的に承認申請時の有効性データとしてRWDを受け入れるための議論が進んでいます。現状、日本の審査当局(PMDA)は明確なガイドラインは出していないものの、企業やアカデミアとの「対面助言」枠組みを設けてケースバイケースでRWD活用の相談に応じており、数件ながら外部対照としてRWDを用いた承認例も出始めています。
こうしたRWD活用により、開発スピードの向上(治験期間の短縮、失敗リスク低減)、開発コストの削減(不要な試験の回避、対象患者の最適化)といったメリットが期待できます。また従来のRCTでは捕捉困難だった多様な患者集団でのデータを得られるため、より実臨床に即した評価が可能になり、新薬の価値証明(Value Demonstration)にも寄与します。製薬企業各社はRWD利活用をデジタル戦略の柱に位置づけており、日米欧の規制当局も連携して評価基準の国際調和を検討するなど(ICHで2024年にRWD/RWEの用語や評価原則のガイダンス策定予定)、いよいよRWDが新薬開発のゲームチェンジャーになりつつあります。
市販後調査の迅速化・高度化
新薬が承認・発売された後の製造販売後調査(市販後調査)や安全性監視にも、リアルワールドデータ(RWD)の活用が大きな威力を発揮しています。発売後の迅速な問題検知と実地での効果検証という二つの面で、RWDは伝統的な手法を補完・強化しています。
- 副作用の早期検知と安全対策:医薬品の安全性監視(ファーマコビジランス)において、従来は医療者からの自発的報告や製薬企業のMR活動による情報収集が中心でした。RWDの利活用により、大規模データベースを用いた副作用シグナル検出が可能になっています。例えば、数百万人規模のレセプトや電子カルテデータを解析し、特定薬剤使用患者の有害事象発生率を対照群と比較することで、まれな副作用やリスク因子を統計的に抽出できます。日本ではPMDAが医療情報データベース「MID-NET®」を構築し、10以上の病院から収集した電子カルテ情報等を用いて市販後安全対策に活用しています。これにより、従来数年かかった安全性評価がリアルタイムに近い形で行えるようになり、必要な措置を迅速に講じることが可能となっています。
- 実臨床下での有効性・費用対効果検証:新薬が実際の臨床現場で期待通りの成果を上げているか、あるいは長期的な有効性・QOL改善効果があるか、といったリアルワールドでの効果検証にもRWDが活躍します。製造販売後臨床試験や観察研究の一環として、製薬企業は広範な患者データ解析を行っています。例えば治療ガイドラインに沿った投与が行われているか、患者背景ごとの効果・副作用に差はないか、他剤との併用状況はどうか――こうした知見は、RWD解析により得られ、適応拡大の検討や適正使用の推進に役立てられます。また費用対効果分析にもRWDは不可欠です。健保のレセプトデータから医療経済評価を行い、医薬品の価値をエビデンスベースで示す取り組みも盛んです。特に高額な画期的新薬について、実地医療でのアウトカムを踏まえて費用対効果を評価することは、保険償還の観点からも重要になっています。
- 条件付き承認の事後検証:近年、重篤かつ治療法の無い疾患に対し限られた試験データで早期承認し、承認後に追加データ収集する「条件付き早期承認制度」が導入されています。こうした承認後のエビデンス補強にもRWDが活用されています。上市後に患者登録を行い、一定期間の有効性・安全性データを収集することで、承認時には不明だった事項を検証します。これも広義の市販後調査であり、RWDと臨床試験データを組み合わせるハイブリッドなアプローチと言えます。
以上のように、RWDは市販後の調査・監視業務を効率化しつつ高度化しています。実際、近年は製造販売後調査を伝統的な症例集積型からデータベース研究型へ移行する動きが顕著で、データベース研究は現在では標準的な手法となりつつあります。この流れに合わせて、医薬品リスク管理計画(RMP)においてもデータベースを用いた調査が計画に組み込まれる事例が増えています。
医療の質向上と病院運営の健全化
リアルワールドデータの利活用は、医薬品開発だけでなく医療提供体制そのものの質改善や医療機関の経営管理にも恩恵をもたらします。
医療機関や行政が持つ大量の診療データを分析することで、これまで見えにくかった医療サービスの実態や課題が浮き彫りになります。例えば:
- 医療の質指標のモニタリング:診療データから、治療成績や合併症発生率、再入院率、患者満足度(PRO活用)などの指標を継続的に追跡できます。これにより、自院の医療の質を客観的に評価し、ガイドラインから逸脱した治療パターンや地域間でのアウトカム格差などを発見できます。得られた知見をフィードバックして院内プロトコルの見直しやスタッフ教育に活かすことで、エビデンスに基づく医療の質改善サイクルが実現します。
- 医療の標準化と均てん化:RWD分析により、同じ疾患でも施設ごとに診療内容や結果に差があることが明らかになる場合があります。この情報を共有することで、診療の標準化(ベストプラクティスの横展開)を促し、どの患者も質の高い医療を受けられるよう支援できます。また、地域医療構想の策定や医療資源の適正配置にも、データに基づいた議論が可能となります。
- 病院経営の健全化(効率化):RWD活用は経営面にも有用です。診療報酬データやDPCデータを解析すれば、診療単価や在院日数、手術件数、ベッド稼働率といった指標から、自院の経営状態を客観視できます。収益性の高い診療領域や逆に持ち出しになっている領域を把握し、経営改善計画に反映できます。さらにAIを用いて患者数の予測や人員配置の最適化を行う試みもあり、データドリブンな経営判断ができる病院は持続的に発展しやすいと言えます。
実例として、国内のある医療データ分析事例では、診療データを用いた分析により特定の治療プロセスの非効率箇所を特定し、業務フローを改善した結果、患者の待ち時間短縮と医療従事者の負担軽減を同時に達成したケースがあります(※具体的な病院名は非公開)。また自治体レベルでもレセプト情報や健診データを突合し住民の疾病動向を可視化することで、効果的な介入(特定保健指導や重症化予防プログラムの展開)につなげている例があります。
このように、RWDの活用は「質の高い医療を効率良く提供する」ことを後押しする武器となります。実際、「医療機関や自治体がRWDを活用することで、医療の質向上や病院経営の健全化に寄与する」という指摘もあり、政府もデータヘルス改革の一環として医療データの集約・活用政策を推進しています。今後は診療現場で得られるデータを、個々の医療機関だけでなく地域・国家単位で活かし、エビデンスに基づく医療政策や病院運営がますます重要になるでしょう。
希少疾患・難病対策への貢献
希少疾患や難病の領域では、患者数が限られるために従来からデータ不足が大きな課題でした。リアルワールドデータ(RWD)の活用は、こうした疾患分野の研究開発に新たな光を当てています。
- 自然歴データの活用:希少疾患では患者登録(レジストリ)を行い、治療介入がない状態での疾患の自然経過(ナチュラルヒストリー)を追跡したデータが貴重です。RWDとして蓄積された自然歴データは、新薬の効果を評価する際の比較対象(外部対照群)として利用できます。前述の例にあったフリードライヒ失調症の治療薬承認では、レジストリから得た未治療患者の長期症状進行データと治験参加患者の経過を比較し、有意な悪化抑制効果を示すことで承認につながりました。このようにRCTを補完・代替するエビデンスとしてRWDが活躍することで、希少疾患でもエビデンスに基づく承認が可能となります。
- 幅広いデータ収集による知見蓄積:難病では症例報告レベルの知見が多く、体系的なデータが不足しがちです。RWDの文脈では、電子カルテやNDBから該当疾患患者を漏れなく抽出し、患者背景・治療状況・転帰を分析する取り組みが可能です。例えばある難病の全患者を医療費助成のデータから把握し、それら患者のレセプトを縦断解析することで、合併症の発現パターンや平均余命などを統計的に明らかにするといった研究が行われています(仮想例)。このようなエビデンスの集積は、新規治療法の開発だけでなく、現在利用可能な治療の最適化(どのタイミングで治療介入すべきか等)にも寄与します。
- 承認後のデータ活用:希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)として開発・承認された薬剤について、承認後に患者レジストリやデータベースを用いて実地での有効性・安全性を追跡する動きも盛んです。RWDにより蓄積されたエビデンスが、適応拡大や投与法改良など次の展開に繋がることも期待されます。
国際的にも、希少疾患領域はRWD活用の恩恵が大きい分野として位置づけられています。欧州EMAでは希少疾患や従来経路での開発が難しい医薬品に対してRWD/RWEの活用が今後増加すると予想されています。米国FDAも、倫理的にRCTが困難な場合のRWE活用に前向きな姿勢を示しています。日本でも難病対策研究やナショナルセンター主導のレジストリ整備が進んでおり、次世代医療基盤法のデータベース等と連携しながら、希少疾患の治療法開発を加速させることが期待されます。
リアルワールドデータ活用における課題とプライバシー・セキュリティ対策
RWDの利活用を推進するにあたり、データの品質確保や個人情報の保護といった課題にもしっかり向き合う必要があります。他分野に比べ医療データはセンシティブであり、患者さんのプライバシーを守りながら有益な情報を引き出すバランスが重要です。最後に、RWD活用を巡る主な課題と、それに対する対策の例を整理します。
| 課題 | 主な対策・取り組み |
|---|---|
|
データ品質・標準化 (生データの不備・ばらつき) |
データクレンジング(欠損値補完や誤記修正)やフォーマットの統一を実施。 また標準用語・コード体系(疾病分類、医薬品コード等)の適用により、異なる施設間でも整合性ある分析ができるようにする。 |
|
データバイアス (偏ったサンプル) |
データセット内の代表性を評価し、解析時に調整を行う。 例:年齢や性別構成のウェイト付け、傾向スコアマッチングの活用。必要に応じ母集団を補う追加データ収集も検討。 |
|
プライバシー保護 (個人情報の漏えいリスク) |
法制度に基づく匿名加工や仮名加工の徹底。 データ提供時は氏名等を完全削除し、住所・日付も加工。研究者側でも不要な個人情報は保持しないルール整備。 |
|
セキュリティ対策 (不正アクセス・サイバー攻撃) |
医療データを扱うサーバやクラウド環境における厳重なアクセス制限・暗号化。 大学病院等では「極めて高いセキュリティレベル」でデータを管理・解析する体制を構築。定期的な監査や監視システムで漏えいを防止。 |
|
倫理・法的側面 (AI診断への責任問題等) |
倫理指針やガイドラインの整備。 AIを用いる際の説明責任や意思決定プロセスの透明性確保。 |
|
倫理・法的側面 (AI診断への責任問題等) |
倫理指針やガイドラインの整備。 AIを用いる際の説明責任や意思決定プロセスの透明性確保。 万一の事故時の開発者・医療機関・利用者の責任分界を法的に明確化。 |
上記のように、データ基盤の整備とガバナンス強化によって課題に対処しつつ、RWD利活用の潜在力を最大化していく取り組みが進められています。例えば京都大学では、「日常診療での臨床情報(RWD)を極めて高いセキュリティレベルで管理・統合・解析」する研究講座を設置し、医療の最適化や医療実態の可視化に取り組んでいます。また欧州では、各国の医療データを中央集約せず解析プログラムだけを送り結果を集めるフェデレーテッド(分散型)解析ネットワークを構築することで、データを手元から出さずに広域分析を可能にする試みも行われています。
日本においても、標準化・匿名化・セキュリティ確保の仕組みを整えながら、行政・医療機関・企業・市民が連携してRWDを社会的資源として活用していくことが求められています。これは単に法令遵守というだけでなく、データ利活用への国民の信頼を得てデータ提供に協力してもらうためにも不可欠です。プライバシーを守りつつビッグデータの力を引き出す技術(匿名加工技術、セキュアコンピュテーション等)や制度の発展が、日本の医療データ活用の未来を左右すると言っても過言ではありません。
むすび:RWDが拓く医療の未来
リアルワールドデータ(RWD)は医療の現場から生まれる“生の情報”であり、その適切な活用によって私たちはこれまでにない知見と価値を引き出すことができます。2025年現在、法律の整備や技術の進歩によりRWD利活用の環境は飛躍的に向上し、実際に新薬承認や医療改善に結びつく事例も増えてきました。下記のタイムラインに示すように、ここ数年でRWDを取り巻く状況は大きく動いています。
- 2018年:次世代医療基盤法 施行 – 医療情報の匿名加工・集約を可能にする法律が施行。日本でRWDを大規模活用する基盤がスタート。
- 2024年:同法 改正施行 – 仮名加工情報の利用やNDBとのデータ連結が解禁。より使いやすい形で医療ビッグデータを活用可能に。
- 2025年:RWD承認事例の増加 – 希少疾患を中心にRWDを活用した医薬品承認が着実に増加。RWD/RWEが規制判断の一角を担う時代に。
RWDの積極的な利活用によって、医療イノベーションの加速と日常診療の質向上が両立できる未来が見えてきています。医薬品開発ではデータ駆動型の意思決定が進み、新薬創出までの道のりが短縮されるかもしれません。医療現場では、蓄積された実臨床データに基づいて患者一人ひとりに最適化された医療(Precision Medicine)や、予防・健康増進へのフィードバックが実現するでしょう。
もっとも、RWD活用の本質は「人々の健康と生活をより良くすること」にあります。データはあくまで手段であり、その先にエビデンスに基づいた意思決定やシステム改革があります。すべてのステークホルダー(患者、医療者、研究者、行政、企業)が協力し、データから得られる知見を社会全体の利益に還元していくことが大切です。
幸い、日本には世界有数の医療保険データや臨床データ資源が存在し、それを守り活かす法制度も整いつつあります。これらを適切に管理・活用することで、「データ駆動型医療」が切り拓かれていくでしょう。リアルワールドデータの可能性を最大限に引き出しつつ、安全・安心なデータ利活用文化を育てることで、医療・ヘルスケアの未来はより明るいものとなるはずです。
最後に、本記事の内容がRWDの基礎と最新動向を理解する一助となり、読者の皆様が自社や自分のフィールドでデータ活用を検討する際の参考になれば幸いです。
【参考文献】リアルワールドデータ/リアルワールドエビデンスに関する公開情報より作成(日本製薬工業協会、PMDA、厚生労働省、NTTデータ、KPMGジャパン、他)
- 【エーザイ】77%の患者が病期進行せず‐「レケンビ」米RWD調査(2025年10月16日)
- 【日本IBM/神戸医療産業都市推進機構】AIとRWDで臨床開発支援‐新薬開発スピードアップ図る(2024年09月19日)
- 日本を魅力ある治験市場に‐中井医薬品審査課長「RWDで成功事例作る」(2023年09月15日)
- 【PMDA】適合性調査で「異次元」改革‐10月にRWD新事業稼働へ(2023年09月01日)
- 【ICH総会】RWD試験の検討着手‐4件がステップ4到達(2023年06月23日)
- 【ロート製薬/藤田学園】RWD活用促進へ合弁会社‐医療分野で社会実装目指す(2023年05月16日)
- 【中外製薬】RWDで臨床開発効率化‐申請の参考資料に活用(2023年01月24日)
- 【TXPメディカル】RWDで臨床研究支援‐中核病院のデータ活用(2022年12月08日)
- 【SaMDフォーラム】早期承認・仮償還を要望‐上市後RWDで再評価(2022年12月07日)
- 【製薬協委員会調査】RWD利活用、わずか3%‐前年からプロジェクト減(2022年09月12日)
- 【PMDA】後発品初のRWD安全評価‐スタチンで先発品と比較(2022年07月22日)
- 創薬へのRWD活用推進‐中外製薬・志済氏、国に環境整備要望へ(2022年03月22日)
- 【厚労省・22年度医薬概算要求】後発品の信頼確保へ増額‐RWD安全評価で新事業(2021年08月27日)
- 【糖尿病学会】処方薬選択、AIが支援‐RWD活用で糖尿病薬選択(2021年06月08日)
- 【中外製薬】RWDの申請資料活用へ‐石井氏「エコシステム構築が必要」(2020年12月08日)
- 【PMDA運営評議会】RWDの申請資料活用、20年度事業計画に盛る(2020年08月05日)
- 【塩野義製薬】中国保険大手と資本提携‐RWD活用で新創薬モデル(2020年04月06日)
- 【京大/NTT】癌RWD事業で合弁会社‐日本最大級データベースへ(2020年02月07日)
- 【千年カルテプロジェクト】RWD二次利用、秋頃開始へ‐製薬企業の研究利用想定(2020年01月29日)
- 【彩都フォーラム】伯野厚労省研発課長「RWD活用の観察研究推進」‐来年度事業で国が支援へ(2020年01月27日)
- 【名城大、薬経連グループ】薬局の業務支援にRWD‐薬歴をエビデンス創出に活用(2019年10月25日)
- 【ファイザーR&D】治験デザインにRWD活用‐患者の同意取得も電子化(2019年03月14日)
- 【調剤メルフィンに新機能】RWD参考に服薬指導‐副作用自発報告を解析(2018年11月19日)
- 【中外製薬】ゲノムとRWDを統合‐データベースで治験効率化(2018年10月04日)
- RWDで新時代の幕開け‐製薬企業が統括部門創設(2018年06月06日)
- 日本のRWD活用、医療DBの統合解析に課題‐清水・東大特任准教授「海外とは周回遅れ」(2018年05月30日)
- 【クインタイルズIMS】市販後ビジネス、国内で創造‐PMSモニター設置、人材とRWDを融合(2017年10月17日)
- 【日本臨床疫学会】RWD研究の加速が必要‐産官学連携し基盤整備を(2017年10月04日)
- 注目集めるRWDの活用(2017年04月07日)
- 【GSK日本法人】臨床試験の変革に着手‐呼吸器治験でRWD活用(2017年03月03日)
- 【中外製薬】安全性評価にRWD活用‐大箸本部長、科学的にメス「布石打てた」(2016年08月18日)