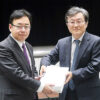会見する学会・中国関係者
日本中医学会が29日に発足した。発足に当たって、設立準備委員長の酒谷薫・日本大学脳神経外科教授は、「漢方薬ばかりでなく、鍼灸や気功などを結合させ、本来の中医学を確立すると共に、日本の先端科学技術を取り入れ、さらに、中国の中医学界などとも交流を深め、日本独自の中医学を確立していきたい」と抱負を語った。
酒谷氏は、中国から導入された中医学は、日本では漢方薬を中心に、東洋医学・日本漢方として発展してきたが、本来の中医学とはいくつか点で異なると指摘。「中医学は弁証論治をもとに総合判断して、漢方薬の使用、鍼灸や按摩、気功などの治療が行われる。日本はこれらの連携が取れていない」との現状認識を示した。
その上で、「欧米では、鍼灸に関する科学論文が、権威ある科学雑誌に掲載されるなど、世界的には、鍼灸などを取り入れた中医学の研究が進められている。こうした差異を考えると、日本の東洋医学発展のためには、中医学を専門とした学会が不可欠」と、中医学会設立の背景を説明した。
学会活動としては、学術集会の開催や学術情報の発信、教育普及活動、国内外の関連団体・期間との交流、特に、中国の中医学界との学術交流を深めていく。
学術活動としてはまず、日本の先端科学技術を用いて、中医学治療のメカニズムの解明に取り組んでいく。日本は光脳機能イメージングや分子イメージングの分野では、世界をリードする研究を行っていることから、これらの先端技術を活用し、中医学治療の脳機能に対する効果や、生体内での分子プロセスなどの解明を行っていく。
さらに、▽中医学と西洋医学を融合させた統合医療の確立▽日本における中医学による理論的臨床的能力の発展向上▽持続可能な研究体制持続のため、産官学連携研究体制の構築▽中医学に関する日中間の国際共同研究の実施--などを目指していく。
酒谷氏はまた、「現在、日本とアジア諸国は“友好”から“友愛”へと、より深い信頼関係を築く時代に入りつつある。日本がアジア各国と協力し、中医学を中心とした統合医療に関する国際共同研究を行うことは、アジアの人々にの健康と平和に大きく寄与すると期待している」とも述べた。
中国では基本的国家施策‐積極的な国際交流を展開
29日には、「現代医療における中医学の役割」をテーマに、設立記念シンポジウムも行われた。シンポジウムには、中国の王笑頻・国家中医薬管理局国際合作司副司長も参加し、中国での中医学施策について説明すると共に、今回の中医学会設立に対して、積極的な交流を進めたいなど、歓迎の姿勢を示した。
王氏は、中医学は中華民族にとって、輝かしい伝統文化を構成する重要な文化財で、また中国の医学技術を特徴づけるものと説明。これまで中国政府は、中医学をはじめとした伝統医学を、文化財としてばかりでなく、重要な産業とも位置づけ、国民経済や社会の発展における重要な役割を持つものとし、基本的国家施策として、支持・保護・活用・発展を図ってきたと話した。
また、中国政府は、世界各国の政府や国際組織との間で、中医学分野の交流と合作の推進を非常に重視。近年、種々の形による中医学の国際的提携を試み、中医学分野における国際的合作プロジェクトを立ち上げたり、各種の中医学関連の国際的交流活動を展開するなど、中医学の近代化と国際化の推進に力を入れていると、その現状を解説した。
さらに、「われわれは世界各国と共に、積極的に伝統医学を発展させる経験を共有し、中医学を統合医療の重要な一部分とし、世界各国の医療保健システムの中に取り入れることを促しており、中医学を含めた伝統医学が21世紀において、ますます大きな役割を果たすことを期待している」とした。