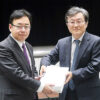大手をはじめとする製薬企業は、海外事業の強化に躍起だ。業績を大きく伸ばすためには、日本より市場が大きく、成長力もある海外市場が有利になるからだ。もちろん、新薬を世界の人々に届けたいという思いもある。
今月、田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併することに合意し、「国際創薬企業」を目指すと表明。4月に完全統合を果たす第一三共は、中期経営計画(中計)を公表。武田薬品をはじめとする上位4社の中計が出揃い、いずれも海外事業の強化、そのために必要な新薬研究開発の強化を打ち出している。株式市場や有識者からも好意的に受け止められている。27日には大日本住友製薬も中計を発表する。
国際競争の土俵に乗ろうと、大型合併の先陣を切ったアステラス、第一三共、大日本住友、田辺三菱など、業界再編が起きているわけだが、忘れてはならないのは新薬の創出だ。それも世界が待望する新薬である。
しかし、研究開発費が世界的に増加傾向にある一方で、承認される新薬の数は減少傾向をたどっている。ゲノムや蛋白質の解析などで創薬技術にパラダイムシフトが起き、創薬まで結びつくに至っていないという事情はあろうが、「新薬メーカー」をうたいながら新薬を出せないのでは、国民・患者からは“看板に偽りあり”と見られかねない。
各社が十分認識している通り、十分な治療法がない「未充足治療領域」は、癌やリウマチなど、まだ数多くある。最近では自殺報道で知られた繊維筋痛症もその一つ。患者の切実な願いに応えたい。 しかし、これまで製薬企業が選択してきた自己完結型の研究開発体制では、限界があることは知られている通りだ。今こそ産学官の連携、特に産学のより強固な連携を築くことが必要だ。その点が日本は弱いと、国内外企業のトップや研究者から指摘されている。
世界的に注目されている分子標的薬、再生医療等のバイオロジクス、こうした先端的な領域であればあるほど、連携の必要性は高い。例えば新薬開発のトレンドにある分子標的薬でも、その下地には疾病メカニズムの研究、患者で特異的に発現している遺伝子や蛋白質などの機能解明、特定の遺伝子や蛋白質の発現を診断や処方決定に生かす技術の開発など、周辺の研究があってこそだ。
先端的研究を進め成果につなげていくためには、製薬企業だけでも、研究者だけでも目的には到達し得ない。大切なのは、世界の人が待ち望む新薬という目的に向かって、共に肩を組むことだ。抗体医薬など先端的な新薬候補の多くを保有しているバイオベンチャーなどとの提携、さらに臨床研究には医療現場、患者の協力も当然必要になる。
連携にスピードを持って対応できる体制づくりも進めなければならない。研究現場からは、分子標的薬の開発と同時に処方選定に用いる診断薬などの開発を行うにしても、「バイオマーカーのバリデーション、診断薬、診断キットの開発は、日本では薬剤開発のPIまでには間に合わないだろう」との声が上がっている。海外企業側からも、日本には研究機関と企業の連携が有効に機能するクラスターが欠けており、その面で優れている中国や韓国など他のアジア諸国から、新薬研究開発で遅れをとりかねないと指摘されている。
国際競争の勝ち残りには、世界的新薬の創出が不可欠だ。業界再編と同時に、官の支援を受けながら産学の連携も急がなければならない。