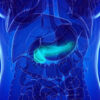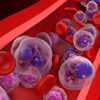関西医科大学総合医療センターの院外処方箋全面発行中止や、滋賀医科大学病院の敷地内薬局誘致の動きが関係者に驚きを持って迎えられている。
この2病院のケースは、少し意味合いが異なる。関西医大の中止理由は、「約16年間処方箋を出してきたが、メリットを十分に感じられなかった」というもので、これは医薬分業の趣旨が十分に浸透しておらず、薬局業務が調剤専門となり、患者がおざなりにされたことにつきるだろう。
滋賀医大の敷地内薬局は、患者の利便性と経営面でのメリットを見込んだものだ。経営環境が厳しい病院などは、経営コンサルタントなどが敷地内薬局の誘致を指南するケースもあるようで、今後、増えてきそうな様相を呈している。
昨年、過去に例のないほどの調剤バッシングを受けて、厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」を策定した。
ビジョンでは、「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へとの副題がつけられており、これに沿う形で、2016年度診療報酬改定で「かかりつけ薬剤師指導料」が新設された。
日本薬剤師会の石井甲一副会長は、敷地内薬局の問題について、「この方向性とは明らかに矛盾している」と不快感を示し、敷地内に薬局を誘致する病院が「安易に増えることがないようにしてもらいたいし、われわれも努力しなければならない」と述べている。
東京都薬剤師会の石垣栄一会長は、国立病院機構災害医療センター(東京都立川市)が病院の敷地内に調剤薬局を誘致しようとする動きがあることに対して、「賛成できかねる」との見解を示している。
確かに、薬局の構造規制の緩和を逆手にとって、敷地内薬局に名乗りを上げる薬局も薬局だ。次期診療報酬改定では、敷地内薬局は院内処方と同じ点数にすべきではとも考えてしまう。
ただ、最近の日薬の総会での質疑などを聞いていると、現場の薬剤師は、自分たちが周りから厳しいバッシングを受けていると認識しているのかどうか疑問が残る。さらに、国が「門前から地域へ」と旗を振ったからといって、何の努力もせずに患者が地域の薬局に来てくれるとは限らない。
そう考えると、地域に敷地内薬局ができてしまったとしても、やるべきことは変わらないのではないか。地に足をつけて、かかりつけ薬剤師・薬局の活動を進めると共に、多職種と連携して地域で顔の見える関係を構築することが何より大事になるだろう。