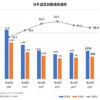第57回日本薬剤師会学術大会
座長
日本薬剤師会副会長
渡邊大記
埼玉県薬剤師会理事
大嶋繁
昨年の学術大会に引き続き、デジタル技術を用いた治療(DTx:Digital Therapeutics)に焦点を当てた分科会の開催となる。しかし薬局を含めた医療現場においては、どれくらいの先生方が治療用アプリの現状と今後の展開を注視されているだろうか。
現在、国においてはプログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略(DASH for SaMD:DX[Digital Transformation] Action Strategies in Healthcare for SaMD[Software as a Medical Device])が第2段階(DASH for SaMD2)として動き始めている。
そこには新たなパッケージ戦略として、実用化促進に向けた申請・審査への支援体制や承認方法の検討と共に、医家向けSaMDからの転用を含む一般消費者を対象とした家庭向けプログラム医療機器の考え方を整理していくことも盛り込まれている。これらのアプリは治療に供する新たな手段として注目されており、既存の薬物療法との併用による相乗効果や医療費削減効果などが期待されている。
つまり、薬剤師にとって薬剤に関する知識を持つのと同じように、治療用アプリに関する知識を合わせ持つことも大変重要な位置付けになってくる。もちろんこれらの領域が医療現場等で実用化されていくに当たっては、適応された患者にとっても初めて使用することになる。
患者がいかに活用方法を理解して治療を継続してもらえるかが重要であり、そのためには導入時の不安を軽減し、使用中のフォローアップを薬剤師が担い、処方医と連携していくことが治療用アプリの効果につながるだろう。そのためには薬剤師がDTxに用いる医療機器を使いこなす一定のデジタルリテラシーおよびヘルスリテラシーを身に付けると共に、このような領域に関心を持ち、その知識を持つ必要がある。
今回の分科会では、早くからこの治療用アプリの臨床活用における医師と連携した薬剤師の関与の必要性について取り組まれてきた和歌山県立医科大学薬学部の赤池昭紀先生や、実際に承認申請の現場を担われているPMDAの石井健介先生、そして治療用アプリの開発に取り組み、実用化を図る先駆的な企業の立場からご講演をいただき、今後の医療における新たな分野への取り組みに薬剤師として理解を深める機会となれば幸いに思う。
(渡邊大記)