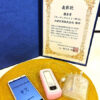宮崎智氏(東京理科大学薬学部教授)
東京理科大学、北海道薬科大学、岐阜薬科大学、武庫川女子大学など、全国の薬系大学9校(学部)が協力・連携して、指導薬剤師・学生・大学の連携を支える「実務実習進捗ネットワークツール」を開発した。プロジェクト中心メンバーの宮崎智氏(東京理科大学薬学部教授)は、「学生の長期実務実習の理解度・到達度が見えるシステムで、長期実務実習がスタートする5月前に提供していきたい。その後のメンテナンス経費も、1校当たり20~30万円程度と考えている」としている。支援ツールは連携校以外の希望校に対しても、提供される予定だ。
ネットワークツール開発の引き金となったのは、文部科学省の医療人GPに採択された「全国的薬学教育グリッドの構築」。東京理科大を中心に全国11大学が連携して、実務実習に必要な知識を効率的に測るための新規出題形式も視野に入れた、自己学習システムの開発が進められてきた。その一環として、今年度から新たに3年計画で「大学連携による6年制薬学教育を事例とした標準的な基盤教育プログラムの開発」が進められ、その成果の一つとして「実務実習進捗ネットワークツール」が開発された。
宮崎氏は「実際に学生が実務実習に行ったとき、その進捗状況をうまく把握、管理できる入れ物を作ろうと進めてきた」と説明する。
支援ツールには、実務実習コアカリキュラムに沿って、実習を進めるためのひな形も組み込まれている。コアカリキュラムでは、実務実習の到達目標が策定されているが、それを実施するための方略については、共通基盤が構築されていないのが現状。ひな形は、その標準的な指導マニュアルに相当する。
プロジェクトは東京理大を中心に、昭和大、帝京大、徳島文理大、北海道薬大、岐阜薬大、東京薬大、東北薬大、武庫川女子大の9校で構成されている。宮崎氏は「支援ツールは、医療人GPを介して9大学連携のプロジェクトとして、作成に当たってきたものだが、当然、連携大学以外にも、使いたい大学には無料で提供するよう位置づけている。実装は次年度以降になるが、それも予算の範囲内です」と、連携校以外にも提供する用意があるとしている。
支援ツールの使用に当たっては、インターネット上でログインする必要があり、そのためにはまず登録が必要になる。薬局等の受け入れ施設側には、施設側の判断によって、1つ以上のID、パスワードが配布される。
支援ツールを開発した基本理念として、宮崎氏は「あくまでも、学生が到達目標を着実に理解し、できるようになればいい。他のシステムに見られるような、いつ何をするかというスケジューラーには関心がない」とし、他システムとは異なって、シンプルな内容になっていることが特徴だと指摘する。
その一方、実務実習の進捗状況をきちんと把握・管理できるような評価面には、十分な対応がなされている。実務実習は、調剤にしても情報収集にしても、1回で終わるものでなく、何回か行うことになるが、その自己評価を学生が何度も入力することができ、履歴として残るようにしてある。一つの到達目標に対して、「学生の理解度・到達度が見える」システムだと、宮崎氏は強調する。
学生が新たに入力した場合、その更新内容が大学・施設側でも分かる仕組みになっている。また、施設側から、学生の自己評価、実習状況を踏まえて、理解度に対するコメントが入力できる仕組みも取り入れられている。
ただ、実際に支援ツールを活用するに当たっては、自己評価を書き込むタイミングなど、運用するための共通基盤に、多少問題を残している。実習先によってパターンがあるため、毎週書き込むようにといった大学サイドから規制などは一切ないが、どの段階で書き込むべきかは、レールが敷かれていない。宮崎氏は「学生個人が判断するというより、むしろ実習先の指導薬剤師が学生とコミュニケーションを取って、学生が自己評価を入力できる段階かどうかを判断する。あるいは、指導薬剤師の指示で学生が入力するというのが妥当だと思っている」と、指導薬剤師と学生の関係構築が重要だと指摘する。
また、実習の評価に関しては、「このシステムに入力したら評価が終わるとは全く考えていない。あくまで実習の記録、進捗状況を管理することが焦点であり、大学の先生にとっては、どれだけ入力があり、どんなことを勉強したかが分かれば十分」だとした。
学生の入力については、学生自身あるいは実習先のインターネット環境に配慮し、携帯電話をインターフェイスとして活用することも検討している。また、先行している富士ゼロックスとの相互乗り入れも検討中で、「富士ゼロックスさんのシステムを使いたいというときには、共通項目のデータを移行できるようにしようと思っている」という。
費用に関しては、国のプロジェクトであるため、少なくとも3年間は無償。後はメンテナンス費用だけという形になる。現時点において、「1人当たりではなく、1大学当たり20~30万円程度と考えている。実際にはデータが各大学の中継サーバーに保存することを考えており、学生数の大きな大学が参加しても、センターサーバーが窮屈になるという事態はあり得ず、人数に応じた料金設定は考えていない」と、低コストが特徴の一つとなっている。各大学でのデータ管理には、既にCBT用に中継サーバーが置いてあることから、その活用も考えられている。
現在のシステムはプロトタイプであり、「2~3年は、様子を見ながらということになる」とし、改良を重ねていく方針だ。