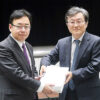日本薬剤師会通常代議員会が2月24、25の両日に開かれた。質疑では後期高齢者医療制度、一般用医薬品の販売制度と登録販売者試験、基準薬局制度、会員・会費問題、学校薬剤師問題など多彩なテーマが取り上げられた。今回は役員改選がなく、調剤報酬も改定の谷間に当たるという状況であったが、多くの記者が取材に詰めかけた。記者の関心は、日本調剤と久留米三井薬剤師会との“もめ事”として再浮上してきたFAX分業問題。だが、FAX分業を含め議論が白熱する場面もなく、集まった記者連も肩すかしを食った格好だ。
ここ数年を振り返ると、役員改選期を別にすれば、日薬代議員会は極めて紳士的になった印象を受ける。また、現場で働く薬剤師は女性が多いにもかかわらず、女性の代議員や理事が少ないことも寂しく感じられる。この点は質疑でも取り上げられたが、改善が望まれよう。
日薬代議員会の議事運営は、初日の会長あいさつに続いて、理事者から会務・事業の中間報告が行われる。さらに重要事項報告として、日薬が直面している問題への対応や活動状況、方針などが示されるというのが例年のパターン。ちなみに今回の重要事項は、[1]医療制度改革[2]医薬品販売制度改革[3]薬学教育6年制[4]その他(基準薬局、中央社会保険医療協議会関係、後発品の使用促進など)――であり、質疑の前に執行部から予め“回答”が説明される仕組みだ。
質疑はこれら重要事項報告を聞いた上で行われる。特に調剤報酬の改定や制度改革といった高度な政治判断が必要となる事項、あるいは水面下で議論され正面切って問い質しにくい内容の場合は、ブロック代表質問や一般質問で当初説明以上の回答を引き出すことは困難と考えて、紳士的な質疑に落ち着いてしまうのかもしれない。
ところが、今回初めてブロック代表に立ったある代議員は、次のように漏らした。「ブロック代表質問は、まず県で質問を上げ、さらにブロックへ上げる。その過程で丸みを帯び、上澄みみたいになってしまう。また質問の数も多くて、焦点が定まりにくい」と。全くその通りである。さらに「地域の話を日薬の幹部に話しても仕方ない。地域の問題は地域で解決すべきである」とも指摘する。加えて質問者の職域が、質問の角度や深さに影響することも間違いない。
例えばFAX分業の問題は、最近話題になっている久留米市以外に、高松市でも別の視点から事例が表面化しつつある。ことの重大さを別にすれば、全国どこの地域でも、少なからず“爆弾”を抱えていると思う。ただ大切なことは、処方せんを送信という形で、FAXを保険医療の一部として利用する以上、どこの地域であっても適正に運用され、その状況が開示されなければなるまい。
日薬代議員会は、全国から薬剤師会の代表が集まる会議だ。何よりも患者のためという視点に立ち、温度差を小さくし、互いに律し合うための声明なり政策提言はできなかったのだろうか、非常に残念に思う。
後期高齢者医療制度が創設される。超少子高齢時代を迎え、高齢化率が急激に高まる中でセットされた大改革である。高齢者医療の大きな課題として、医薬品の多剤併用、重複投与が強く指摘されているにもかかわらず、薬剤師は制度の大枠を検討する場から外された。「新しい診療報酬体系の骨子」が決まった後に、委員として議論に加わるだけである。こうした流れに、危機感を覚えた代議員も多いのではあるまいか。新制度の中で薬剤師はどのような役割を果たしていくのか、本音の熱い議論が聞きたかった。