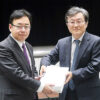先月20日から始まった「登録販売者試験実施ガイドライン(GL)作成検討会」。改正薬事法の目玉である登録販売者制度に関して、まずは国が関与すべき部分の明確化を図るのがこの検討会のスタンスだ。
ここで検討するGLの項目は、▽試験の出題範囲▽試験の実施方法▽受験資格――の3点となる。今月14日に第2回の検討会が開かれ、「試験の出題範囲」についてのヒヤリング等が行われる予定だ。今後、6月頃までに意見の取りまとめを行い、遅くとも8月にはGLが示されるものとみられる。
医薬品小売業界内外を問わず、その動向は大きく注目されているが、「資質認定であって資格ではない」と強調されることが多く、それも間違いではない。しかし、医薬品リスク分類で販売できる範囲は限定されるとはいえ、これまで薬剤師にしかなかった医薬品販売の属人的な資質認定が付与されるという意味では、これまでの一般用医薬品の供給体制が大きく変わる方向にあるといえよう。
ただ、GLは、あくまでも国が示す一つの基準にしか過ぎない。そのため、試験の出題や実施方法などについては、認定する地方自治体の特色を打ち出すことが可能だ。とはいえ、認定が全国的に通用するものと考えれば、やはり「受験資格」だけは統一化せざるを得ない話で、今回のGL作成の最大の注目点になろう。さらに、配置販売業の新規認定ともリンクするだけに、一筋縄ではいかない状況もある。
受験資格については、「高卒以上、1年程度の実務経験で落ちつくのでは」との小売関係者の観測もある一方で、実務経験に関しては、既存の薬種商販売業認定試験並みの3年程度を要望する向きもある。また、ドラッグストア業界では、登録販売者試験の初年度には全国で5 07万人の認定を想定しているとの見方もあるという。さらにコンビニ、スーパーなどの参入も考慮すると、受験資格次第では大量の受験者が発生する可能性は高い。
登録販売者をめぐっては先日、医薬品販売の業界団体関係者らが、登録販売者の養成から生涯教育などの支援事業を行うための組織「日本登録販売者協会」(仮称)を立ち上げることを発表した。今秋にも本格的な活動を開始するとのことで、GL作成を視野に、登録販売者の受け皿としていく意向のようだ。ただ、中身については、日本チェーンドラッグストア協会主導の感は否めない。独断専行ではなく、幅広く認知されるには、他の薬業小売団体などとのコンセンサス作りも課題となろう。
いずれにしても、今年夏までのGL作成を受け、その後、都道府県で条令改正などの調整が行われた上で、2009年の登録販売者試験実施というスケジュールは固まっている。さらに、既存の一般販売業、薬種商販売業も経過措置を経て12年度には店舗販売業に統一され、時同じくして薬学6年制第1期の薬剤師も誕生する。その時期には、薬局と店舗販売業それぞれの医薬品供給の果たすべき役割分担もさらに明確化されよう。
医薬品販売制度の見直しの趣旨は、一般用医薬品の適正かつ安全な使用を確保するため、購入時に的確な情報提供を行える体制整備をすることだ。誤解を恐れず言えば、その提供者は「薬剤師」でも「登録販売者」でも、一般市民にとって良き理解者・相談者であれば問題はないはずだ。登録販売者という医薬品販売認定の落としどころはまさに、そこにあると思う。
今後もGL作成に向けた検討会の推移をしっかりと見守りたい。