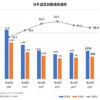激動の2024年が終わろうとしている。今年は元日から能登半島地震が発生し、未曾有の自然災害からのスタートになった。9月には追い打ちをかけるように被災地に記録的豪雨が襲った。宮崎県沖で発生した地震では、初めての「南海トラフ地震臨時情報」が発表され、改めて災害大国に暮らしていることを実感する出来事が相次いだ。
日本経済もインフレによる物価上昇が地盤沈下に拍車をかける1年となり、直近の発表では国民1人当たり名目GDPは世界22位に沈んだ。日経平均株価がバブル期超えを果たし、4万円を突破するという景気のいい話題もあったが、その一方で対ドルの円相場は一時1ドル160円台まで下落した。コメ価格の高騰が象徴するように、円安下の物価高が国民生活を直撃しており、この状況は簡単に改善しそうにない。
薬業界も足下では、解決に向けた道筋が見えない医薬品の供給危機に追われ続けた。本紙でも「限定出荷」「出荷制限」「出荷停止」といった言葉が紙面に掲載されない日はないほどで、それだけ医薬品の供給が不安定化していることを象徴した出来事だったとも言えるだろう。
こうした中で、来年度の中間年薬価改定が決着した。秋の衆議院議員総選挙で自民・公明の与党が過半数割れし、中間年改定の廃止を訴えていた野党の国民民主党が議席を伸ばしたことで力が強まり、廃止に向けた機運はかつてなく高まった。しかし、最終的には新薬創出等加算対象品目、後発品、長期収載品などと品目ごとに改定対象の範囲を設定し、メリハリを付けて実施する内容で決着した。
中間年改定の対象範囲が前回より縮小される見通しとはいえ、昨今の医薬品供給危機は毎年薬価改定の影響が大きいことは明らかだ。今回の改定がさらなる打撃となるのは必至で、製薬企業での製造のみならず、医療機関、薬局の現場で医薬品の調達に苦労する混乱が続くだろう。
来年の通常国会では医薬品医療機器等法の改正案が提出される見込みである。政府は安定供給体制確保のための体制整備を法律に位置づける対策を打ち出したが、不採算が問題の本丸である以上、どこまで実効性があるかは未知数だ。このまま行けば、来年は供給危機がさらに重大な局面を迎える可能性もある。
国民にとってもインフルエンザやマイコプラズマ肺炎が猛威を振るう今冬、医薬品不足を身近に感じる機会があったのではないだろうか。
来年の干支は「乙巳(きのとみ)」であり、「努力を重ね、物事を安定させていく」という意味を持つ年とされている。医療費の財源には限りがある中にあっては、国民の理解と協力も必要不可欠である。多難な時代だが、来年こそは国民を含めた全ての関係者が努力を重ね、医薬品供給を安定させていく。そんな明るい光を照らすような1年になってほしい。