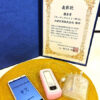政府は7日に予算編成や政策の指針となる「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針)を閣議決定した。社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進では、医療・介護分野のDX推進、医薬品の品質・安定供給の確保と創薬力の強化、リフィル処方箋の普及・定着に向けた仕組みの整備の実現などが盛り込まれた。
後発品とバイオ後続品に関する記述で骨太方針21から書きぶりが変わったことに注目したい。後発品は「品質と安定供給に関する信頼性の確保、数量シェアを23年度末までに全都道府県で8割以上とする新目標についての検討、医療機関別の使用割合を含めた実施状況の可視化を早期に行うべき」と記載していたが、今回は言及がなかった。
一方、バイオ後続品は「医療費適正化効果を踏まえた目標設定を検討、さらなる使用促進を図る」としていたのを、「医療費適正化効果を踏まえた目標値を今年度中に設定し、着実に推進する」と踏み込んだ。低分子後発品で数量シェア80%を達成し、バイオ後続品に軸足を移していくことを明確にした。
まずは使用促進の目安となる具体的な目標値を設定することが重要だ。後発品も80%の数量目標を掲げることで医療従事者や患者、国民にもどのくらい使えばいいかが分かりやすくなり、業界にとっても将来の市場規模からどれくらい投資すればいいかを判断できた。
低分子後発品の置き換え率のように「数量」で測定する方法は、承認品目数が少ないバイオ後続品では新しい品目が承認されると、計算式の分母が一時的に大きく変わるため、目標設定としてはなじまない。日本バイオシミラー協議会が提案している「医療費適正効果額」など様々な評価指標の中からバイオ後続品の特性に合った最適な指標を採用し、早期に目標値を決定してほしい。
バイオ後続品の使用推進には、国民・患者、医療従事者への啓発、診療報酬上の措置などを行う必要性が指摘されているが、同時に日本のバイオ産業を育成しなければならない。
バイオ後続品を含むバイオ医薬品の研究開発や製造は、一部の製薬企業を除き基盤が脆弱で、海外バイオ企業に大きく遅れ、分業も進んでいない。現状では国内企業が開発中のバイオ後続品より、既に承認を取得し製法が確立した海外製が選ばれやすい。新型コロナウイルスの感染拡大で海外製のワクチンや治療薬に依存することになった。バイオ後続品の国産化を急がなければ、必要な薬を確保できない悲劇が繰り返されることになる。
さらに、懸案となりそうなのがバイオ医薬品のオーソライズドジェネリック(AG)の取り扱いをどうするかだ。バイオAGに優先してバイオ後続品が採用されるのは難しく、競争環境の検証も必要になる。