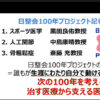2023年は医療機関、保険薬局のDX元年と位置付けられる年となりそうだ。薬局では、患者の保険資格がその場で確認できるオンライン資格確認の導入と合わせて、1月26日から同基盤を活用した電子処方箋管理サービスへの対応に追われている。
医療機関、薬局でのオンライン資格確認の本格運用が始まったのは21年10月だが、療養担当規則等の改正で、4月にはオンライン資格確認の導入が原則義務化される。これら要素も薬局などの取り組みに拍車をかけている。
薬局が電子処方箋を活用するためには、オンライン資格確認等システムの導入が前提となる。その際、患者の健康保険を認証する顔認証付きカードリーダーの導入に加え、レセコン改修が必要となる。電子処方箋対応でも別のレセコンシステムの改修が必要になる。
現在、全国の薬局におけるオンライン資格確認導入(1月29日時点)について、資格確認に必要な顔認証付カードリーダーの申込率は94.8%、接続率77.3%、参加率70.6%で推移しているが、3月末までの100%導入は厳しい状況だ。
この現状を受け、厚生労働省は導入困難な薬局等に期限付きの経過措置期間を設ける通知を発出している。具体的には、今月末までにシステム事業者と契約締結したものの、導入に必要なシステム整備が未完了の薬局などを対象に「遅くとも9月末まで」とし、これら経過措置の対象薬局等に対しては、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームや郵送によって猶予届出書を3月31日までに提出することを求めている。
一方、電子処方箋については、厚労省が公表している電子処方箋サービス対応施設リスト(同日時点)によると、対応可能な薬局は187施設、病院・診療所21施設の計208施設である。本格運用の開始直後とはいえ、患者がその恩恵を得られる数ではない。
また、デジタル庁が公表しているマイナンバーカードの累計交付枚数は7530万枚(全人口の67.7%に相当)であり、このうち健康保険証としての利用登録数は4392万件と、全国民の3割程度しか普及していない。そこには、マイナンバーカードに対するプライバシー侵害、情報流出や悪用、紛失時トラブルなどの懸念が払拭されていないこともある。
今後、オンライン資格確認や電子処方箋管理サービス対応可能な施設は増加していくと思うが、国民の認知度も踏まえ、広くかかりつけ薬局などで活用できるようになるには、まだ時間を要するだろう。
やはり、医療DX化においては、ハード面の進化だけではなく、得られる多くの患者情報を積極的に活用することで、薬剤師がそこに介在する価値を示していくことが必要になる。