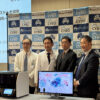1 ミュルレルの胸像
レオポルド・ミュルレルは、ドイツ人の外科医で明治の初め頃に日本に来て、ドイツ医学を最初に教えた医師である。来日したのは明治4年(1871年)8月のことで、同僚の内科医テオドール・ホフマンと一緒であった。二人とも軍医で、ミュルレルは47歳の陸軍少佐、ホフマンは34歳の海軍少尉であった。
特にミュルレルは、当時のわが国の医療体制を見て、本国ドイツの医薬分業とは異なって日本は医者が患者に投薬をしており薬を扱っている。医師から独立した薬学教育を合わせて行い、医師と共に医療を行うべきであるとの想いを強く持った。
翌年には、その建白書を政府に提出した。当時のミュルレルの立場は文部卿に次ぐ地位を委ねられ、発言権は大きかった。建白書をもとに、明治6年(73年)6月に当時の医務局長の長与専斎(欧米の医療事情などを視察)は「製薬学校設立申請書」を政府に提出した。この申請書に長与は、「今、輸入している薬品には不良品や贋薬が多く、国民の健康に悪影響を及ぼす恐れがある。薬学によって真贋鑑別や製薬を行う必要がある」などを強調した。

2 ミュルレル胸像の全体像
政府は直ちにこれを認め、翌7月25日に第一大学区医学校に「製薬学科の設置」を布告し、9月開校となり、わが国の薬学教育が始まることになったのである。ミュルレルらは3年間の契約を終えて、明治8年(75年)11月に帰国した。このようなことから、薬学者にとっては、その功績に敬意を表しミュルレル没後の3回忌の明治28年(95年)に胸像を建立し、現在の薬学部の敷地内に設置した。
この胸像はブロンズ像で、戦後盗まれたことがあったが、昭和50年(1975年)に復元された。ミュルレルはわが国で最初にドイツ医学を教え、また薬学教育の必要性をも主張し実現させたので、医学・薬学の恩人であると言えよう。ミュルレルが生まれたのは1824年6月24日なので、今年は生誕200年に当たる。この胸像については、このような長い歴史があるのである【写真1、2】
胸像の場所

3 下山順一郎の胸像
この胸像がある場所は、東京大学の龍岡門から入り病院へ向かう左側の歩道を進むと、左側に薬学部の校舎があり、隣接する小高い丘の木立の中に設置されている。角地近くに階段があるので、それを上るとミュルレルの胸像に出会う。プロシアの軍医の正装した像になっている。その左奥約5m先には、東京帝国大学医科大学薬学科生薬学の初代教授だった下山順一郎の胸像もあり、人物の説明をした立て看板がある【写真3】
願わくは、薬史を伝えていく意味で薬学を学ぶ学生(特に新入生)に対し、2人の胸像を見せて歴史を教えた後に、隣の建物の薬学図書館に行き、薬史学文庫の書籍をも見せることによって薬学の歴史をさらに感じ取ってもらえるような教育をしてほしいと願う。教科書の活字を読ませるよりは、こうした現物を見せた方が印象に残るであろうし、改めて薬学の歴史に興味を覚えるかもしれない。

4 ミュルレル胸像への階段
4月からは、改訂された薬学教育モデル・コア・カリキュラムにより実施され、そのうちの3割は各校独自の方法で教えて良いことになっている。上述した薬学の歴史を教えることで、社会人になってから役立つのではないかと考える。
しかし、胸像を見るために行ってみると、残念なことに階段付近には立札もなく、胸像があるとさえ気付かない。せめて、立て看板程度で良いから歩道から見えるところに案内板を付けてほしいと切に思う【写真4】
当時の時代背景
明治の新政権は、わが国の近代化を強く推進した。その方策として、諸外国から各分野の専門家を招聘し指導を受け、新しい国づくりに役立てた。特に国民の医療や保健・衛生面については重要な分野であり、医学教育にも早くから取り組んだ。
その中で、ドイツ医学を採用することを決定したのが明治2年(69年)であった。当時のわが国の指導者たちは、どの国からその分野の優秀な専門家を呼び、日本に導入するかを模索していたころであった。例えば、法学関係はフランスが主流で、フランス人が招聘され法学を教えていた。医学では、担当(医学校取調御用掛)であった相良知安(蘭医)がドイツ医学の導入を強力に進言した。
本来は、倒幕に成功した薩摩や長州、土佐の出身者たちがイギリスとは幕末から親しく、特に戊辰戦争で傷病兵に対して熱心に治療してくれたイギリス人医師のウィリアム・ウィリスに恩義を感じ、わが国の医学教育はイギリス式を導入しようと話し合いがなされていた。こうした中で、突然にドイツ医学を、と叫んでもなかなか理解が得られなかった。
相良知安が進言した中に、オランダ医学書はドイツの医学書から訳したもので、ドイツ医学が現時点では世界の最先端であることを強調した。2009年に佐賀市で開催された第110回日本医史学会総会の特別講演において、相良知安より数えて五代目の子孫である相良隆弘氏は「佐賀藩医―相良知安とドイツ医学」の演題で、ドイツ医学に決定したいきさつを次のように述べている(文献:日本医史学雑誌55(2)135,2009)
明治2年6月頃、太政官が出席した廟議(評議)において、相良が決定する役目なのに、何も相談もなくイギリス医学を取り立てるという約束をしたのは正式な手続きを経ない私事であると主張した。これはまさに正論であるので、出席した岩倉具視、木戸孝充、大久保利通、松平春嶽ほかの政府高官たちは反論ができなかった。
大蔵大輔の大隈重信、議定の鍋島直正、参議の副島種臣、会計官の江藤新平らは相良の意見に同調するようになり、次第に政府部内の空気も変わってきて、最後は三条実美太政大臣がドイツ医学の採用を正式に決定した。イギリス医学導入を画策した山内容堂は免職となり、逆に旧土佐藩からは反感を買うことになる。
当時の政府顧問のオランダ生まれで、米国人宣教師グイド・フルベッキも相良を後押しした。岩倉の信任が厚いフルベッキは、来日した当初は佐賀藩英学校「致遠館」で相良や大隈、副島らにアメリカ憲法や政治、聖書を英語で教えていた。
医学の導入先を決める重要な会議のメンバーに旧佐賀藩出身者が多く出席していたように思われるが、たまたま職務上で出ていたに過ぎず、歴史の巡り合わせかもしれない。こうしてドイツ医学をわが国に導入することが廟議で決定され、翌明治3年(70年)2月、政府は北ドイツ連邦公使と医師派遣の契約をした。そして、明治4年(71年)8月にミュルレルらが来日し、ドイツ医学の教育が始まったのであった。
最後に、東京大学薬学図書館の飯野洋一氏(日本薬史学会評議員)にお世話になりましたことに深謝します。
文献
薬学史事典:薬事日報社、2016.
お雇い外国人:講談社学術文庫、2007.
この記事は、「薬事日報」本紙および「薬事日報 電子版」の2024年6月10日号に掲載された記事です。