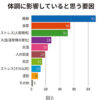世界に先駆け超高齢化社会を迎えるわが国では、団塊の世代全員が後期高齢者となる2025年を目指し社会保障制度改革国民会議報告書に沿った改革が進められている。
実際、疾病治療を地域の中核病院や中小病院、有床診療所などで行ってきた“病院の世紀”が終わりを告げ、総合的解決モデルを必要とする“在宅の世紀”への変遷は避けては通れない状況下にあるのは間違いない。その要因の一つとして、要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移が挙げられる。75歳以上人口は、介護保険創設の00年以降から急速に増加してきたが、25年までの10年間も同じ速度で伸長する。30年頃からは急速に伸びなくなるが、その一方で85歳以上人口がその後の10年程度は増加が続く。
こうした75歳以上の人口推移に伴い、複数の疾患を抱えながら地域で暮らす人が増大していくのは言うまでもない。
医療と介護を同時に必要とする高齢者がさらに増加する中、生きがいを持って健やかに住み慣れた地域社会で過ごし、そこでの終焉を目的とする地域包括ケアシステムの確立が急務となっている。
地域包括ケアシステムの確立で忘れてはならないのが、全国各地で生じるであろう地域差だ。人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市群と、75歳以上の人口増加は緩やかだが人口が減少する町村部では、高齢者の状況やニーズに大きな差が生じてくるためである。
医師・医療資源が少なく、高齢者が増加していく地域では、より地域密着型の医療体制を整備していく必要があるだろう。在宅医療の提供者が少なく、面積が広大なため訪問看護・介護が困難となる過疎地では、医療・介護サービス提供を継続するための集中化を余儀なくされるケースも考えられる。
地域包括ケアシステムの構築は、地域の総力戦、すなわち地域づくりそのものであり、医療従事者は多様な高齢者の状況やニーズに柔軟に対応する必要がある。従って、高齢者ケア対策では、「地域で創り育てる」ことが最も重要であると言っても過言ではない。
では、住み慣れた地域での尊厳ある暮らしの継続をアシストするには、どのようなマネジメントが必要か。
キーポイントとして、▽急激な機能低下の縮小と、穏やかな機能低下のさらなる緩和▽シームレスなケアの実現▽日常の健康管理と重症化予防▽介護と医療のチーム化▽健康管理のための客観的データの収集▽地域ケアマネジメント会議・カンファレンスの開催――などが挙げられる。
これらのマネジメントを実現するには、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・栄養士・臨床心理士・精神保健福祉士などの医療間多職種連携や、医療・介護の連携推進が不可欠となるのは言うまでもない。
今後の包括ケアシステム構築において、地域の薬局・薬剤師にはファーストアクセスの健康支援業務、チームアクセスの在宅医療(在宅復帰・QOL確保、医療安全、多職種連携)に加え、医療間多職種連携におけるコーディネーター的役割も期待したい。