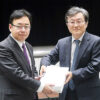1980年に、癌は日本人の死亡原因の第1位となた。現在では死因の31%を占めるまでになっており、2015年には日本人の2人に1人が、癌で死亡するものと予測されている。
癌治療は手術、化学療法、放射線治療に大別される。それぞれにメリット、デメリットがあり、これらをうまく組み合わせて、患者個々にあった治療が行われている。このうち放射線治療は、欧米では癌患者の半数に適用されている。わが国でも癌患者の25%に、放射線治療が初回治療として採用されており、15年には40%まで上昇すると言われている。
近年、放射線治療が癌患者に繁用されるようになったのは、日進月歩の放射線治療技術と機器開発によるところが大きい。これまで日本では、外科的治療が優先されてきたが、症状によっては放射線治療が、外科手術と同等の効果を発揮するまでになった。手術できない進行癌であっても、放射線による治療が可能なケースもある。
頭部、頸部だけでなく、脊椎、肺、肝臓、前立腺などへの治療にも応用可能な世界最高水準の定位放射線癌治療装置として注目を集めているのが、ドイツのブレインラボ社が開発した「ノバリス」だ。ノバリスは画期的なX線による患者位置決めシステムにより、1mm単位のピンポイントで腫瘍の位置を特定する。従ってごく小さな病変や、極めて変則的な病変にも対応可能であり、周囲の正常細胞に対する照射を、最小限に抑えることができる。
ノバリスは現在、世界で90施設、日本では3施設に設置されている。その一つ金沢市の浅ノ川総合病院では、既に頭蓋病変112例、顔面・頸椎病変57例、体幹部病変131例の症例数を誇り、入院を必要としない非侵襲治療(1回平均照射時間15 020分で数回照射)として、癌患者から好評を得ている。奈良県立医大病院は2年前から導入しており、肺癌、肝癌など週平均4例の治療を行っている。京都大学病院も、今年12月に導入する予定という。
ノバリスの保険点数は6万3000点で、脳、脊髄、肺、肝臓の腫瘍に保険適用が認められているが、前立腺癌は適用外になっている。ノバリスの保険適用施設となるには、専属の医師及び放射線技師各1人、医学物理士1人を置く必要がある。医学物理士は数が足りないため、今後の養成が急務となっている。
一方、強度変調型放射線治療(Intensity Modulated Radiation Therapy:IMRT)は、放射線の照射口に厚い鉛を取り付け、それをコンピュータで制御することにより、病巣の形状に合わせて放射線ビームごとに方向、照射範囲、強さなどをきめ細かく調節できる。IT技術が医療で最も成功を遂げた一例と言っても過言ではない。
複雑な形状の病変でも、ビームを瞬時にその形状に一致させ、放射線量の強弱を調整することで、正常組織への被爆を軽減、病変部のみへの高線量照射を可能とした。1回当たりの平均的な照射時間も、15 020分と短い。
日本でIMRTが行われている施設は20カ所程度だが、京都大学病院では前立腺癌150例、頭頸部30例、脳腫瘍10例の症例数を有する。前立腺癌では、2年生存率が予後良好群で95%、不良群で75%の成績を示している。今後、呼吸によって動く臓器表面のマーキング技術が開発されれば、膵臓癌への応用も期待できるという。IMRTは今年4月から、先進医療として厚生労働省の認可を受けている。
文部科学、厚生労働の両省は「第3次対がん10カ年総合戦略」を策定し、癌の予防法確立や画期的な治療法の開発を通し、生存率の20%向上、治療に伴う副作用の半減を目指している。また昨日閉幕した通常国会では、「がん対策基本法」が成立し、適切な癌医療の提供体制を整備する基盤がつくられた。今後、放射線治療が癌医療の大きな柱の一つとして果たす役割に注目したい。