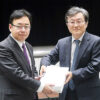グランキューブ大阪で

狭間氏
日本在宅薬学会(理事長:狭間研至氏)は15、16日の2日間、大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)で「『在宅薬学』の夜明け~その実践とエビデンスの構築に向けて~」をテーマに、第11回目となる学術大会(大会長:狭間氏)を開催する。今回は大会長講演、基調講演、教育講演2題、シンポジウム10題、ワークショップ3題のほか、一般演題、各種セミナーなどのプログラムが行われる予定で、約1600人の参加者を見込んでいる。
大会長を務める狭間氏は、学術大会開催を前に「在宅医療の現場で活躍する薬剤師が増加する中で、具体的な実践においては経験論だけではなく、在宅医療に参入するための薬学的エビデンスの構築が必要になる。その系統立った取り組みを学術大会を通して追求していただければと思う」と抱負を語る。
日本在宅薬学会は、2009年11月に発足した「在宅療養支援薬局研究会」がその前身。当初は、薬剤師向けにバイタルサイン講習会開催などを主事業として展開。その後、病院薬剤師の参画もあり会員数が増加。12年から日本在宅薬学会と名称変更し、学術大会を毎年開催している。
学術大会の特徴について狭間氏は、「薬局薬剤師、病院薬剤師のみで在宅医療を考えるのではなく、大学薬学部、厚生労働省、医師会関係者のほか、医師、歯科医師、看護師、介護職など多くの職種が参加することで、医療全体から薬剤師や薬局のあり方を在宅医療の分野から考えていこうという取り組み」と強調。
その上で、「この国における在宅医療の今と未来が実感できると思う。今、在宅に取り組んでいる人も、そうでない人も地域包括ケアシステムの中では外せない要素について、学会を通じ、その雰囲気、臨場感などを実感していただければと考えている」としている。
今学術大会のプログラムでは、国家戦略特区でスタートしたオンライン服薬指導の取り組みで、実際に福岡市での実証に関わるIT企業代表で医師である武藤真祐氏による基調講演が注目される。また、在宅医療業務を展開する上で、増える対物業務量の軽減で避けては通れない非薬剤師(パートナー)の導入や活用の実際に向け議論を交わすセッションも予定されている。
主なプログラムは次の通り(シンポジウム、ワークショップは演題のみ)
▽大会会長講演:在宅薬学の夜明け=狭間氏
▽基調講演:オンライン診療の現状と未来、そしてオンライン服薬指導への道筋=武藤真祐・医療法人社団鉄裕会理事長/インテグリティ・ヘルスケア代表取締役会長
▽教育講演:[1]地域包括ケアに貢献する医療連携と薬剤師の責任=佐々木均・長崎大学病院薬剤部長教授[2]薬剤師の社会的役割の向上と職能の高度化を目指して=紀平哲也・厚労省医薬生活衛生局総務課薬事企画官
▽シンポジウム:[1]平成30年度診療報酬改定後の病院・薬局薬剤師―未来志向で考える薬剤師へのミチシルベ[2]介護保険が使えない!誰がケアをマネジメントするのか?―家族に過度な負担がかからないために[3]薬局での店頭対応と健康サポート機能について[4]同職種連携?阪神間での保険薬局・病院薬局薬剤師の連携について考える(薬薬連携)
[5]薬物治療の幅を広げるための漢方薬処方提案―漢方薬は本当に効果があるのか[6]地域医療における感染対策と感染症治療を考えよう!―薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン策定を受けて[7]在宅薬学の実践に活かすガイドラインの理解[8]ポリファーマシー、実効性のある対策とは―理論を語ることから実践への具体策[9]多職種で討論しよう!退院支援―入院時から退院後の生活まで[10]地域包括ケアシステム『ご当地モデル』スペシャルセッション=先進モデルの実態と薬剤師の活躍を知ろう!
▽ワークショップ:[1]糖尿病療養者への薬学的支援および生活視点による多職種連携を考える[2]緊急時に求められること、できること[3]在宅で役に立つ緩和医療領域薬剤師養成講座(基礎編)第2弾