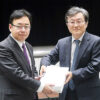調剤メルフィン‐副作用の早期発見・対応を支援
三菱電機インフォメーションシステムズの保険薬局システム「調剤メルフィン」に昨年11月、副作用の早期発見や早期対応を支援するオプション機能が加わった。
副作用自発報告事例データベースを解析し、服薬開始後どの時期にどんな副作用の報告が多いのかを画面に表示。薬剤師はそれを参考に、患者個々のその時の状況に応じた、今注意してほしい副作用の説明を行えることが特徴だ。

医療業界向けコンサルティング会社のマディアが開発し、販売を開始した日本初のシステム「m-SPEHEC」(マディアスピーク)と連携することで、この機能を実現させた。マディアスピークは、製薬会社や医療従事者からの副作用自発報告50万件以上を集積した、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用データベース」(JADER)を自動的に解析し、その結果を示すことができる。
調剤時に薬剤師は、調剤メルフィン画面の「副作用指導」ボタンをクリック。そうすると新規処方薬や現在服薬中の薬が▽14日以内▽15~28日▽29~56日▽57日以上――の服用期間ごとに分けて示される。画面左側に表示される医薬品名を順に選択すると、その期間中にはどんな副作用の報告事例が多いのかが、最新情報から示される仕組みだ。
添付文書には通常、多数の副作用が羅列されている。情報を調べたり、患者と話したりする時間には限りがある中、この仕組みを活用することで、今どの副作用に注意する必要があるのかに焦点を当てた服薬指導を行える。服薬初期に発現しやすい副作用と、長期服薬時に発現傾向が高い副作用を明確に意識した注意喚起が可能で、薬機法改正で義務化予定の服用中のフォローアップも支援する。
このほか、患者への説明内容や次回指導計画を自動的に文章化して電子薬歴に保存する機能や、患者の症状から副作用か否かを検討する機能も備えている。この機能は、望月眞弓氏(慶應義塾大学薬学部教授)が主任研究者を務めた厚生労働省科学研究の結果をもとに、望月氏の監修を得て開発。システムのアルゴリズムは、中村敏明氏(大阪薬科大学教授)の指導のもとで開発した。
15店舗全店で利用しているすずらん薬局(広島市)の薬剤師は「同じ処方が継続している患者さんへの服薬指導内容を考える手立てとなり、指導の根拠を薬歴にも記載できる。患者さんにも数字を示して説明できるので、理解を得やすい」と評価。
また、「添付文書に未記載の副作用の情報を確認、指導することで、今まで以上に副作用を未然に防ぐことができ、薬剤師の知識の向上にも有益」と話している。
三菱電機インフォメーションシステムズ
http://www.mdis.co.jp/products/melphin/index.html