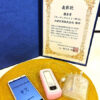厚生労働省は、昨年3月に改訂された流通改善ガイドラインに基づく取引実態の状況や単品単価交渉の実施状況に関する調査結果を20日の「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」に示した。基礎的医薬品などの別枠品や新薬創出等加算品の乖離率は全体の乖離率よりも低く収まっていた一方、交渉形態別の区分ごとでは交渉形態の77%を占める「本部等との一括交渉」の場合は単品単価交渉率が34%で、そのうち価格交渉代行業者と交渉している場合は15%と低い割合になっていたことが判明。病院団体の構成員からは価格交渉代行業者の単品単価交渉率の低さを懸念する意見が上がった。
調査は、医薬品卸8社の協力を得てアンケート等により実施。改訂ガイドラインでは医療上の必要性の高い医薬品として、基礎的医薬品、安定確保薬(カテゴリーA)、不採算品再算定品は「交渉段階から別枠」とし、単品単価交渉を行うよう強く要求しているが、今回の調査では別枠品の単品単価交渉の実態把握を行った。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。