薬局が自ら製造し、自局だけで販売できる「薬局製剤」。実は、一般の医薬品と違うルールがいくつも存在します。この記事では、薬局製剤の概要や許可・申請手続き、そして現場で役立つ情報を詳しく解説します。法令に基づくポイントをまとめつつ、理解を深めるための具体例や活用方法もご紹介します。
目次
1 薬局製剤とは何か
2 なぜ薬局製剤が必要とされるのか
3 製造・販売のルール
3-1. 製造時の注意点
3-2. 販売・情報提供時の注意点
3-3. 法的責任と義務
4 許可・申請の流れと重要書類
5 薬局製剤の最新動向とその現状・必要性
6 まとめ
1. 薬局製剤とは? 薬局製剤の基本知識
薬局製剤の定義と特徴
薬局製造販売医薬品(以下、薬局製剤)とは、「薬局が独自に製造し販売する医薬品」です。
具体的には、薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を取得した薬局が、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与することのできる医薬品のことです。厚生労働省の「薬局製剤指針」に基づいて製造します。
この制度は、患者さんや地域住民に必要な薬を柔軟に提供できるように作られました。しかし、他の薬局や医薬品卸などへの販売は認められていません。あくまでも「自局で製造し、自局だけで販売」することに特徴があります。
例えば、軟膏やうがい薬等、一部の基本的な製剤を薬局内で製造することがあります。漢方薬の調剤で、薬局独自の組成を工夫するケースも考えられます。いずれも、許可と申請の手順を踏んだうえで製造・販売することが求められます。
2 なぜ薬局製剤が必要とされるのか
医療現場では、患者さんそれぞれの症状やライフスタイル、服薬しやすさを考慮した薬が必要とされています。
一方で、大手メーカー製の一般用医薬品だけでは最適な提供が難しい場合もあります。
そこで、薬剤師の専門性を活かした薬局製剤が重要視されています。
製薬メーカーとの違い
薬局製剤の製造販売は、法律上は製薬メーカーと同じ「医薬品製造販売業」に該当します。しかし、小規模な薬局での運営を前提としているため、様々な特例と制限が設けられています。
主な特例として、許可・承認の権限が厚生労働大臣ではなく都道府県知事に委任されていること、薬局の設備をそのまま製造に使えること、薬局の管理者が製造責任者を兼務できることなどが挙げられます。
一方、制限としては、簡単な物理的操作(混ぜる、溶かすなど)で製造できるものに限られること、注射剤は製造できないこと、薬局業務に支障が出ない規模での製造に限ることなどがあります。
| 項目 | 製薬メーカー(専業) | 薬局製剤 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 許可・承認の権限者 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事(または保健所設置市長・区長) | 手続きが身近な自治体で完結する。(国から権限が委任されている) |
| 製造所の設備基準 | 医薬品製造業としての専用基準 | 薬局としての構造設備基準でOK | 薬局の設備をそのまま使える。大がかりな専用設備は不要。 |
| 製造できる品目 | 多様な医薬品 | ①簡単な物理的操作(混ぜる・溶かす等)で製造できるもの ②注射剤は不可 |
合成のような化学反応が必要なものや、無菌操作が必須の注射剤は製造できない。 |
| 製造できる規模 | 制限なし | ①薬局の管理者が完全に管理できる範囲 ②薬局業務に支障が出ない規模 |
あくまで薬局業務がメイン。卸売するほどの大量生産はNG。 |
| 責任者 | 総括製造販売責任者と製造管理者をそれぞれ配置 | 薬局の管理者が兼務可能 | 1人の薬剤師が「薬局の管理者」「総括製造販売責任者」「製造管理者」の3役を兼ねることができる。 |
| 手数料 | 全国一律 | 自治体により異なる | 申請先の自治体に確認が必要。 |
薬局製剤は、地域密着型の薬局が独自性を発揮できる魅力的な取り組みです。
3 製造・販売のルール
薬局製剤を進めるには、薬機法や薬機法施行規則(厚生省令第1号等)に基づく多岐にわたるルールがあります。
ここでは製造時と販売時の主なポイントを解説します。
3-1. 製造時の注意点
薬局製剤では、どんな医薬品でも自由に作れるわけではありません。「薬局製剤にふさわしい」として国が指定した品目リストの中から選ぶ必要があります。
このリストは大きく二つに分類されます。一つは日本薬局方収載品目(53品目)で、もう一つは日本薬局方外品目(377品目)です。後者は、国が定めた共通の処方リスト(いわゆる「47処方」など)がベースとなり、漢方製剤などを中心に時代に合わせて見直されてきたものです。
薬局の設備や器具を用いて製造する際は、品質と安全を担保するための試験や記録の作成が求められます。
薬局製剤は法律上GMPの適用外ですが、医薬品としての品質と安全性を確保するため、GMPの考え方に準じた管理が求められます。医薬品は人体に直接影響を与えるものです。誤った製造方法や不適切な管理は、大きなリスクへとつながる可能性があります。そのため、法令を遵守しながら製造することが不可欠です。
具体的には、
- 原材料の譲受記録やロット番号の管理。
- 製造工程での中間試験(重量チェックなど)の実施。
- 完成した薬の安定性や品質を確認するための記録保存。
などです。
薬局製剤を製造する際は、「日本薬局方」に定められたルールに従う必要があります。製剤総則には剤形ごとの基本的な製造ルールが、通則には医薬品製造全般の共通ルールが、一般試験法には品質確認のための試験方法が定められています。
製造・試験に関する記録は、法律により3年間(または有効期間+1年)の保管が義務付けられています。これは単なる法的義務だけでなく、万が一製品に問題が発生した際に、適切に製造・管理していたことを証明する重要な証拠となります。
記録すべき項目としては、作業責任者名、製造日、製造工程の管理状況、製造数量と原料使用量、自家試験の結果、原料・製品の保管状況などがあります。
3-2. 販売・情報提供時の注意点
薬局製剤は「薬局医薬品」に区分されるため、薬剤師による対面での情報提供が大切です。
また、広告や陳列方法にも独特の規制があります。不適切な広告表示や過度な効能の謳い文句は、購入者の誤解や健康被害につながる可能性があります。薬局の信頼を維持するためにも、正しいルールを守ることが求められます。
例えば、「あたかも全ての病気が治る」といった誇大広告は法律違反のリスクがあります。広告する場合は、医薬品の承認された効能・効果の範囲内にとどめる必要があります。
正確な情報を提示し、購入者の理解を深めることで、薬剤師としての専門性を発揮できます。
3-3. 法的責任と義務
薬局製剤の製造販売業者は、以下のような法的責任と義務を負います。
- 副作用報告義務:副作用が疑われる事例が発生した場合、PMDAに報告する義務があります
- 製造物責任法(PL法):製品の欠陥により健康被害が生じた場合、賠償責任を負います
- 販売先の制限:他の薬局や医薬品販売業者への卸売りは禁止されています
- 製造場所の制限:許可を受けた薬局の設備・器具を使い、その薬局の薬剤師が製造しなければなりません
4. 許可・申請の流れと重要書類
薬局製剤を行うには、製造販売業許可や製造業許可、さらに扱う品目ごとの承認・届出が必要です。法律で定められたプロセスを踏まなければ、適正に製剤を流通させることはできません。この一連の手続きは、薬局としての信頼と医療安全を確保するための基盤とされています。
具体的には、
- 「薬局製剤指針」に沿った手続きの記載。
- 地方自治体(保健所等)に対して行う申請書類の提出。
- 有効成分や分量、製造方法などの内容を細かく説明する資料の提出。
などです。
申請して合格すれば、必要な許可証がおりる仕組みです。申請には時間と手間がかかりますが、その過程で安全性や品質管理について十分に学べます。
- 製造販売業許可:製品の品質や安全性に最終的な責任を持つための許可(6年ごとの更新が必要)
- 製造業許可:実際に医薬品を製造する行為(場所)に対する許可(6年ごとの更新が必要)
- 製造販売承認:製造したい品目ごとに、その品質・有効性・安全性を審査してもらう手続き(一度取得すれば更新は不要)
「許可」は事業者の体制に対するもの、「承認」は製品そのものに対するもの、と理解すると分かりやすいでしょう。
5. 薬局製剤の最新動向とその現状・必要性
薬局製剤は、地域医療において患者ニーズに即応する重要な役割を担う一方、取り扱い薬局の減少、原材料の調達困難、費用対効果の低下、さらには医薬品の進化といった外部環境の変化により、現状ではその維持・発展が困難な状況となっています。今後は、薬局製剤指針の改訂や新たな品目の導入、連携体制の強化、そして適切なガイドラインの整備が急務であり、これらの施策を通じて地域医療における薬局製剤の活用と普及を図る必要があります。
薬局製剤指針の現状と改訂提案
厚生労働省は、令和4年12月27日付の改正により、いくつかの品目の削除や備考欄の変更を行い、さらに新たな改訂に向けた検討連絡会議の設置を予定しています。これには、従来の指針に収載されていなかった単味生薬製剤の取り扱い拡充への要望が背景にあり、消費者需要と薬局内製造の実態を踏まえた改訂が求められています。
■地域医療における薬局製剤の必要性
地域医療の充実の一環として、薬局製剤はかかりつけ薬局の機能強化に繋がります。薬剤師が患者と直接対話し、個々の症状や体質に応じた製剤を提供できる点は高いメリットです。しかし、現行の取り扱い業務が煩雑であることや、十分な人材・設備が整わないことが普及の障壁となっています。
■改訂が示す今後の方向性
今後、薬局製剤指針のさらなる改訂を通じて、取り扱い品目の拡充や製剤方法の簡素化、さらに調剤薬局間の連携強化を図ることが必要です。また、薬学教育でも薬局製剤の実習や技術指導の強化を行い、次世代の薬剤師による制度継承を促す動きも重要視されています。
6. まとめ
薬局製剤は、患者さんのニーズに合わせた医薬品を提供できる魅力的な仕組みです。
公的な許可・申請が求められ、「日本薬局方」や「薬局製剤指針」等の基準に基づく試験が必要です。法令遵守と高品質・安全確保のため、正しい手順と情報提供が欠かせません。
製剤の内容を誤れば健康被害が発生する可能性もあるため、慎重かつ正確に進める姿勢が求められます。医療の信頼性を支えるうえで、薬剤師の専門知識が重要になります。
各工程での試験や記録を丁寧に行うことで、顧客満足度とリスク管理を同時に達成できます。
今後は在宅医療や地域包括ケアが拡大する可能性があり、薬局製剤の必要性はさらに高まると考えられています。
| 関連書 『薬局製剤業務指針 第6版』 | |
|---|---|
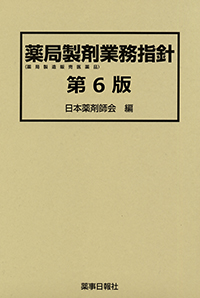
|
薬局製剤(薬局製造販売医薬品)を取り扱うために必要な「指針」とその「解説」に加え「使用上の注意」を3冊セットにした『薬局製剤製造業・製造販売業許可薬局の必備書』。 |

















