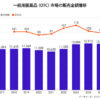これまで、統一されていなかったことは驚きであり、同時に事故・過誤が多発して社会問題にならなかったことも不思議だ。医薬品の処方せん記載方法のことである。このほど厚生労働省の「内服薬処方せんの記載方法のあり方に関する検討会」(座長:楠岡英雄国立病院機構大阪医療センター院長)が報告書を取りまとめ、やっと標準化へ向けて第一歩を踏み出したことは、医療安全の面から大いに歓迎されるべきことだ。
これまで処方せん記載方法の統一について、何も手をつけてこなかったというわけではない。端緒は2002年の厚労科学研究による処方せん記載方法の標準化に向けた検討であり、05年には医療安全対策検討会議から意見が提出されたほか、情報伝達エラー防止のための処方に関する記載についての標準案も示されてきた。
全ての医療機関で統一された記載方法による処方せんが発行されることが望ましいとしながらも、現状では薬品名、1回量、1日量、1日の服用回数、服薬のタイミング、服用日数等を記載することは困難であるとの指摘もあることから、今回まとまった報告書では、内服薬処方せん記載の“あるべき姿”が示されている。
それによると、▽「薬名」は薬価基準に記載されている製剤名▽「分量」は最小基本単位の1回量▽散剤や液剤の「分量」は(原薬量ではなく)製剤量▽「用法・用量」における服用回数・服用タイミングは標準化して情報エラーを惹起する可能性のある表現方法を排除して日本語で明確に▽服用日数は実際の投与日数――の記載を基本に据えている。
提示されたあるべき姿に向かって行動を起こさなければ、単なる絵に描いた餅である。報告書には、短期的(可及的速やかに着手する)方策と長期的方策が記されている。
短期では、処方オーダリングシステム、電子カルテシステム等の入力画面で1回量と1日量を同時に確認できるようにし、出力処方せんには両方を併記することのほか、詳細な記載方法、適切で明解な表現へ是正することを求めている。
システムの変更・改修は、保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)等の業界団体に協力を求めることが明記されており、JAHISとしてはレセプトオンライン義務化(こちらは若干減速気味だが)に続く、追い風となることも期待できる。
特筆されるのは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など医療従事者に対する教育(国家試験への出題)、卒後教育を短期的に、可及的速やかに実施することが盛り込まれていること。処方せんに関わる全医療人の認識を共有することが重要であることを、如実に表しているといえよう。
標準化に向けた道標は示された。あとは、全ての医療人、医療機関、調剤薬局がアクションを起こす番であるが、コストや時間など課題も多く、実現までの道程は遠い。
しかし、ことは患者の生命につながる問題だ。正しい服用、与薬をするために絶対に必要となる処方せん。その処方せんを、患者を含め、誰が見ても同じ理解ができるようにするための標準化は不可欠だ。医療人全員の意識と行動変容が、処方せんに関する医療事故、ヒヤリ・ハット事例を未然に防ぎ、患者を安全へ導くことになることを自覚すべきだろう。