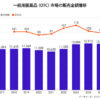ポリファーマシー(多剤併用)の削減が注目を集めている。多剤を併用するなど不適切な処方は、副作用の発現を引き起こし、患者に不利益をもたらす。薬剤費を押し上げ、残薬など薬剤費の無駄も発生する。副作用に対応する費用も必要になり、医療費の高騰を招いてしまうからだ。
診療報酬の改定を審議する中央社会保険医療協議会の場でも最近、多剤併用のリスクが示され、ポリファーマシー削減が論点の一つになった。
また、日本老年医学会が策定した「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」が今月、出版される予定だ。
高齢者は複数の疾患を患うことが多く、多剤併用に陥りやすい。このガイドラインは、高齢者で重篤な有害事象が出やすい薬剤や頻度が高い薬剤をリスト化し、それぞれの推奨使用法を示している。「開始を考慮すべき薬物のリスト」も改訂にあたって新設された。今春提示された案には医療関係者から賛否両論の大きな反響があり、週刊誌などを通じて患者からの注目も集まった。
ポリファーマシーの削減に関心が強まる今は、薬剤師が職能を発揮するチャンスだ。薬物療法全体を俯瞰し、不適切な処方を抽出して、中止や変更、減量などを医師に提案する。それによって処方の適正化が図られると、多剤併用も減少するだろう。このガイドラインには改訂にあたって「薬剤師の役割」が盛り込まれた。薬剤師に対する期待は大きい。
ポリファーマシーは医療の構造上の産物だ。医師は何も悪意があって多剤を処方するわけではない。ただ、医学教育では臓器別に対応する概念が主流になっているため、総合的に患者を捉えることが得意ではない医師が少なくない。なんとかしたいと考えて、症状ごとに、ガイドラインに従って、患者や看護師の求めに応じて薬を処方するうちに、薬の潜在的なリスクを十分に考慮しないまま、多剤になってしまうようだ。
患者は複数の医療機関を受診し、医師はそれぞれの考えで処方する。医師は、他の医師の処方には介入しづらいため、多剤になるという側面もある。患者の薬物療法を一元的に管理し見直すことがどこかのタイミングで必要だが、それが十分に行われていないのが現状だ。
その改善に向けて、入院はいい機会になる。実際に神戸大学病院の薬剤師は、欧州で開発されたスクリーニングツール「STOPP基準」を活用。持参薬から不適切な処方を抽出し、その改善を医師に提案して処方の適正化を推進している。
療養病床や回復期リハビリテーション病床においても、長い入院期間を利用すれば、薬剤師がポリファーマシー削減に取り組みやすいと聞く。
入院中の薬剤調整が退院後も継続されるように、削減理由などを記載した情報提供書を退院時に発行するなど、情報連携の強化も必要だ。