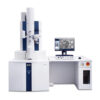(2)川下流通における提言
[1]医薬品卸の価格決裁権限の明確化
上述のように医薬品卸が原価管理に基づき適正な販売価格を設定したとしても、相対の交渉である以上、過去の取引関係等により値引額が増減するのは当然である。医薬品卸の最終的な価格決裁権は一般的に上位職が担っているが、強硬な値引要求をする顧客に対してはMSレベルでの価格決裁権を明確にした上で、組織的に対応する必要がある。
[2]利益マイナスの取引に対する医薬品卸の姿勢
僻地や離島などにおける全国一律の価格設定は、医薬品卸の流通コストを全く配慮していないと言わざるを得ない。これは、流通改善ガイドラインにおける流通経費等の負担の公平性確保の観点からも望ましくない。医薬品卸もそのような取引に対し断る勇気を持って、取引を検討すべきである。
[3]契約に基づく保険薬局との取引価格明示化
保険薬局は医薬品卸との価格交渉における透明性を確保するためにも、交渉期間や交渉方法等を明示し、価格妥結後は医薬品卸と保険薬局間における取引基本契約に準じ、単品ごとの販売妥結価格を覚書として締結すべきである。契約期間は未妥結減算制度に基づき、毎年度9月末までに1年間の価格決定を行うことを前提とするが、経営計画立案時期に応じて医薬品卸とすり合わせを行うことで仕入原価率の設定に反映すべきであろう。
[4]流通コストの明示と公平な費用負担
上述の通り医薬品の製品価値に大きな変更が無いならば、基本的には医薬品卸から医療機関・保険薬局への販売価格水準も大きな変更は道理に合わない。一方で、医薬品卸と医療機関・保険薬局間には配送回数や至急の配送、返品基準等、取引に基づく流通コストが生じている。医薬品卸は医療機関・保険薬局との取引条件を明確にし、医薬品の価格交渉に反映せずに、別途流通コストを負担してもらう仕組みを導入してはどうだろうか。
(3)行政への提言
[1]未妥結減算制度における価格妥結期間の通年適応
上述の通り、価格妥結後の10月以降に価格再交渉が行われている実態がある。医薬品の製品価値に変更が無い限りメーカーの仕切価格は変わらないのであれば、医薬品卸が医療機関・保険薬局への販売価格を下げる道理が無い。取引停止を仄めかす顧客からの強硬な値下げ要請を是正するためにも、妥結価格の通年適応必須化を条件とした未妥結減算制度を検討すべきである。
[2]保険薬局ボランタリーチェーンにおける調剤基本料の見直し
保険薬局ボランタリーチェーンにおいて、本部と加盟店の関係は価格交渉機能のみにおける協調関係であり、経営面では同一グループに該当しないため、調剤基本料1(41点)を算定している加盟店が多い実態にある。しかしながらボランタリー全体の処方箋受付回数が40万回以上と思われるグループがあり、調剤基本料のフリーライダー状態と言えるのではないだろうか。このような状況を踏まえ、調剤基本料の見直しを検討していただきたい。
〔(4)卸の動向〕
流通改善ガイドラインでは、一次売差マイナスの解消に向けて、医薬品メーカーとの仕切価格の交渉についての指摘があったが、上記のようにほとんどの医薬品メーカーが対応せず、医薬品卸の仕切価格および最終原価の悪化につながった。
そのような環境の中、医薬品卸連合会は全国で流通改善ガイドラインの説明会を実施し、各医薬品卸は医療機関・保険薬局との「早期妥結の推進」「単品単価取引の推進」「頻繁な価格交渉の改善」「医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉の是正」「返品の扱いや頻回配送・急配のコスト負担についての流通当事者間での事前取り決め」を推進していくことを目指した。
200床以上の病院では、システム対応の理由もあり前年度の納入価を今年度4月からの暫定価格とするところが存在する。価格交渉に入った際に暫定価格を値上げすることは許容しないという先や前年度と同様のスライド率を要求するところも多々見られた。また一部の購買代行、交渉代行業者においては、全国のある地域で出された価格を取り上げて、それに合わせさせるような要請も行われた。しかし各医薬品卸とも粘り強い交渉を実施し、全体としては値引き率の圧縮につなげることができた。病院要望との乖離幅が大きいところや医薬品卸の最終原価の根拠について納得できないところは、未妥結減算にならないように計算した上で抗がん剤などの高額薬剤を中心に未妥結で終了している。今後も年間交渉を継続するため、まだまだ予断は許さない。
保険薬局では、地域の中小保険薬局についてはこれまでも大きな問題はなく、比較的早期に妥結を進めることができた。全国を網羅している保険薬局チェーンと地域保険薬局チェーンについては、これまでの総価契約から単品単価取引へ移行する上で各医薬品卸に単品単価での見積もり依頼を行うケースが増えた。その後はおおむね二つのパターンに分かれている。
一つ目は単品単価での見積もりを数回実施し、単品ごとに各医薬品卸から出された価格を比較して、最低価格を出した医薬品卸が落札、または従来の帳合卸に最低価格に合わせるように指示するケースである。保険薬局では医薬品メーカーごと、または品目ごとに基本的な帳合卸を決めているが、欠品対応を含むさまざまな理由により同一品目が複数卸から購入されていることが多い。各医薬品卸は過去の納入実績がある品目について自社の利益率と数量をみながら値付けを行ったが、購入側からみて安い品目だけを新帳合として選択されたことにより、全体の値引き率では医薬品卸の想定よりも拡大していく見込みである。
得意先のある品目の全体使用数量が仮に半期で1000本であったとしても、過去の自社実績10本に基づく値付けを行ったことにより、下期からの全体加重は大きく影響を受ける。これは過去の総価交渉では有り得なかった事例である。品目ごとの医薬品の利益ではなく、医療機関・保険薬局ごとの利益を重視した値付けを行った結果であるが、現在の医薬品メーカー仕切価をベースにした値付けでは市場実勢価格との乖離があり、全体加重を引き下げるために調整が行われた。
二つ目は単品単価交渉を行ったというプロセス重視のためだけ単品ごとの見積もりを実施し、その後は見積もりを生かすことなく、従来通りの全体の値引き率を決める交渉に終始したケースである。全体の値引き率で合意した後に、医薬品卸が品目ごとの価値に応じて単品ごとの値付けを行っている。これまでとの違いといえば、前年度までのようにカテゴリーチェンジにより値引き率が動いたとしても、その分を医薬品卸が補償をするということはやらないだろう。これをやってしまえば一律値引きと変わらない。総価交渉の場合、医薬品卸からみれば得意先ごとの利益を確定しやすいという背景もあるが、薬価制度の趣旨を踏まえれば望ましくない。最低でも「新薬創出加算品」「先発医薬品」「長期収載品」「後発医薬品」「血漿分画製剤」「基礎的医薬品」「その他除外品」などのカテゴリーごとに相場観をすり合わせした上で妥結し、価値に応じた単品ごとの値付けを行っていきたい。
病院、保険薬局の双方とも個々の医薬品の価値やメーカーの仕切価が分からないことから、前年度妥結率をベースにした要請を行ってくることに変わりはなかった。しかし厚生労働省医政局の経済課による流通改善ガイドラインを遵守する旨の協力依頼が行われた効果により、交渉期限である9月末に近づくに従って一方的に前年度スライド率を押し付けてくるような交渉は減少した。だがこれまで年間妥結していた先についても、妥結価格への不満もあったことやカテゴリーチェンジの影響を極力なくしたいという意向が働き、半期の妥結先が増加してしまった。「頻繁な価格交渉の改善」については逆に悪化したといえる。
返品の扱いや頻回配送・急配のコスト負担についてはモデル契約書を参考に契約を締結することが望ましいが、4-9月については具体的な進展はみられていない。医薬品卸の共同配送などの流通効率化を含めて、今後の課題として残っている。